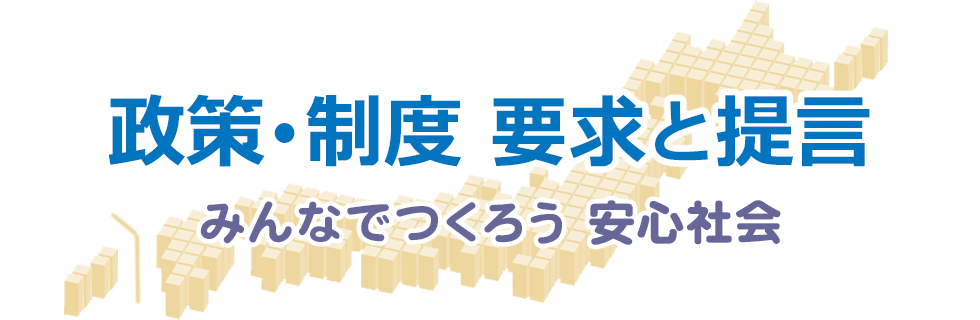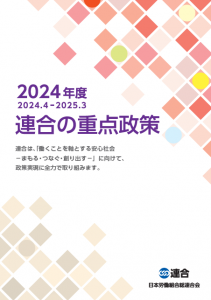複数ワード検索は語句間を半角スペースで区切ってください
更新履歴
- 2024.07.25
[第10回中央執行委員会確認]
を更新しました。
- 2024.05.22
[第8回中央執行委員会確認]
を更新しました。
- 2024.05.08
[第7回中央執行委員会確認]
3.安心できる社会保障制度の確立(医療政策)、(介護・高齢者福祉政策)、(障がい者政策)
7.公正なグローバル化を通じた持続可能な社会の実現(国際政策)
を更新しました。
- 2024.02.29
[第5回中央執行委員会確認]
を更新しました。
- 2023.08.28
[第23回中央執行委員会確認]
を更新しました。
- 2023.06.26
[第21回中央執行委員会確認]
を更新しました。
- 2023.05.19
[第20回中央執行委員会確認]
を更新しました。
- 2023.04.17
[第19回中央執行委員会確認]
4.社会インフラの整備促進(DX(デジタル・トランスフォーメーション))
を更新しました。
- 2023.02.20
[第17回中央執行委員会確認]
7.公正なグローバル化を通じた持続可能な社会の実現(国際政策)
を更新しました。
各種パンフレットの
ダウンロードはこちら