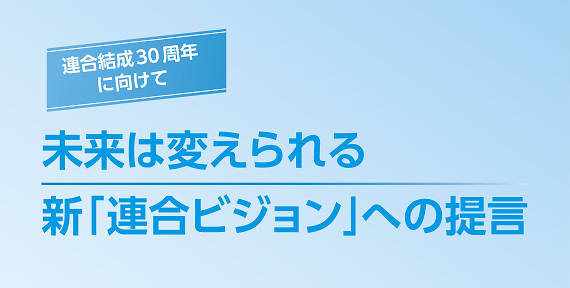
連合は12月20日、「連合ビジョン(仮称)」の素案を組織討議に付した。その策定に向けて議論を重ねた、連合「人口減少・超少子高齢社会ビジョン」検討委員会は、最終報告において、人口減少・超少子高齢社会、情報技術革新、地球環境問題などによって直面する課題を整理しつつ、それでも「未来は変えられる」と投げかけた。これを受けて、新たなビジョンは、「働くことを軸とする安心社会」の深化をはかり、その実現に向けた運動に踏み出すことを強く打ち出した。キーワードは「まもる・つなぐ・生み出す」。素案の活発な職場討議に向けて、3人の有識者から提言を受けた。
提言1-「安心社会」の深化に向けて
まもる・つなぐ・生み出す」 その相互の連関こそ重要だ

宮本太郎(みやもと・たろう)
中央大学法学部教授
1958年生まれ。中央大学大学院法学研究科修了。福祉政治論専攻。立命館大学法学部助教授、北海道大学法学部教授などを経て、2013年より現職。著書に『生活保障―排除しない社会へ』(岩波新書)、『福祉政治―日本の生活保障とデモクラシー』(有斐閣)など。
連合結成30周年という節目に、新たな「連合ビジョン」が提起されることは、たいへん意義深い。
新ビジョンは、2010年策定の「働くことを軸とする安心社会」を深化させるものと位置づけられているが、では、従来のビジョンは、どういう意義を持っていたのか。戦後、日本の労働運動は、「雇用の場」を中心とする生活保障システムを構築してきた。それは、年功賃金による家族扶養も含めた社会保障的機能を持ち、長期雇用を前提に教育機能も担ってきた。結果的に、日本の公的教育は素材育成型教育に留まり、社会保障は「退職後」が柱となった。「雇用の場」を中心として、「教育→雇用→社会保障」と一方通行的に進んでいくライフコースが描かれた。
ところが、経済社会環境の変化の中で、非正規雇用が急増し、雇用による生活保障システムが綻び始める。そのことを受け止め、一方通行型から交差点型の社会システムを構築しようというのが、「働くことを軸とする安心社会」のビジョンであった。教育・家族・雇用・失業・退職の場を行き来できる5つの安心の橋を架け、働くことを通じて社会への参加を保障していく。これは、具体的な政策パッケージによって補強され、国や自治体の政策にも取り入れられてきた。ただ、このビジョンに1つだけ課題があったとすれば、その実現に向けて組合員一人ひとりがどう踏み出していくのか、職場からの行動にどう結び付けるかという問題だった。
そこで、新ビジョンは、「まもる・つなぐ・生み出す」をキーワードに、実現に向けた具体的課題を提起した。何を守り、何をつなぎ、何を生み出すのかについても、具体的な方向づけがなされている。ただ、運動を広げるには、それぞれが相互にどう連関するのかについても、考えておく必要がある。
「まもる」は、まずダイバーシティの広がりの中で、働く仲間一人ひとりを守る。地域・社会では、学び直しや家族の時間を守る。そのための制度として、5つの橋を行き来することで、人生を充実させながらスキルアップするキャリア権を守る。
「つなぐ」は、まず働く仲間を単組につなぎ、仲間同士をつなぐ。そこから地域組織につなぎ、また労働組合が結節点となってNPOなどとの連携を強化し、地域社会を支えていく。それによって、地域全体に5つの橋を架けていく。
「生み出す」は、生産性三原則を創造的に応用し、AIなどの技術革新をディーセント・ワークに結び付け、成果の公正な配分を実現する。そして、その職場の生産性向上を、地域の知的インフラ整備や他産業とのシナジー効果につなげる。現状では、AI導入が労働を劣化させるような方向で進んでいるが、あくまで一人ひとりのキャリア権を充実させるような「労働移動」を可能にすることが重要だ。
その上で、「まもる・つながる・生み出す」の相互関係に目を向け、運動として具体化してほしい。それこそが日本の未来を変えるカギになる。
まず、「まもって生み出し、生み出してまもる」。セーフティネットがあってこそ、創造的な仕事ができ、ダイバーシティが守られてこそ、力を発揮できる。他方で生み出すことによって守るために必要な財政基盤を確保することが重要だ。次に「つながりをまもり、つながってまもる」。つながることで雇用を守るのは労働組合の原点だが、脆弱になっている家族や地域のつながりを守ることにも目を向けてほしい。最後に「つないで生み出し、生み出してつなぐ」。職場のつながりを強固なものにして生産性を上げていくだけでなく、職場・企業を超えて、地域の産業連携や知的基盤の共有が進むことにより生み出す力が高まっていく。つながりをつくる一番のきっかけは、職場の仕事であれ地域での活躍であれ、労働組合の生み出す活動だ。
「まもり・つながり・生み出す」こと、その相互関係をどう具体化していくか。労働組合の創造的な知恵を期待する。
提言2-長寿化と社会保障の課題
短期的判断の流れに抗い長期的判断による将来ビジョンを

駒村康平(こまむら・こうへい)
慶應義塾大学経済学部教授、ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター長
1995年慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。連合「人口減少・超少子高齢社会ビジョン」検討委員会有識者アドバイザー。著書に『最低所得保障』(岩波書店)、『日本の年金』(岩波書店)など。
2040年の日本を展望しながら、社会保障の課題を提起したい。2040年は、団塊ジュニア世代のリタイアが始まり、支え手の構造が大きく変化する時期だ。社会全体でみれば高齢化だが、個人からみれば「人生100年時代」と言われる長寿化が進む。現在、40歳を超えた団塊ジュニア世代は、非正規雇用比率も未婚率も高く、資産形成が遅れている。足元では、「親の介護」による介護離職問題も抱えている。団塊世代のように高度成長を享受できた世代が高齢期を迎えるのとは、質的に大きく異なる問題が生じてくるだろう。
この2040年を展望した時、社会保障財源をどう確保し、何を重点に制度改革を進めるのかという議論は避けて通れない。長寿化との関係で何歳まで働く必要が出てくるのか、急激な人口減少や人口構造の変化によって、特に地方はどういう影響を受けるのかも考えなければいけない。社会保障給付費は、現在の120兆円から、2040年には190兆円近くまで増えると見込まれる。介護・医療分野でより多くの労働者が必要であり、その人材確保の財源も必要だ。
長寿化に対応して公的年金をどう維持するのか。40年間保険料を払って30年給付を受け取るとすると、よほど保険料を上げるか、給付額を下げるか、あるいは支給開始年齢を大幅に遅らせるしかない。現行では、保険料は固定、支給開始年齢も上げずに、マクロ経済スライドを使って30年かけて基礎年金の給付水準を30%ほど切り下げていくとしている。この制度のもとで、団塊ジュニア世代は高齢期を迎えていく。個人の備えが必要になるが、貯蓄率はむしろ停滞している。
少子化も深刻だ。1975年の推計では、出生率2%前提に、日本社会は長期的に年間200万人の出生が見込まれていたが、この30年ほどで出生数は半減し100万人を下回った。この状況が続くと、これからの30年で出生数は50万人まで下がる。出生率が多少改善しても、全体の人口減少の趨勢を反転上昇させる力はなく、もはや手遅れの状態だ。
死亡者数は、現在の年間130万人から2040年頃には170万人となり、年間100万人ずつ人口が減少していく。すでに病院施設は増やさない方針なので、この170万人のうち数十万人は在宅で看取ることになるが、日本の家族にその力があるのか、介護離職の増加につながるのではないかと心配される。これは未来の話ではなく、すでに団塊ジュニア世代が直面しつつあるリスクだ。
もう一つ気になる指標は、働き盛りの男性の労働力率がここ20年以上にわたって継続して低下していることだ。さまざまな事情で労働意欲を失った人がじわじわと増えて、かなりの数になっている。これは他の先進国でも見られる現象だが、放置すれば生活保護の問題にもつながる。この人たちが、働くことを通じて社会に参加していくための支援も重要な課題だ。
私は、現在、脳神経科学と経済学をミックスした「金融老年学」の研究に携わっている。人間の意思決定は、情動的に素早く判断するシステム1と、長期的支援でじっくり判断するシステム2という二重構造でなされている。前者は大脳辺縁系、後者は前頭前野でコントロールされているが、前頭前野は加齢やストレスの影響を受けやすい。社会保障や教育など、長期的に判断すべき政策の重要性が増しているのに、政治家も行政も企業も短期の情動的判断に流れ、社会が不安定化している。
そういう中で、何より労働組合に期待されるのは、長期的判断ができる存在であることだ。人生100年時代、これまで通りの社会保障制度は維持できない。何を重点化させていくのか、その優先順位を決め、自助努力の範囲を見直し、高齢期の雇用環境を整備していくことが必要だ。労働組合には、短期的判断に流れる社会に抗い、長期的判断に基づくビジョンを提起し、その実現のために行動してほしい。
提言3-労働組合の役割と生産性向上
将来に希望が持てる「生産性向上」のあり方を

戎野淑子(えびすの・すみこ)
立正大学経済学部教授
慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。慶應義塾大学産業研究所臨時研究員などを経て、現職。連合「人口減少・超少子高齢社会ビジョン」検討委員会有識者アドバイザー。著書に『労使関係と職場の課題―雇用不安の解決に向けた労使の視点』(日本生産性本部)、『2025年の日本―破綻か復活か』(共著、勁草書房)など。
足元の雇用状況は良好で、特に新卒は売り手市場である。ところが、新入社員の意識調査(日本生産性本部、2018年)では、「いずれリストラにあうと思う」との回答が38・4%にのぼる。景気拡大が続き、雇用が改善する中で、将来に不安を抱いている若者がこれほど多いことは深刻な問題だ。このような不安を解消するためにも、連合が新ビジョンにおいて、将来に向けどこに向かって歩むべきかを示すことは重要である。
連合は結成30周年を迎えるが、まさにこの30年間で労使関係は大きく変化した。日本の労使は、戦後の紛争を克服し、生産性三原則に基づく日本的労使関係を形成し、高度経済成長を担った。その最大のポイントは、生産性向上と雇用維持を両立させることで、企業の発展が、労働者の生活向上さらには日本経済の発展につながるという好循環を生み出したことだ。
ところが1990年代半ば以降、グローバル化を背景に、生産性向上に伴い雇用を削減せざるを得ない企業や、生産性を上げるために賃金の安い海外で生産したり、非正規雇用にシフトする企業が出てきた。その結果、内需は冷え込み、人材が育たなくなっていく。ここにおいて、企業の業績が良くなっても、必ずしも人々の生活は豊かにならないし、日本経済の発展につながらないのではないかという疑念が生じることとなる。そして、それが先の意識調査に示された新入社員の将来不安につながっている。
では、こうした疎隔化した労使関係の下で、職場では何が起きているのか。人手不足、とりわけ若年層が不足し、中堅層がその分の仕事も背負い多忙となっている。そのため、目の前の生産性を上げることが優先される中、人材育成が後回しになっている。今、製造現場では、ラインに不具合が起きると、あっという間にベテランが直してしまう。本当は、その原因や修理方法について若手に教えたいが、そのわずかな時間さえ許されないこともあるという。
しかし、人材育成が希薄になることは、将来の生産性を低下させることになる。来たる人生100年時代には、長期的視点による技術革新や産業構造の変化に対応した人材育成や雇用の創出がより重要になる。まず、この短期的生産性と長期的生産性の調整が必要だ。
また、生産性は産業ごとに性質が違う。ある介護事業所は「効率的に仕事はするが、生産性は上げない」という。その真意は「介護の仕事は労働集約的で、生産性を上げようと思えば、寝たきりの人を受け入れたほうがいい。徘徊などがある人はその何倍も手がかかるからだ。しかし、社会が介護業界に求めているものは違う。手がかかる要介護者を受け入れることで、家族が心おきなく働くことができれば、他の産業を支える縁の下の力持ちになれる」からだという。こうした産業特性を踏まえた生産性を考えていくことも課題だ。さまざまな産業が支え合って人々の生活や社会が成り立っている。社会全体としての生産性のあり方にも目を配っていく必要がある。
「生産性向上」は、労使関係のあり方を決定づける要だ。そして、職場、産業、社会という、それぞれのレベルで生産性を考えることができるのは、企業別組合、産業別組合、地方組織、ナショナルセンターをもつ労働組合しかない。労使のベクトルが必ずしも一致していない今だからこそ、職場、産業、社会全体に目が行き届き、一貫した歩みを進めていける唯一無二の組織、労働組合の役割は大きい。それぞれの得意とする分野で、将来に希望が持てる「生産性向上」のあり方を見いだしてほしい。
では、具体的に何から始めるべきか。まず、シニア層や非正規雇用、フリーランスなど、同じ職場で働いているのに距離がある人たちを労働組合の仲間にしていく。その課題やニーズに向き合い、ともに解決に取り組むことが、社会全体の、そして長期的な視点での生産性を高めていく一歩になると考える。
※この記事は、連合が企画・編集をしている「月刊連合1・2月合併号」をWEB用に再編集したものです。
