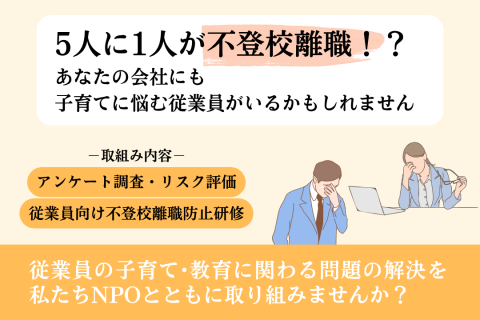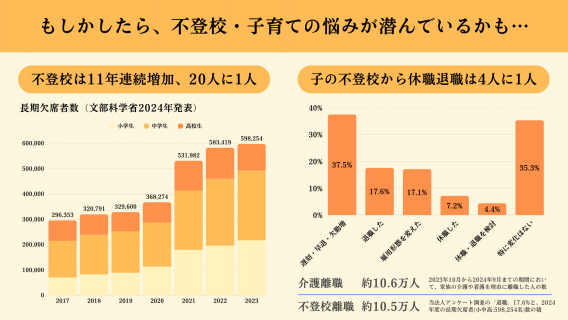531PV
531PV いいね|111
いいね|111
小・中学校または小・中学校教職員に対して、退職教職員が経験を活かしサポートを行うことにより、学校現場の多忙化を少しでも解消し、児童・生徒の学びの環境をより良くしたい。
社会や政治からの要請に伴い、学校の役割は膨らみ、教員の仕事量は増える一方です。加えて教員の人手不足は慢性化している現状です。そこで、退職教職員が学校現場に出向き、以下の2つのサポートを実施しながら、教員を支援し、子どもたちの教育環境を充実させる取組を行っています。いずれも1日4時間まで、1校当たり月に5日間までの短期のサポートとしています。
「学校サポート」では、主に小学校の授業等において特別な支援が必要な子どもや学級の支援、担任や養護教諭の不在で人手が足りないときの支援をしています。具体的には気持ちが不安定になった子どもへの声掛けや自習の見守り、学習が遅れがちな子どもへの個別の対応、保健室での見守り等です。最近は、特別支援学校や中学校からの依頼も増えています。
「ねこの手サポート」では、幼小中学校やその他教育現場の側面的・事務的な支援をしています。具体的には行事のピアノ伴奏、会合中の子どもの保育、作文の校正やデータ入力等です。
刻々と変わる学校現場で、臨機応変に多様な児童に対応することは難しいです。しかし、退職教職員ならば今まで培ってきた教育現場での経験から、高い専門性、指導性を生かして個に応じたサポートを行うことは可能です。
他にも、サポートの質を保つために、研修を行っています。提供会員連絡会を2か月に一度のサイクルで開催し、お互いのサポートの状況を情報交換し、悩みや課題を共有し、解決できることを話し合っています。学校の現状に合わせてタブレット研修や養護教諭を講師に招いて、保健室での対応の仕方の研修なども行いました。会員どうしの親睦や交流も大切にしています。
また、当団体では、学校や教育関係団体からの依頼を一斉送信し、対応できる人がサポートに入るシステムをとっており、「できるときにできる人が」というモットーでサポート事業を行っています。これは退職教職員にとっても、退職後の選択肢として無理のないものであること、自分のスキルや持ち味が活かされることで充実感を得られる活動であること等のメリットがあり、会員である退職教職員からも好評を得ています。
サポートに行った学校からは、以下のような感謝の言葉をいただいています。
「サポーターに優しく話を聞いてもらい、児童はとても満足そうな表情を浮かべていました。」
「児童の困り感に気づいて適切にサポートしてもらったおかげで学級全体に落ち着きが出てきたように思います。」
「いてくれるだけで、担任は普段よりも余裕をもって子どもと接することができました。Smileういんずが来た日は安心が来たと思います。」
「保健室が開いているのは本当に助かります!」
「トイレに行く時間ができて、ほっとしました。」
教師は、担任ならば1人で何もかもやらなければならないという想いを抱えています。そんな中でサポートを受けるばかりでなく、退職教職員に相談できることはたいへん心強く、励ましが力になると喜ばれています。
児童からは以下のような声をかけられています。
「今度いつ来るの?」
「明日も来てね。」
「給食も一緒に食べて行って。」
「いつもいてくれたら、勉強が分かるようになる気がする。」
学校現場は今も慢性的な人手不足に悩まされています。そのため、教職員が一人でも休むとたちまち困難な状況に陥ってしまいます。そんな状況が頻発し、すぐに来てほしいという切迫した依頼が増えています。私たちがサポートに入ることで、「休まなければならなくて恐縮している職員も安心して休めます。」という声を聞くと、学校の困り感に少しは対応できているのかなとやりがいを感じています。
支援者に徹して多様な子どもに対応することは簡単ではありませんし、介護等を抱えるサポーターも多い中、すべての要請に対応できる人を探すのは容易ではありません。しかし、学校の隙間を埋め、子どもたちや教職員を支える存在であり続けたいと願っています。より多くの学校支援者と手を結び、活動を続けていきたいです。