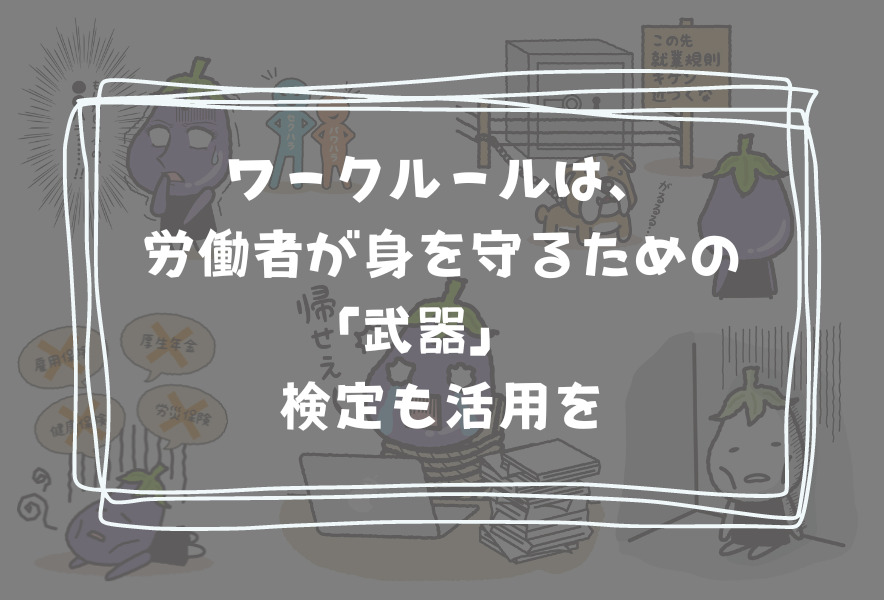「お店の皿を割ったら賠償」「試験よりもシフトを優先」。初めてアルバイトを始めた高校・大学生は、こうした勤め先の「マイルール」を正しいと思い、鵜呑みにしてしまいがちだ。学生たちと雇い入れる職場の双方が、労働者の権利や法律に関する正しい「ワークルール」を知らないために、こうした事態が起きている。
ワークルールは、労働者が権利侵害などから身を守るための、強力な「武器」の一つ。本当は長い職業人生の入り口に立った若者にこそ、ぜひとも身につけてほしい知識なのだ。
「店長がかわいそう」最低賃金を下回る時給で働く学生

「学生たちは、最初にアルバイトした職場で教えられたことを『ルール』と思い込んでしまう。『深夜もシフトに入れ』と言われてもルールだと思って素直に応じ、翌朝は寝坊して授業に出られない。その繰り返しで留年・退学してしまう悪循環が起きています」
駒澤大学経営学部教授の鹿嶋秀晃氏はこう嘆く。同大学では毎年、成績不振の学生と個別に面談する修学相談会を組織的に実施している。その際、留年の理由などについてアンケートを取っており、アルバイトを理由に挙げる学生は少なくないという。
学生バイトの職場では、無理にシフトを入れられるだけでなく、最低賃金を下回る時給や雇用契約外の深夜・長時間労働なども横行している。ただ多くの学生は、ワークルールについて何も教わってこないため「働くってこんなものなんだろう」と考え、職場の「おかしさ」にすら気づけない。
またルール違反を知りながら、店側の事情を忖度し従ってしまう「優しい学生」も増えていると、鹿嶋氏は感じている。
「私のゼミで最低賃金について十分学んでいる学生ですら『店長が困っていてかわいそう』と最低賃金を下回る時給で働いてしまう。学生にとって勤め先は、収入を得るだけでない大事な『居場所』であることも多く、自分を犠牲にして尽くしてしまうのです」
「Z世代」に属する学生は、20歳になるまで飲酒しないなど「ルール」に従順な傾向が強い。一方、ルールを疑って批判したり、自分の権利を主張したりすることには消極的だ。
「私が政府の労働政策やゼミで教材に使っている本の内容を批判すると、多くの学生が『先生、そんなこと言っていいんですか?』と驚きます。そして初めて『批判していいんだ』と気づき、堰を切ったように話し始めるのです」

高校、大学、社会人5年目…学び続けることが大事
働き手の従順さは、時として働き手自身に「あだ」となって返ってくる。会社側はたとえ労働環境が劣悪であっても、労働者が何も言わなければ「現状に満足している」と認識し、職場を改善しようとはしない。今いる労働者自身が「おかしい」と声を上げないままでいると、後に続く後輩たちも、同じ苦しみを経験することになる。
「学生には『会社に尽くして過労死しても、会社側は報いるどころか必死で責任を逃れようとする。労働者は正しいルールを主張し身を守ることが大事だ』と伝えています。しかし学生は、ゼミで学んだことより毎日のように会う店長の言葉に動かされてしまうようです」
また鹿嶋氏は、各大学のキャリア教育が「仕事を通じてやりたいことを実現する」「スキルや能力を高め有用な人材になる」といったテーマに偏り、ワークルールに関する情報が抜け落ちてしまっていることも問題だと指摘する。
「単に夢を追いかけることだけでなく、正社員になれなかった時や失職した時、ブラック企業に当たった時にどう対応するか、そして社会にどのようなセーフティネットがあるかなどを、きちんと教えるべきです」
このため鹿嶋ゼミでは、連合と協働して、学生たちが学びの一環として「アルバイトを始める際に知っておくべきこと」などを伝える画像を作り、SNSで発信している。
ただゼミの卒業生すら、社会に出て4~5年経つと「ゼミではこう教わったけど…」と言いつつ、残業は当たり前といった企業風土に染まっていくという。だからこそ鹿嶋氏は「社会に出てからも数年おきに、ワークルールを復習する機会を持ってほしい」と要望する。
「まず学生がアルバイトを始める前に正しい知識を刷り込み、社会人になってからも、自分の職場が法律に適っているかどうかを定期的に振り返る。ワークルールは、人生を通じて学び続けるべき分野だと思います」
権利意識の低下と比例し、労働者の待遇も劣化
.jpg)
NHK放送文化研究所の「日本人の意識調査」によると、「労働組合をつくる」ことを国民の権利だと知る人の割合は、1973年の39.3%から2018年には17.5%と、半分以下に減った。また「仮に職場で労働条件に不満がある場合どうするか」という質問について、「労働組合をつくって条件が良くなるよう活動する」を選んだ人の割合は、31.5%から15.6%へとほぼ半減。一方で「しばらく見守る」を選んだ人は37.2%から50.6%へ上昇した。
また国税庁の民間給与実態統計調査によると、給与所得者の1年間の平均給与額は、1998年の464万円から2021年には443万円となり、この20年ほど横ばいから低下傾向で推移している。近年は非正規の働き手が増えたことで、年収200万円以下の人の割合も高まった。元連合副事務局長で、日本ワークルール検定協会副会長を務める高橋均氏は「団結して待遇改善を訴えるという労働者の権利意識が低下するのと比例して、賃金や待遇も劣化している」と訴える。
事態に追い打ちをかけたのがコロナ禍だ。組合はオルグ(労働組合づくり)などの活動に制限を受けて組合員とのつながりを思うように築けず、アフターコロナでも企業にリモートワークが普及したことで、かつてのような「密」なつながりを作りづらくなった。このため働き手が組合活動を通じて、ワークルールに触れる機会も減りつつある。
さらにギグエコノミー(インターネット等を通じて単発の仕事を受注する働き方)の台頭で、フリーランスや個人事業主など組織に所属しない働き手も増えた。彼ら彼女らは、発注者による賃金未払いやハラスメントがあっても、仕事を失うことを恐れて声を上げづらい。また一人ひとりが孤立しがちで、トラブルがあっても誰かに相談したり、同じ問題を抱える人同士で協力して解決をめざしたりすることが難しい。
「現代社会は人間関係の分断が進み、働き手が集まって権利を主張しづらくなっています」と、高橋氏。その分、働き手一人ひとりがワークルールを知り、自衛する必要性も高まったと言える。
ワークルール検定 現場の管理職・店長に受けてほしい
同協会は、労働法などの知識習得を目的とした「ワークルール検定」を、年2回実施している。2013年の開始以来、22年秋までに約1万8000人が受検した。
受検者の多くは労働組合関係者だが、最近はハローワークや労働局にあるチラシやWeb広告を見て、一般の会社員や学生らが受検するケースも増え始めたという。
またスポーツ用品販売のムラサキスポーツは、検定の初級合格を管理職登用の条件にしている。高橋氏は「企業から店長や管理職に向けて、受検を促す動きがもっと広がってほしい。現場のマネジャーが知識を得ることで、職場の待遇改善も加速するはずです」と期待する。

また高橋氏も鹿嶋氏同様、学生に教育段階からワークルールを教える必要がある、と強く主張する。しかし現在の公教育では、高校の教科書ですら「労働三法」にごく簡単に触れるだけで、内容を学ぶ機会はほとんどない。公務員である教員は、労働法の枠外にいるため「ワークルールを教えることの重要性を、今一つ『自分ごと』として実感しきれない面もあるのかもしれません」と、高橋氏は推測する。
「しかし今、高校・大学でアルバイトを始める若者たちは、何も学んでこないまま職場に放り出され、権利がはく奪されている自覚すら持てずにいます。ぜひとも高校生のうちに、労働者の持つ基本的な権利について伝えておくべきです」
(執筆:有馬知子)
※ ※ ※
「ワークルールを知らないまま職場に放り出された」学生は、どんな苦労をしているのだろうか。7月20日公開の記事では、現役大学生の「バイトのリアル」や、労働者が身を守るための心得を紹介する。