2025春季生活闘争では、大手組合の平均賃上げ率が昨年を上回る5.46%(3月14日速報時点)となった。中小組合も33年ぶりに5%台に乗ったものの、価格転嫁が道半ばなために厳しい交渉を迫られる組合も多い見通しだ。自動車などに使われる「特殊ばね」のメーカー、村田発條労働組合(栃木県宇都宮市)の大杉純一執行委員長に現状を聞いた。
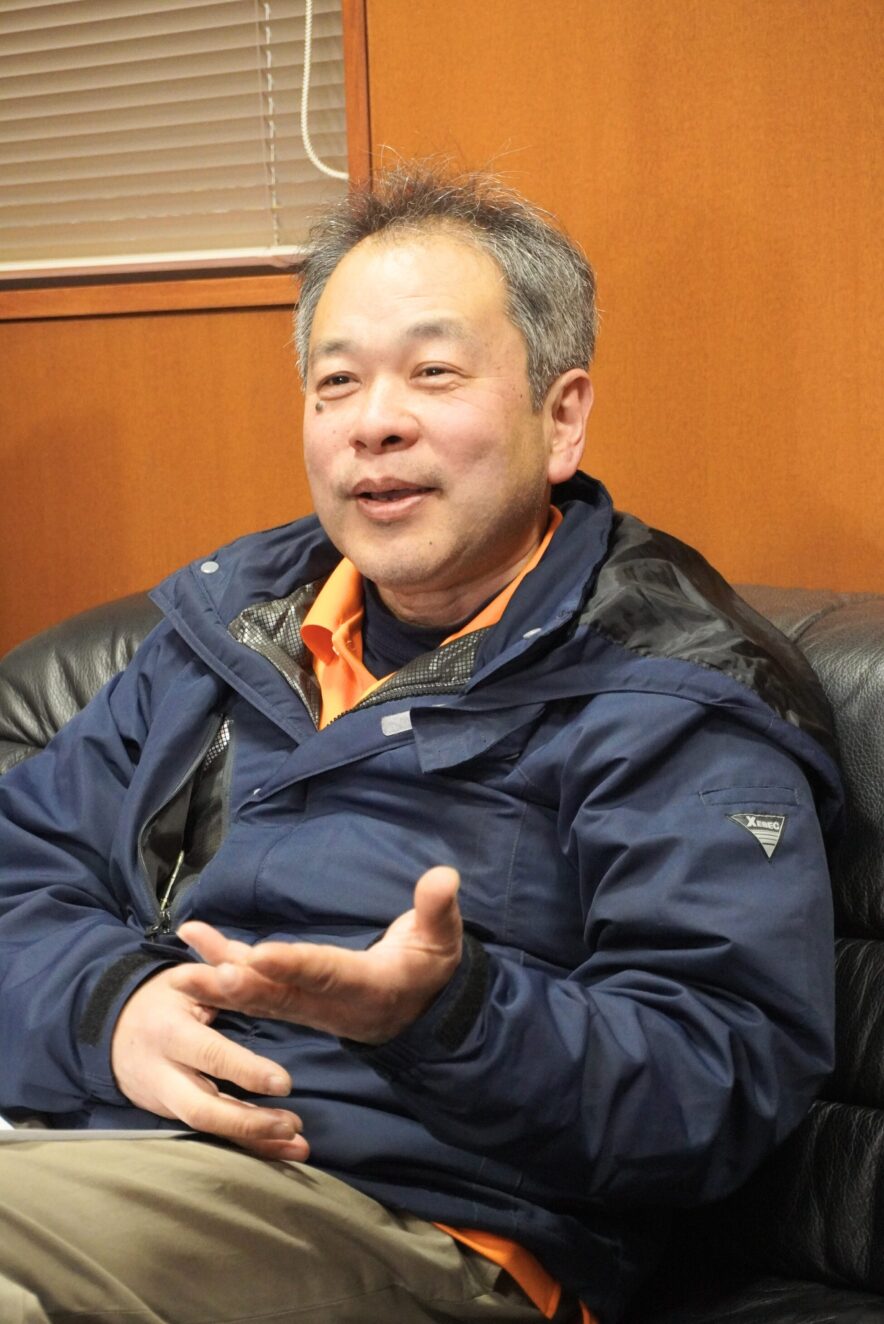
価格転嫁、実現は6割程度 中間メーカーは板挟み
村田発條労働組合は、産業別労働組合JAMに属し、従業員約350人のうち約200人が加入している。2025年春の賃金交渉では、ベア1万5000円、一時金5.1カ月を要求した。 大杉さんは「昨今の物価上昇で、組合員の生活は本当に苦しい。たとえ満額回答を得ても物価高には追いつかず、経営側にはとにかく少しでも賃金を上げてもらわなければ困ります」と訴えた。
ただ同組合は前年、ベア1万2000円、一時金5.0カ月を要求し、回答はそれぞれ8000円、4.1カ月と要求額を下回った。さらに2024年度は、大手自動車メーカーが不正問題や労災事故で生産ラインを一時停止した影響によって部品の受注数が減少し、売り上げ、利益ともに前年を下回ったという。
「業績が苦戦している上、価格転嫁も十分には進んでいない状況を考えると、交渉は非常に厳しいと予想しています」
価格転嫁の進捗は、概ね会社目標の約6割程度に留まり「100%転嫁を認める取引先と20~40%に留まる取引先があり、温度差も大きい」という。一次発注者となる大手自動車メーカーについては、投資家からステークホルダーの尊重やサステナビリティ経営が求められていることもあり、ほぼ100%の価格転嫁が行われた。しかし「2次下請けからは『1次メーカーが認めてくれたら認めます』と言われるケースもあります。下請けになるほど利幅が薄くなり、転嫁を避けようとするのでしょう」。
燃料費や素材費、労務費の値上がりについて、膨大な証拠資料の提出を求められた上、上昇分を「一時金」として支払う企業も見られた。この場合製品価格は据え置かれているため、今年度分の価格転嫁には再度の交渉が必要となる。
一方で村田発條が仕事を発注している下請け企業は、多くが個人経営や従業員の少ない小企業だ。「製品単価を引き上げなければ、本当に会社が存続できなくなってしまうので、応じざるを得ないのです」
発注者にはなかなか転嫁に応じてもらえないが、下請けには転嫁せざるを得ないという「板挟み」の中で、賃上げの原資を確保しづらくなっているのが現状だ。
離職増加で組合員20人弱減 組合に「借金」する人も
大手企業のトップは価格転嫁の必要性を理解しているものの、購買や営業担当者のレベルでは未だに「調達価格を抑える」ことが評価される傾向が強いことも、転嫁のネックになっている。
「経営トップと現場担当者の意識の乖離を改めなければ、下請けの賃上げ環境は厳しいままだと思います」
賃上げが進まないことは、離職者の増加や採用難に直結する。また近年は賃上げが行われても、採用強化のため若手の賃金を集中的に引き上げ、ミドルシニアへの配分が抑制されがちなことも、多くの職場で問題視されている。
村田発條も例外ではなく「現場の主力を担うミドル層の離職が増え、組合員も過去1年ほどで20人弱減りました」。
さらに欠員を補充するため求人を出しても、思うように人が集まらない状況も続いている。「求人サイトを見れば、すぐに他社の給与が分かります。工場勤務のキツさなど製造業の労働環境が敬遠されているというより、賃金水準が見劣りするため人が集まらないという要因の方が大きいと感じます」
こうした中で製造ラインの人手不足感は強まり、残業や休日出勤も増えているという。
「従来は1人1台の機械を担当していたのが、2台、3台をカバーせざるを得なくなりました。このため品質や歩留まりが低下する懸念も出ており、そうなれば業績への打撃も避けられません」

同組合には、生活費などが不足した組合員に最大15万円をほぼ無利子で貸し付ける「緊急貸付」の制度がある。昨今の物価高などで、組合員20人ほどがこの貸付を利用しているという。
「家計に余裕がなくなり車検費用を出すのが難しい、生活苦のためといった理由が多い。中には完済前に『どうしても苦しいので、15万円の枠内でもう一度貸してほしい』と申し込む人もいます」 さらに任意加入の「ねんきん共済」などを解約し、当座の家計に充てる人もいるという。「このままでは組合員の間で、老後の生活が苦しくなる人と豊かな人の格差が拡大しかねません」と、大杉さんは懸念を口にした。
厳しい経営、「トランプリスク」も浮上 大手も中小の役割を理解して
「経営側も人手不足を解消するためには、賃金水準を引き上げる必要があることは認識しています」と、大杉さん。しかし経営環境に不透明な要因が多いために、賃上げに踏み切ることができないのだという。
2025年に発足した米トランプ政権は、自動車関連製品に高率の関税を課す方針を打ち出した。同社は日米両国とメキシコに工場を持っているが、近年は米国の賃金上昇などから米国での生産比率を下げて日本やメキシコで部品を作り、米国へ納品するビジネスに軸足を置いてきた。日本とメキシコに関税が課されれば、こうしたスキームも見直しを迫られることになる。
「会社としても、自動車産業以外のビジネスを増やすことや、下請け脱却を目的とした新規事業などさまざまなことに取り組んではいます。しかしこうした施策はすぐに成果は出ないため、直近の賃上げにはやや手詰まり感も見えています」
賃上げ原資を得るため、労働組合には何ができるだろうか。大杉さんは「価格転嫁を進めるよう、経営側に働き掛けることに尽きると思います」と断言した。
「このままでは離職が増えて人も集まらず、会社が先細りになって存続すら危うくなりかねない。経営側は現状への危機感と、社員への誠意を持って賃上げを行う必要があり、そのためには製品単価を上げて、賃金原資を確保することが絶対に不可欠です」
大手自動車メーカーの中には2024年度、売上高、営業利益ともに過去最高を更新する企業も見られる。さらに2025闘争でも、トヨタ自動車がベースアップ(ベア)、一時金ともに満額を回答するなど、前年に引き続き高水準の回答が相次いでいる。 「過去最高の利益とそこで働く人の賃上げは、私たち下請けの製品価格を抑えることによって実現している面もあります。大手メーカーが製品を作るためには、私たちの納める部品も欠かせないことを理解し、転嫁に応じてほしい」
連合、産別の働きかけも重要 価格転嫁進めて格差拡大に歯止めを
大杉さんは、個社の労使の力で発注企業の認識を変えることには限界があり、連合やJAMが経営者団体に働き掛けたり、組織内議員が国会で対処を求めたりすることが重要だと考えている。
実際、2023年には価格転嫁に関するガイドラインが出されたほか、2024年3月には公正取引委員会が、下請けの値上げ要請に対して理由を示さず価格を据え置いた企業は、告発などに基づき社名を公表するとした。
「告発したことが発注企業に知られて転注(下請け事業者を変えること)されるリスクがあるので、社名公表のハードルは高いと思いますが、それでも連合や産別の働き掛けによって、国の取り組みが進み始めたことは確かです」
経営側との交渉でも、同じ地域の同業他社の賃金や労働条件を比較したデータの提供を受けるなど、JAMからの情報が役立っているという。
連合によると、300 人未満の中小組合の平均賃上げ率は5.09%(3月14日時点)と、33 年ぶりに5%を上回った。企業別組合と連合、産別それぞれの取り組みが、一定の成果を生み出したとも言えるが、それでも大手には届かず、連合が目標とする6%にも達していない。大杉さんは「中小が大手を超える賃上げ率を達成するのは、極めて難しい。100%価格転嫁が実施されても、大手には届かないのではないか」と厳しい見方を示した。
「しかし価格転嫁が行われなければ、これから中小企業の経営は成り立たなくなります。そして転嫁が実現すれば、確実に格差拡大を食い止める力になるはずです」

(執筆:有馬知子)


