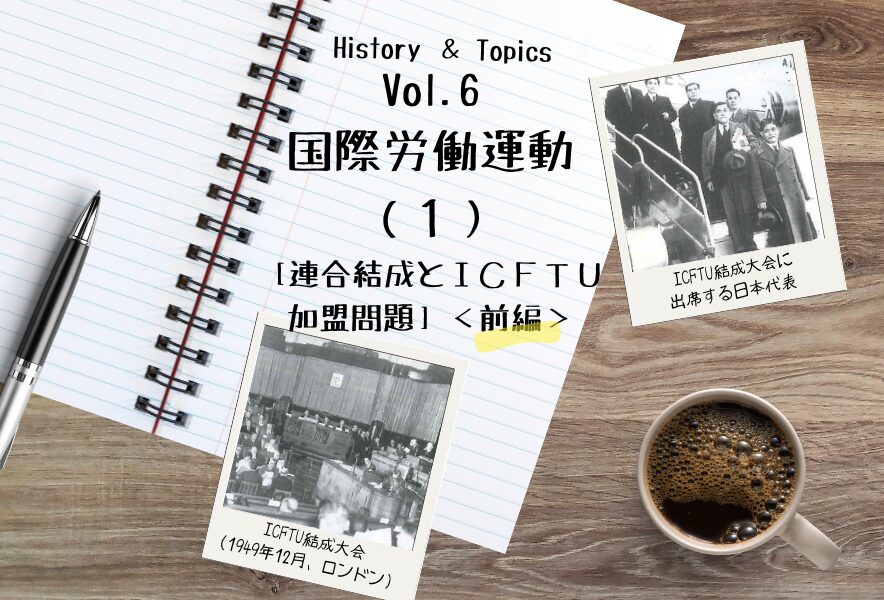労働組合運動の強みは、企業を超え、産業を超えて、働く人たちがつながりあえることだと言われるが、実は国境を超えてつながろうという「国際連帯活動」も長い歴史を持っている。しかも、経済のグローバル化が進む中で、その重要性はますます高まっている。ということで、RENGO ONLINE「労働組合の歴史」新シリーズは、「国際労働運動」をテーマに連載スタート。
日本の労働組合は、国際労働運動をどう捉え、どう関わっていったのか。 初回は、連合国際局で長く実務にあたった生澤千裕日本ILO協議会理事の全面協力を得て、「連合結成とICFTU(国際自由労連)加盟問題」の経緯を2回に分けて解きほぐしていこう。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)
日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー
1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバー・サミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。
2024年11月、連合は結成35年を迎えた。その統一にあたって、重要な条件の1つに掲げられたのが、「ICFTU(国際自由労連)への一括加盟」だった。
ICFTU(International Confederation of Free Trade Unions)とは、1949年11月に結成され、2006年にWCL(国際労連)と統合してITUC(国際労働組合総連合)となった国際労働組合組織。現在、世界160カ国以上のナショナルセンターが加盟し、組合員数は約1億9000万人。会長は連合(UAゼンセン)出身の郷野晶子氏(ILO労働側理事)が務めている。
しかしながら、いったいなぜ、日本のナショナルセンターの統一において国際労働運動へのスタンスが問われることになったのだろうか。
労働組合の誕生と国際労働運動の源流
それは、ICFTU結成の経緯にも深く関わっているようだ。「世界史」の領域になるが、少しだけ「国際労働運動の源流」を確認しておこう。
18 世紀後期、イギリスで産業革命が起きて、蒸気機関を原動力とする機械制大工業が始まった。資本家が資金を出して生産設備をつくり、労働者を集めて生産を行い、利潤を上げる。労働者は労働の対価として賃金の支払いを受ける。そんな「資本主義」の生産方式が確立されていったが、働く人たちは、低賃金・長時間労働など劣悪な労働条件・労働環境を強いられる実態があった。
この問題を解決するために考え出されたのが、労働組合だ。働く人は一人では弱い立場にあるけれど、団結して集団で要求し交渉すれば、賃金引き上げや労働条件・労働環境の改善を実現できる。
当初、労働組合は警戒され、多くの国で結成が禁止されたが、深刻化する社会問題を解決するために必要な存在であると広く認知されていく。
例えば産業革命の先進国イギリスでは、1824年に団結禁止法を廃止して労働者団結法が制定され、労働組合の結成が法的に認められた。1833年には児童労働禁止や労働時間などが規定された世界初の労働者保護法「一般工場法」が制定され、1871年には労働組合法において団結権・団体交渉権・ストライキ権(労働三権)が確立された。
労働組合活動が合法化されると、各国で職業別や産業別の労働組合を束ねる全国組織(ナショナルセンター)が発足し、さらに「働く仲間に国境はない」と国際的な連帯活動も活発に行われていく。
この国際労働運動にはいくつかの流れがあった。
1つは「労働者階級の解放」を掲げ、共産主義国家の実現をめざす流れ。
1848年、社会思想家のカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスは『共産党宣言』を発表して「万国の労働者、団結せよ!」と呼びかけた。そして、1864年に国際組織「第1インターナショナル」を結成するが、内部対立が深刻化し、1872年に解散。その失敗を教訓に、1889年に第2インターナショナルが設立されるが、第1次世界大戦へのスタンスをめぐって対立が生まれ、1919年に解散。同年、ロシア革命を実現したソ連共産党の主導で、国際共産主義運動を掲げる第3インターナショナル(コミンテルン)が創設された。
もう1つは「自由で民主的な労働運動」をめざす流れだ。1913年に国際労働組合連盟(IFTU)が結成されるが、翌年に勃発した第1次世界大戦によって活動停止に追い込まれた。IFTUは、終戦後の1919年、オランダのアムステルダムで改めて設立総会を開催し、労働組合の国際戦線の統一、各国労働運動に対する協力援助、国際労働立法の促進などの基本原則を採択。アムステルダム・インターナショナルとも呼ばれ、同年に設立された国際労働機関(ILO)の設立・運営にも大きく貢献していく。
また、1920年にはIFCTU(国際キリスト教労連)が結成されている。IFCTUは、2つの潮流とは距離をおいて独自の道を歩んでいたが、1968年に「信仰、人生観、民族、性別のいかんを問わず、世界のすべての労働者に呼びかける」とする新宣言を採択して、名称を国際労連(WCL)に改称。2006年にICFTUと統合してITUCを結成した。
「反ファシズムの旗」の下に合流した世界労連(WFTU)
この前史を踏まえた上で、ICFTU設立の経緯をみていこう。
第2次世界大戦末期の1945年2月、ロンドンで第1回世界労働組合会議が開催された。参加したのは、「連合国(戦勝国)」に属するイギリス、アメリカ、フランス、ソ連、中国を含む40余カ国のナショナルセンターの代表者。同会議は、新しい国際組織が必要だという認識で一致し、その準備のための組織委員会設置を決議した。
これを受けて、1945年9月、フランスのパリで第2回世界労働組合会議が開催され、世界労連(WFTU)の結成が決定された。
ところがWFTUは、早々に深刻な対立に見舞われる。生澤さんは、その構図をこう解説する。
20世紀前半には、労働組合主義のアムステルダム・インターナショナルと、国際共産主義のプロフィンテルンという、国際労働運動の2つの潮流が存在していましたが、この主義・主張の異なる両者が、第2次世界大戦中に「反ファシズム」という旗印の下に合流し、終戦直後の1945年9月にWFTU(世界労連)を結成しました。
ところが、アメリカとソ連の関係は急激に悪化。WFTUにおいても、アメリカが作成した「マーシャルプラン」という欧州経済復興援助計画への対応をめぐって、西側の労働組合とソ連を中心とする東側の労働組合との意見が対立し、イギリスのTUC(労働組合会議)やアメリカのCIO(産業別組合会議)など西側陣営の主要労働組合が脱退。WFTUはその後、国際共産主義運動の前線組織としての性格を強めていきました。
そして、WFTUを脱退した組織と、もともと未加盟だったアメリカのAFL(アメリカ労働総同盟)などが一緒になって新たな国際労働組合組織の結成へと動く。そういう経緯で1949年11月に結成されたのが、ICFTU(国際自由労連)だったんです。

出所:ICFTU日本加盟組織連絡協議会<左・右写真ともに>

「パンと自由と平和」を掲げて
ICFTUは、結成大会において、「パンと自由と平和」を基本目標とする宣言を発し、下記の規約を採択した。
「国際自由労連は、民主主義の諸原則を熱烈に支持する組織として、人間の自由という大義を擁護し、すべての人々に対する機会均等の実現を推進し、世界のあらゆる所で人権・宗教・性別ないしは出自に基づくすべての形の差別待遇や従属状態の一掃に努め、またすべての形の全体主義や侵略に反対し、これと闘う。抑圧的政治体制のために労働者および人間としての権利を奪われているすべての働く人々に対し、国際自由労連は連帯と支持を誓約する」。
生澤さんは「注目してほしいのは、『すべての形の全体主義や侵略に反対する』というフレーズです。ICFTUは、ソ連を中心とする「自由とは言えない」国際共産主義運動に対し、明確に反対の旗を掲げて出発したのです」と解説する。
では、日本の労働組合は、こうした国際労働運動の動きにどう対応したのか。〈後編〉で詳しくお伝えする。