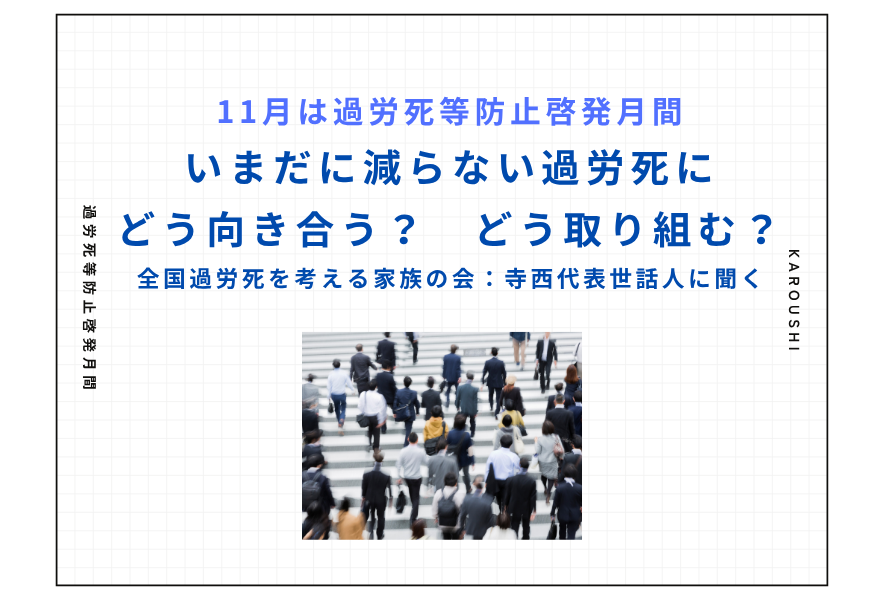毎年11月は過労死等防止啓発月間。「全国過労死を考える家族の会」代表世話人の寺西笑子さんに、過労死のない社会を実現するために必要な取り組みを聞いた。
「全国過労死を考える家族の会」ウェブサイト:https://karoshi-kazoku.net/

寺西 笑子(てらにし えみこ)
全国過労死を考える家族の会代表世話人
京都市在住
1996年2月 夫、過労自死
1997年 過労死家族の会活動に参加
2001年 京都下監督署にて労災認定
2005年 京都地裁にて勝訴
2006年 大阪高裁にて和解
2008年~現 在 全国過労死を考える家族の会代表世話人
2014年~2025年 過労死等防止対策推進全国センター共同代表
2014年~2024年 厚生労働省過労死等防止対策推進協議会委員
遺族が国を動かした 過労自死の認定基準制定
寺西さんは1996年2月、夫の彰さんを過労による自死で失った。長時間労働は明らかだったが、当時は仕事に起因する自殺を労災と認定するための基準がなく、行政や弁護士などから「労災申請をしても認定は難しいし、企業を訴えても勝てないだろう」と言われた。
「夫を亡くした上に泣き寝入りするしかないと言われて、奈落の底に突き落とされたような気分になりました」
最初の1年は動く気力すら湧かなかった。しかし、その後諦めきれずに過労死110番に相談すると、応対した弁護士に「自殺も仕事が原因なら、労災と認められるべきだ。認定基準を変えるため、一緒に頑張りませんか?」と言われた。この言葉に励まされて1999年、「ダメ元で」労災申請に踏み切った。
同じ年、厚生労働省が精神障害・自殺に係る業務上外の判断指針を制定した。指針の策定は、先行する過労自殺に関する司法判断がきっかけとなっている。息子を過労自死で失った遺族が、勤務先企業に損害賠償を求めた訴訟で、過重労働と自殺の因果関係が認められ、企業責任が認定されたのだ。
「原告側は認定基準がなくても諦めずに戦い、その結果国が動いて認定基準が出されました。ご遺族と弁護団にはとても感謝していますし、私も道を開くために活動していきたいと、気持ちが大きく変わった瞬間でした」
寺西さんは当時、2人の息子のことを考えて表立った活動を控えていた。しかし遺族の奮闘で指針が出されたことや、弁護士から「世論を味方につけて、労基署に『過労死は大きな社会問題だ』と認識してもらい、正しい判断を下すよう促す必要がある」と説得されたことで、積極的にメディアへの取材対応や署名活動などを行うようになった。その結果、2001年に労基署で労災認定が出され、その後起こした民事訴訟も企業責任が認定される形で和解が成立した。
若年化する過労自死 テレワーク中の過労死も
夫の死から30年が経とうとしている今も「事態の深刻さは変わっていない」と、寺西さんは話す。特に心配しているのが、若い世代の自死が増えていることだ。
「夫は49歳で他界しましたが、今は20代、30代の夫を失い、幼い子とともに残された妻や、娘や息子を亡くしたご両親からの相談が増えています」
近年は、月の時間外労働が単月で100時間超、2~6カ月平均で80時間超といういわゆる「過労死ライン」を超えていなくても、総合的判断で過労死と認定されるケースは増えた。一方で、業務時間外の研修や医師の学会準備などが『自己研鑽』『上司の命令に拠らない自主的な取り組み』などと判断され、労働時間に算入されない傾向も見られるという。
さらにコロナ禍以降、1人暮らしでテレワーク中に死亡するといったケースも出てきており、遺族側が勤務実態を把握しづらい面もある。近年は企業が労働者の「キャリア自律」を打ち出して「自発的な」学びやスキルアップを求めるようになり、さらにテレワークなどの働き方も定着しつつある。こうした中で、業務時間の線引きは今以上に難しくなる懸念もある。
「労災認定されない場合は裁判を通じた解決が必要ですが、訴訟を戦う気力のある人はごく一部です。特に自死遺族はそっとしておいてほしい、周囲に知られたくないという心理も働き、泣き寝入りしてしまう人もたくさんいます」
家族の会では若年層の自死の増加を受け、大学生、高校生への予防・啓発授業を行っている。遺族と弁護士ら専門家が全国の学校を訪問し、体験談を話した上で、過労死から身を守るための知識を伝えるのだ。
「過労死は、劣悪な条件が重なると誰にでも起こり得ますし、精神的に追い込まれると自分の働き方が異常だということにすら気付けなくなってしまう。働き始める前に正しい知識を身につけ、おかしいと思ったらすぐに、家族や専門機関に相談してほしいのです」

「あんな思いは誰にもさせたくない」が活動の原動力に
寺西さんを活動に向かわせるのは「もう誰も、私のようなつらい経験をしてほしくない」という思いだ。
寺西さんは彰さんが亡くなった後「様子がおかしいと気付いた時に何かしていたら、夫は死ななかったのではないか」と自分を責めた。一方、自死の場合はいくら長い時間働いていても労災認定が難しいと分かってからは「なぜ自死を選んだのだ」と、夫を責める気持ちにすらなったという。
労災が認定され、企業責任が認められることは遺族にとって「一つの救い」だが、亡くなった人は生き返ってはこない。
「何年経っても、遺族は生きているときに救えなかった自責の念が消えることはありません。私自身、孫が生まれるなど嬉しい出来事があるたびに『ここに夫がいたら』という気持ちになります。自死する人はもちろん、私のようなつらい思いをする遺族もこれ以上増えてほしくないのです」
「働きたい改革」は「人の命を大切にする社会」から逆行
寺西さんらの尽力の結果、2014年には過労死等防止対策推進法が施行され、働き方改革推進法などワークライフバランスを推進するための法律も整備されてきた。しかし首相に就任した高市氏は、条件付きながら労働時間の規制緩和を検討する姿勢を打ち出した。
過労死を防ぐには企業側、特に経営トップが「犠牲者を出さない」という強い意識を持ち、労働環境を改善することが重要だと、寺西さんは強調する。
「『生活や健康を顧みず働くのが良いことだ』と評価するトップの価値観は、言動に必ずにじみ出ます。いくら上司に『あなたは休んで』と言われても、部下は休みづらくなりますし、過労死防止への『本気度』も、失われてしまうのではないでしょうか」
くしくも11月は過労死等防止啓発月間に当たる。寺西さんは「命より大事な仕事はありません。安全に働ける環境を整え人の命を大切にするのが、経済団体や政治本来の役割」だと訴えた。
WHO(世界保健機関)とILO(国際労働機関)は2021年、長時間労働によって虚血性心疾患と脳卒中のリスクが高まるとの研究結果を発表し、WHOのテドロス事務局長(当時)は「脳卒中や心臓病のリスクを負う価値のある仕事などどこにもない」と訴えた。
「国際社会も、日本を含む各国政府や企業に長時間労働をしないよう求めています。そんな中で、日本だけが昔の働き方へ逆行することはあってはならないのです」

長時間労働の是正、ハラスメント防止に向け、労働組合が重要な役割担う
寺西さんは政府に対して、勤務間インターバルの導入義務化やハラスメント対策などを通じて、長時間労働とハラスメントという過労死の2大要因を排除するよう求めている。また労働基準監督署にも、上限を超えた時間外労働などの違法行為に対して「積極的に徹底した監督・指導に取り組んでほしい」と訴えた。
労働組合には、経営側が労働時間管理やメンタルヘルス対策、ハラスメント対策などを適切に行っているかを日常的にチェックするとともに、不十分な場合は労使交渉などを通じて改善を促すよう要望した。また組合役員などが、組合員に「いつも遅い時間に職場にいるけれど、体調は大丈夫?」などと、きめ細かく声掛けする努力も大事だという。
「労働組合と組合員の関係はやや希薄化しているように思えますが、職場の実態や情報を最も把握しやすいのは労働組合ですし、本来は使用者には言えないことも組合には言いやすいはず。ぜひ、労働者が相談しやすい雰囲気づくりに努めてほしいと思います」
連合に対しては、労働政策の決定プロセスに関わる労働政策審議会のメンバーとして「命を大切にする社会」の実現をめざした政策に取り組んでほしいと語った。
「連合は、労政審で労働者代表という非常に重要な役割を担っています。健康で充実して働き続けることのできる社会をめざすという過労死防止の理念にのっとって、意見反映などを進めていただきたいです」
(執筆:有馬知子)