6月は「連合男女平等月間」であると同時に、LGBTQ+の人権について啓発する「プライド月間」。世界各地でレインボーフラッグを掲げた「プライドパレード」といったイベントが開催されている。昨年まで4月に実施されてきた「東京レインボープライド」が、今年から名称を「Tokyo Pride」に変更して、6月に開催される。
連合は、2016年に「LGBTに関する職場の意識調査」を実施、2017年には「性的指向及び性自認(SOGI)に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン」を策定し、職場での環境整備を進めるとともに、関係団体と連携して差別禁止やSOGIハラスメント防止のための法整備に取り組んできた。
2023年には「LGBT理解増進法」が制定され、多様性の尊重は進んだ面もあるが、相次ぐ性加害問題をめぐって、「ビジネスと人権」の視点からジェンダーやセクシュアリティをはじめ日本企業の「人権軽視」の風土が問われる事態となっている。
さらにアメリカでは、トランプ新大統領が就任演説で「米政府の公式方針として性別は男性と女性の2つのみとする」と発言し、人種や性別の多様性を重んじるDEI(多様性、公平性、包摂性)政策を敵視する姿勢を鮮明にしている。 連合は、今期運動方針で「ジェンダー平等・多様性推進」を重点分野に掲げているが、性的マイノリティに関する情報発信を行う一般社団法人fairの松岡宗嗣代表理事は「ジェンダー平等とLGBTQ+の問題は、同じ根を持つ地続きの問題」と指摘。様々な動きが錯綜する現状をどう捉えればいいのか。なぜ多様性の推進が求められるのか。労働組合に求められる役割は何か。松岡代表理事と芳野会長が語り合った。
(季刊RENGO2025年夏号転載)
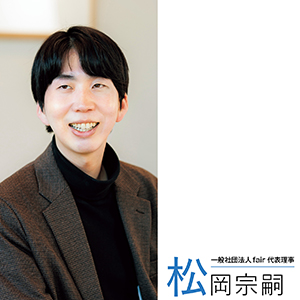
松岡宗嗣 まつおか・そうし
一般社団法人fair代表理事
明治大学政治経済学部卒業。ゲイであることをオープンにしながら、Yahoo!ニュースやGQ等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等で研修や講演を行う。映画(『エゴイスト』『52ヘルツのクジラたち』)やドラマ(『日本一の最低男※私の家族はニセモノだった』)などの監修も行う。
著書に『あいつゲイだって—アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、共著『LGBTとハラスメント』(集英社新書)など。
一般社団法人 fair
「どんな性のあり方でも、フェアに生きられる社会」の実現をめざして、2018年に設立。政策や法制度を中心としたLGBTQ+に関する情報発信やキャンペーン、イベント、講演・研修、コンサルティング等の活動を行っている。https://genda-radio.com


「LGBT理解増進法」制定から2年 ―その経緯と評価
当事者ではなく社会の側に壁がある
井上 松岡さんとは長いおつきあいですが、最初に自己紹介をかねて、fairの活動を始めたきっかけをお話しいただけますか。
松岡 私は「LGBTQ+」でいうと、ゲイ(G)の当事者です。高校を卒業し東京の大学へ進学した後に両親にカミングアウトしました。大学生活でもスムーズに受け入れられることが多かったのですが、当時LGBTQ+の友人のほとんどはカミングアウトしておらず、家から追い出された、就活で排除された、自死未遂をしたなどという話をたくさん聞きました。なぜ、性自認や性的指向が違うだけで、こんなに苦しい思いをしなければいけないのか。それは、当事者側じゃなくて社会の側に壁があるからだと思い、NPOなどの活動に参加するようになったんです。その中で、現在、LGBT法連合会の事務局長である神谷悠一さんとの出会いもあり、当事者の生きづらさを解消していくには、セーフティネットとしての法制度が必要だと気づかされました。そのために一般の人々にも、当事者に向けても、情報を発信していこうと、2018年にfairを立ち上げました。
芳野 連合は2016年に「性的指向及び性自認に関する差別禁止」に向けた当面の対応方針を確認し、「LGBTに関する職場の意識調査」を実施しました。当時、職場の労使の間で更衣室やトイレの配慮をどうするかという議論が始まりつつあったのですが、なかなかそれが表に出てこない。連合は「人権を守る」という視点で、LGBTQ+の課題をオープンにしながら議論を深めていくことが重要だと考え、その一歩として調査を行ったんです。
マイノリティではなくマジョリティのための法律に
井上 連合が対応方針を決定して調査を実施したのが2016年。松岡さんがfairを立ち上げたのが2018年。
芳野 当時、当事者団体などを通じて深刻な差別やハラスメントの実態が明らかになり、LGBTの権利保障や差別禁止、SOGIハラ防止の法整備を求める声が高まっていました。2020年に施行されたパワハラ防止法の指針に「パワハラにはSOGIハラおよび同意のない暴露であるアウティングも含まれる」ことが明記され、次は差別禁止法の制定だという流れの中で、関係団体との連携強化を進めてきた経緯があります。
松岡 2010年代初めに、ビジネスの観点から経済誌でLGBT特集が組まれるようになり、2015年には渋谷区や世田谷区でパートナーシップ制度が導入され、企業でも同性パートナーへの福利厚生適用などの対応が広がり始めました。その時流の先に2016年の連合調査があったのだと思います。職場の課題を浮き彫りにした貴重な調査で、私もたくさん引用させていただきました。
井上 連合は、「LGBT差別禁止法案」の成立を求めていましたが、超党派の議員連盟で合意した案から国会提出の過程で内容が大きく変更され、2023年に「LGBT理解増進法」が成立します。「マイノリティのための法律がマジョリティのための法律になってしまった」とも言われましたが、松岡さんの受け止めは?
松岡 差別や偏見をなくすために、国がなすべきことは第一に法律で差別的取り扱いを禁止すること。ところが、理解増進法の立法過程で、政治による無理解が広げられる事態が起きました。特にトランスジェンダーに対するバッシングは悪質で、トイレや公衆浴場、スポーツの問題だけが意図的に取り上げられ、SNS上で当事者団体に誹謗中傷が浴びせられたり、自治体と連携した居場所事業や啓発教育にも圧力がかけられたりした。結果、めざすべきは「差別の禁止」のはずなのに差別禁止規定は入らず骨抜きに。マジョリティの無理解が原因で差別や偏見が起きているのに、「すべての国民の安心に留意する」という、実質マジョリティに配慮する条文が加えられた法律が成立したわけです。さらに、施行から約2年経っても基本計画すら策定されていない状況です。
多様性尊重に逆行する動きと日本の現状
時代を映し出すドラマで自分自身もアップデート
井上 この10年の多様性をめぐる社会の変化をどう捉えていますか。
松岡 まさに「激動の10年」。私が活動を始めた頃は、「LGBT」の一般的なイメージは著名なオネエタレントの方など「女装の男性」。私も当事者だと言うと、「普通の学生に見える」と驚かれましたが、今はその言葉の意味を多くの人が理解するようになっています。
最近の調査では、まだまだ少ないとはいえ約3割がLGBTQ+を「自分の身近にいる」存在だと認識し、パートナーシップ制度を導入する自治体も急速に増えて人口カバー率は9割を突破。パワハラ防止法にSOGIハラが入ったことで企業の取り組みも進んでいる。司法においても、同性婚を認めない現行法は違憲であるという判断が相次いでいて、判決文を見ると理解増進法が後押しになっています。
芳野 変化を感じるのは、ドラマや映画で多様性の尊重が描かれるようになったこと。若い世代、特に子どもたちの世界の中では多様性が当たり前になっていますが、意思決定の場で多数を占める男性のアップデートは進んでいません。
松岡 最近、ドラマの監修を頼まれることが増えています。今年1月から放送された『日本一の最低男※私の家族はニセモノだった』(フジテレビ系放映・香取慎吾主演)では、第2話の同性カップルの話を中心に監修したのですが、他にも子どもの居場所づくりに奔走したり、保育士が処遇改善を求めてストライキしたり、社会課題がテーマに取り上げられていた。労使交渉の場面なんて、少し前のドラマならなかなか出てこなかったのではと時代の変化を感じました。労働組合も変わりましたか?
芳野 連合が結成されて35年、私が会長になって3年半。「連合運動のすべてにジェンダーの視点を」と掲げ、「変わった」という評価もいただきますが、気を抜くと男性ばかり並んでいるし、政策課題についても本質的な議論が足りていないと感じます。
1990年代半ば、国際会議で「ジェンダー」という言葉が一般に使われるようになった頃、連合本部のHPに「ジェンダー・チェック」を掲載したところ、構成組織から「ジェンダーとはなんだ! 男性には男性の、女性には女性の特性がある。男らしさ・女らしさの何が悪い!」という苦情がきました。連合東京の執行委員会でも議論しましたが、今で言う「炎上」状態になり、一時期、連合の文書から「ジェンダー」という言葉が消えました。その頃に比べれば、女性役員は増えましたが、男性社会からの脱却は道半ばです。
松岡 ええ〜! 本格的なバックラッシュが起きる前にそんなことがあったんですね。
トランプ政権の影響を受けやすい日本
井上 アメリカではまさに今、激しいバックラッシュが起きています。
松岡 昨年11月、渡米してニューヨークとフロリダに行き大統領選挙戦を見てきました。アメリカは「揺らぐ国」だと実感しましたが、勝利したトランプ氏は、人権を否定する排除的な政策を次々と打ち出し、企業や教育機関にも圧力をかけ始めた。
危惧しているのは、日本がトランプ政権の影響を受けやすい状況にあることです。研修に協力してきた企業の担当者からは「LGBTQ+やジェンダー平等に関する取り組みはやめておいたほうがいいという声が社内で出ている」という話も聞いています。
芳野 今、アメリカでは、「ジェンダー(gender)」という言葉が使えなくなってきていると聞きました。ただでさえ日本は世界から周回遅れなのに、バックラッシュだけ輸入されたら大変です。
松岡 DEIと総称される、ダイバーシティ(Diversity)、エクイティ(Equity)、インクルージョン(Inclusion)という言葉も使えなくなっています。言葉を奪われていくのは、2000年代に日本で起きたバックラッシュと重なります。
でも、世界はアメリカだけじゃない。EUでは、包括的な差別禁止法が制定されていて、DEIを積極的に推進していく立場を崩していない。日本の企業には「ビジネスと人権」を長期的に捉えて冷静に対応してほしいと思います。
ジェンダー平等・多様性推進へのアプローチ
−「ビジネスと人権」という視点から
多様性を排除することは選択肢としてあり得ない
井上 改めて世界における日本の状況とは?
松岡 2023年のG7サミットは広島で開催されましたが、議長国日本は、G7の中で唯一SOGIの差別的取り扱いを禁止する法律も同性カップルの権利保障もなかった。G7各国から首相に対応を促す異例の書簡が送られ、それをバネに法制化の機運が醸成されました。G7という“外圧”の重要性を感じつつ、外面重視が内容の後退を許してしまったという反省点もあります。
芳野 労働組合の国際組織は、G7にあわせてL7(労働サミット)を開催しているのですが、そこでも日本での法整備を積極的に進めることが決議されました。
井上 「ビジネスと人権」という視点からも重要課題となっているのに、なぜ日本では進まないのでしょう。
松岡 同性婚も差別禁止法も選択的夫婦別姓も、労使がともに求めているのに政治は動かない。ジェンダーやセクシュアリティの課題には「絶対反対」を掲げる政治勢力が存在するからです。
芳野 反対勢力は、誰も困っていないとか、もっと重要な課題があるとか主張してきますが、目に見えない差別や不利益は、今もあちこちに存在しています。労働組合として、それがどこにあるのかに気づき、「差別は人権の問題」だということを強く訴えていく必要があると思っています。
松岡 同感です。トランプ大統領は「多様性尊重は少数者の優遇だ。これをやめて実力主義に変える」と主張しますが、実力主義と多様性は矛盾しない。同質性の高い人材ばかりになれば、重大なリスクを見落としたり、イノベーションが起きなくなったりする。特に人口減少社会・日本では、多様性を排除することは選択肢としてあり得ないんです。
芳野 オールドボーイズネットワークが力を持つ政治の世界こそ多様性が必要ですよね。
松岡 4月に開幕した大阪・関西万博のテープカットは、全員男性で「数合わせ」すらされていなかった。フジテレビの性加害問題も同じです。同質的な男性中心の組織の中で、性暴力が矮小化される風土が形成されていったと思います。
マイノリティの排除とジェンダーバランス
井上 なぜ、女性やマイノリティを排除しようとするのでしょうか。
松岡 公開中の『ウィキッド ふたりの魔女』(ユニバーサル・ピクチャーズおよびマーク・プラット・プロダクションズ)という映画がその構造を見事に描いています。マジョリティの「共通の敵」をつくり、それを排除することでみんなの困難の責任を転嫁し、団結させようとする。まさに今の日本と世界の政治状況です。
井上 社会を変えるには?
松岡 最近、都内で料理店を開いている友人から、こんな話を聞きました。会社員のグループで、年配の男性が若い男性に対して「おまえゲイだろう」としつこく絡んでいた。友人はゲイの当事者で、同じ仲間も一緒に働いているんですが、聞くに堪えない言葉が飛び交って苦痛だったと…。自分のすぐそばに当事者がいるかも、ということが想像できていないのだと思うし、この年配の男性のような意思決定層におけるジェンダーバランスを変えていかないと認識は変わらないと思います。
芳野 そうなんです。だから、労働組合の意思決定過程への女性参画が必要なんだと、私たちはずっと言い続けてきたんです。
地方女子の生きづらさに共感
井上 先日、SNSにおばあさまと一緒に登場されていましたね。
松岡 それも社会を変える一助になればと…。うちは自主自立を重んじる雰囲気の家族で、祖母も私のカミングアウトをすんなり受け入れてくれた。でも「祖父母には言えない」と悩んでいる当事者は多いので、こんなおばあちゃんもいると発信してみたんです。祖母は九州の保守的な地域出身ですが、ちゃんと自分の世界を持っているから他者を尊重できるのかなと。
芳野 素敵ですね。今、政府は「地方創生2・0」を掲げていますが、地方の保守的な価値観に生きづらさを感じて都市圏に転出する女性が増えています。
松岡 私は名古屋出身ですが、都市部でありながら保守的な土地柄で、小さい頃から息苦しさはあり東京に出たいとずっと思っていました。女性たちが地方を出たくなる気持ちをすべては理解できていないけれど、共感します。LGBTQ+の権利とジェンダー平等はつながっているんです。
めざす社会と労働組合への期待
問われるのは「当事者性」
井上 労働運動に期待することは?
松岡 私はゲイの当事者であり、問題意識を持ってLGBTQ+の社会運動に関わってきましたが、その活動を通じてジェンダー平等や外国人排除の課題にも気づかされました。労働組合は自ら目的意識を持って入る人は少ないと聞きますが、やはり多様な人や社会課題に出会える場になっているのではと思います。
今、連合のような中間団体の存在感が薄れ、個人と社会の間が疎遠になり、SNSのイメージの世界とだけつながっているような危うさを感じます。歴史ある労働組合は、法的に守られ、交渉のノウハウをたくさん持っています。多様な人たちで構成される中間団体としてもっと機能してくれることを期待しています。
ジェンダー平等も性的マイノリティの権利保障も、アイデンティティのみの問題と捉えられがちですが、生活の話であり、労働の話。生活の困難をみんながつながって解決していける社会を一緒にめざしていけたらと思います。
芳野 今ジェンダー平等参画を進めなければ、社会から取り残されるという強い危機感を持っています。労働組合として人権をきちんと捉えた運動が必要であり、そこで問われるのは「当事者性」です。「当事者性」を高めるためにも多様な人々の参画に全力で取り組んでいきたいと思います。
井上 ありがとうございました。



