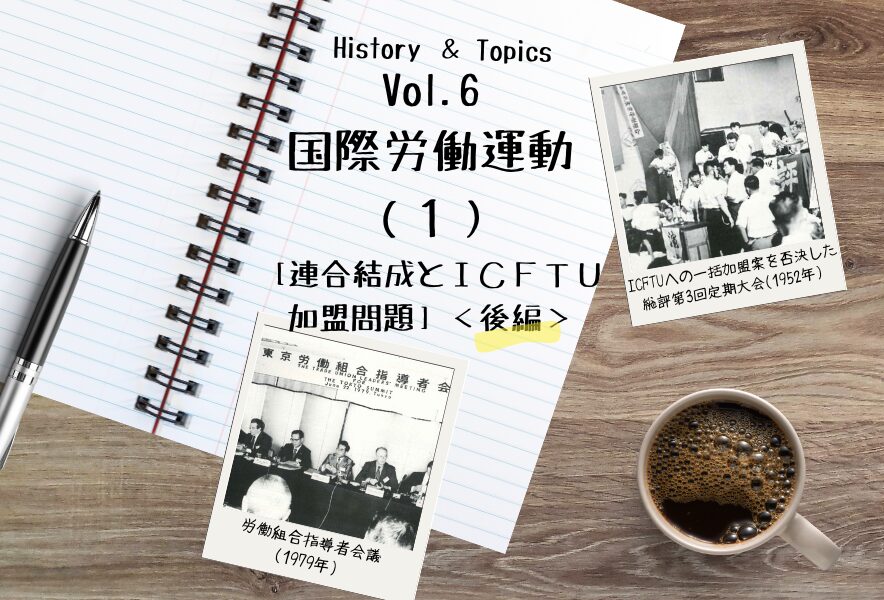労働組合運動の強みは、企業を超え、産業を超えて、働く人たちがつながりあえることだと言われるが、実は国境を超えてつながろうという「国際連帯活動」も長い歴史を持っている。しかも、経済のグローバル化が進む中で、その重要性はますます高まっている。ということで、RENGO ONLINE「労働組合の歴史」新シリーズは、「国際労働運動」をテーマに連載スタート。
日本の労働組合は、国際労働運動をどう捉え、どう関わっていったのか。
連合国際局で長く実務にあたった生澤千裕日本ILO協議会理事の全面協力を得て、「連合結成とICFTU(国際自由労連)加盟問題」〈後編〉では、日本の労働組合の対応を中心にその歴史をたどっていこう。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)
日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー
1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバー・サミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。
日本の労働組合と国際労働組合組織との関係
日本の労働組合は、めまぐるしい国際労働運動の動きにどう対応したのか。
終戦後、GHQ(連合国最高司令官総司令部)は、民主化の柱の一つとして労働組合結成を奨励しました。全国各地で労働組合が結成され、戦前からの流れを汲む産業別組織やナショナルセンターの再建も取り組まれました。
いち早く活動をスタートさせた総同盟(日本労働組合総同盟)や産別会議(全日本産業別労働組合会議)、日労会議(日本労働組合会議)は、いずれも全国組織としてWFTUに加盟する方針を持っていました。
1947年3月、総同盟と産別会議は全国労働組合連絡協議会(全労連)を結成してWFTUに加盟申請し、1949年に承認されますが、その時点ですでに総同盟は全労連を脱退。ICFTU結成と連動するように、日本では1948年頃から職場で日本共産党の組合支配に反対する「民主化運動」が広がっていたからです。
日本では、戦時体制下において、労働組合や、社会主義、共産主義を掲げる政党は非合法化され厳しく弾圧されました。戦後、政党活動家の一部は、労働組合の内部にグループを作り、運営の主導権を握って本来の労働組合活動より政治的な闘争を優先させるようになります。こうした政党による支配を排除し、運営を民主化して本来の労働組合活動を取り戻そうという動きが生まれ、自らを「民主化同盟」と称して「労働組合主義」を掲げる運動を展開しました。
民主化同盟グループは、国際共産主義運動の性格を強めるWFTUへの加盟に反対し、1949年9月に「国際自由労連加盟促進懇談会」を開催。ICFTU結成の動きを受けて、11月には国労、海員組合、総同盟、日教組、炭労、全鉱、全日労の7組合が「国際自由労連日本加盟組合協議会」を設置。結成大会には国労、全日労、全繊同盟、全鉱、日教組から計5人の代表団が参加しました。
その翌年の1950年7月、ナショナルセンター「総評」が結成されます。総評の運動の基本理念には「あらゆる自由にして民主的な労働組合の結集された力によって、労働者の労働条件を維持、改善し、その政治的、社会的地位の向上をはかり、日本の民主主義革命を推進するとともに,社会主義社会の建設を期す」と記され、当面の行動綱領には「国際自由労連への加盟の速やかな実現を期す」と明記されました。
実際に、ICFTUに加盟した7組合に加えて、日放労、全農林、私鉄総連、全逓が日本加盟組合協議会に参加してICFTU加盟を果たしました。

出所:公益財団法人総評会館 総評退職者の会
「平和4原則」をめぐって総評が方針変更
これで一件落着と思われたが、総評は翌年「一括加盟方針」を取り消し、「ICFTU加盟問題」はさらに紆余曲折をたどることになる。
何があったのか。
総評が結成された1950年、米ソ代理戦争とも言われた朝鮮戦争が勃発。アメリカの対日政策は「民主化と再軍備廃止」から、「再軍備」へと転換し、日本は、軍需物資を中心とする朝鮮特需により急速に経済復興を果たしていく。
こうした情勢を受けて、総評は1951年の第2回大会で「平和4原則(全面講和・中立堅持・軍事基地提供反対・再軍備反対)」を採択。同時に「ICFTU一括加盟」の方針を否決した。そして、1952年の第3回大会で、加盟は当面各単産の決定に任せることとされたのである。
生澤さんはその経緯をこう解説する。
総評における平和運動や国際活動の基本方針となる「平和4原則」をめぐる論議の中で、ICFTUの朝鮮戦争などへの態度に疑念が示され、各単産のスタンスに変化が生じたのだと思います。具体的にこの辺りの事情が記載されたものとしては、総評第3回大会に提案された「ICFTUへの加盟については当面各組合の自由な意志を尊重する」という方針案があります。そこには「われわれは今もなお、自由な労働組合の国際的団結の必要を信じ、これを支持する」が、「朝鮮動乱後、われわれが単独講和に反対し、再軍備に反対している時、国際自由労連は・・・サンフランシスコ単独講和および安保条約についてはこれを積極的に支持し、・・・日本人の切実な念願である再軍備反対については、何ら協力しなかった。このような事情から今年度になって急激に日本の労働組合の間に国際自由労連に対する批判が芽生えた」となっているのです。
なお、事実関係では、総評とICFTUとの間に誤解が生じていたようで、後日、ICFTUからの弁明がなされています。ICFTUは日本の加盟組合の要請に応じて『可及的速やかに対日講話条約が締結されることを要請する』決議を採択したことは事実だが、講話条約締結の手続きや講話の条件については討議も決定もしていない。また、『日本の反共防衛軍の支持』については、事実無根である。ICFTUは自衛権は認めるが、自衛する義務ありと断じていない」などとしています。

出所:公益財団法人総評会館 総評退職者の会
いずれにしても、この総評の方針転換は、ナショナルセンター分立の動きへとつながっていく。
全繊同盟・海員組合・全映演は1953年、「一括加盟方針」撤回を批判して総評を脱退。この3組織と総同盟が1954年に合流して全労会議(全日本労働組合会議)を結成した。総同盟は、その時点でICFTUに加盟が認められていたので、全労会議として一括加盟申請を行ったが、それが実現したのは1964年4月のことだった。
同年11月に「同盟」が発足すると、同盟は、全労会議と総同盟の継承団体として1965年1月にICFTU一括加盟を認められ、1964年12月にはOECD(経済協力開発機構)の労働組合諮問委員会(TUAC)にも加盟した。
一方、総評は「組織的中立」「積極的中立」の方針の下、ICFTUとWFTUとの間で連携関係を様々に変化させた。1953年に国労と私鉄総連、1958年には日教組がICFTUを脱退したが、その後、高度経済成長を経て、国際・国内情勢が大きく変化する中で、1977年には同盟と総評加盟の5単産(全逓、炭労、都市交、全鉱、日放労)によって、ICFTU日本加盟組織連絡協議会(ICFTU-LC)が設置された。
そして、1979年に日本で開催されたG7サミットに対応する先進国労働組合指導者会議(レイバー・サミット)は、総評と同盟が共催する形で開催された。

出所:公益財団法人総評会館 総評退職者の会
生澤さんの初めての仕事は、このレイバー・サミットへの対応だったという。
私は、1979年3月に同盟国際局に入局しました。同年、日本でG7(先進国首脳会議)が開催され、それにあわせて先進国労組指導者会議が開催され、議長国日本の大平正芳首相に政策要請を行うことになりましたが、そのスタッフが足りないと、同盟が国際局員を募集していたんです。
ということで、最初の仕事は、まさにG7と労組指導者会議への対応でした。
総評も中立労連もその前年にはTUACに入っていたので、一緒に対応しました。その後も、総評の国際局のメンバーとはILOの会議などで顔を合わせることが多く、良好な関係だったと思います。
国際社会で果たすべき役割が拡大する中で、総評の国際労働運動のスタンスもICFTU重視に変化し、労働戦線統一の動きがその背中を押すことになったのではないかと思います。
そして、1980年代に「民間先行」労戦統一の動きが進展する中で、総評はICFTUとの連携を強化していったが、それでも「ICFTU一括加盟問題」は連合結成の直前まで議論が交わされる課題となった。
加盟を条件にすることは選別につながりかねない
1976年、連合の前身となる政策推進労組会議が誕生。1980年に「民間先行の労働戦線統一」という方針の下に結成された全民労協は、「新連合体は国際自由労連に一括加盟する」とのスタンスを確認。民間連合の「進路と役割」にもそれが引き継がれた。
労働4団体のうち、同盟と中立労連は一括加盟方針を支持するが、総評は「ICFTUへの加盟を条件にすることは選別につながりかねない」と、これに慎重な態度を示した。
この相違をどう乗り越えたのか。
1987年11月20日の民間連合結成大会には「国際自由労連への加盟について」が独立の議案として提出されました。ここで、①連合はICFTUに加盟する、②ICFTU-APRO(国際自由労連・アジア太平洋地域組織)に加盟する、③ICFTU-LC(国際自由労連・日本加盟組織連絡協議会)に参加するという3点を確認し、すでにICFTUに加盟している組織は加盟形態の変更を行うという方針を決定しました。
これを受けて総評は、1988年7月の大会で「国際自由労連加盟検討委員会」の設置を決め、ICFTU加盟の意義と問題点についての検討を進めます。その結果1989年9月の大会でICFTU加盟が提案・採択され、総評は直ちに加盟申請を行いました。その後、連合結成に向けて総評は解散しますが、1989年11月29日、ICFTU執行委員会は申請時に遡っての総評の加盟を承認しました。
1989年11月の官民統一連合の結成大会で採択された運動方針には、「国際自由労連の構成組織として・・・国際社会における役割と責任を自覚し、主体的かつ積極的に国際労働運動の前進に貢献する」と記され、連合は結成直後にICFTUに民間連合から連合への加盟名義の変更を行い、連合に新たに加わった全逓、都市交、全官公の各組合は個別加盟から連合による一括加盟へと加盟形態の変更を申請。ICFTUは1989年11月29日にロンドンで開いた第96回執行委員会でこれを承認した。
生澤さんは、こう投げかける。
ICFTUとの関係は、東西冷戦構造の存在や、その影響を受けた日本の労働運動の分裂によって複雑な経緯をたどってきましたが、まさに連合が結成された時、東西冷戦構造の崩壊と労働戦線統一というタイミングで、40年の年月を経て正常化したといえるでしょう。
労働戦線統一の過程において、連合がICFTUに一括加盟すること自体が大変大きなテーマでした。ここは、今日に至る国際労働運動の入口として、しっかり押えておいてほしいと思います。
【前編】へ戻る
(執筆:落合けい)
〈参考文献・サイト〉
※独立行政法人 労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/foreign/index.html
国際労働運動の歴史と国際労働組合組織
※『総評結成40年 かく闘い、かく歩む 1950〜1989』(公益財団法人総評会館 総評退職者の会)
※『ものがたり 戦後労働運動史Ⅰ』(教育文化協会)
『ものがたり 戦後労働運動史Ⅱ』(教育文化協会)