だれでもどこでも時給1,000円
今年度の地域別最低賃金の改定額が決定した。全国加重平均は、6.3%アップの1,121円となり、初めて全都道府県で1,000円を超えた。連合が「だれでもどこでも時給1,000円」のスローガンを掲げて最低賃金の大幅引き上げを求めたのは、2006年のこと。当時の全国加重平均が673円だったことを考えると、20年越しとはいえ、どこでも1,000円に到達できたことをうれしく思う。
連合がめざす次のステップは「一般労働者の賃金中央値の6割水準」という中期目標の実現だ。国際的に日本の最低賃金の水準は低い。EU(欧州連合)は、2022年に「最低賃金は労働者の賃金中央値の6割とすべき」という指令を採択したが、その時点での日本の水準は中央値の45.6%。また、物価高騰や人材流出への危機感、賃上げを起点としたデフレ脱却という観点からも最低賃金引き上げの必要性が認識されるようになった。2023年には岸田内閣が「2030年代に最低賃金1,500円」という政府目標を掲げ、石破内閣はその達成を「2020年代中」に前倒しした。
そのためには、向こう5年間、7%の引き上げが必要になる。今年度は、「政府主導」で過去最高の引き上げが実現したとの見方もあるが、一方で、中小零細企業の準備期間が必要として、11の県が改定のタイミングを11月以降に遅らせるという異例の事態も起きている。地方の賃金水準の底上げをはかる環境整備が不可欠だ。政府は、中小零細企業への助成金拡大などを打ち出しているが、それだけでいいのかとモヤモヤしていたら、またもやNHK『クローズアップ現代』がしっかりと切り込んでくれた。
ジェンダーの話をすると「珍獣」扱い?!

9月24日放送の「最賃1,000円超だけど…どうする地方女性の低賃金」だ。当コラム17回で取り上げた「女性たちが去っていく 地方創生10年・政策と現実のギャップ」(2024年6月17日放送)の続編である。
最低賃金レベルで働く人は約700万人。うち女性が7割を占める。日本の男女の賃金格差は、男性100に対し女性は75.8(2024年)。最低賃金引き上げをめぐる課題は、男女間格差、地域間格差という問題とクロスしているが、番組は「地方女子プロジェクト」の視点から、その背景を明らかにしていく。「地方女子プロジェクト」とは、山梨県在住の山本蓮さん(26歳)が立ち上げたもの。「日本では約8割の地域から若年女性が首都圏に流出し人口減少や地方衰退の原因であると言われている。でも、それって私たちが問題ですか?」と投げかけ、これまで地方の女性100人以上の声を集め、SNSなどで発信してきている。
番組の冒頭は、「地方女子の話をしよう」というワークショップのシーン。地方在住や地方出身の若い女性が、「地元だと男性がメインで稼いで、女性はサブで稼ぐパートぐらいでいいでしょっていう価値観がすごく強くて」「待遇の男女格差を口にするのはタブー、ジェンダーに関しての話をすると、なんだこいつと珍獣扱い…」と訴える。
地方創生を掲げる石破総理大臣がこの地方女子プロジェクトに着目し、山本さんの話を聴くというシーンもあった。「地方にはやりたい仕事がない。結婚・出産の圧力が息苦しい。地域で女性の役割を求められるのがイヤだ」という地方女子の声を伝えると、総理はこう答えた。「地方のオジサンたちは、女性が何を考えてるかわかんない。お互い話し合ってみると、ああそうなのねみたいなところ、私はあると思っているのですよ」。
総理自身はどう受けとめたの?と突っ込みたくなるが、本当に話し合ってわかりあえるのか。山本さんは、地元山梨で、自分の父親(60歳)と旧知の自治会長(63歳)に地方女子の思いを直接伝えたのだが、さて、2人の地方オジサンの答えがある意味凄かった!
「地域社会での女性の生きにくさ、家庭に入って固定的な役割を期待されちゃうというのは、なかなか一朝一夕に直らないかもしれないね」「だって、家に帰ってこれから夕飯の支度するんだぞって言ったら、できる?」「いや、できないなあ、ボクには」「残業して、帰ってきて夕飯の支度をして、お風呂を入れて、洗濯をして…。スーパーマンじゃなきゃできないよね。それを今、一部の女性はやっているかもしれないね」と無邪気に他人事として語るオジサンたち。
若い女性が流出するのも当然である。だが、山本さんはオトナである。「悪気なく、そういうものだということで続いてきていることなので、やはりちゃんとどう変えてほしいのか、言っていかないとダメだなと思ったし、そういうふうに話し合える場をつくっていくことが大事かな」と総括していた。本当に感服する。
番組の解説者、小安美和さん(Will Lab代表取締役)は、女性活躍を進めようとすると「この地域では難しい、中小企業では難しい、女性自身が望んでいない」というのが必ず言われる三点セットだと指摘する。職場にも家庭にも性別役割分担が根強く残っていることが女性の低賃金につながっていて、若い女性の流出を引き起こしている。最低賃金を早期に引き上げ、地域の賃金水準の底上げにつなげていくには、やはりこの問題にしっかり向き合う必要があると思う。
山本さんと同い年のZ女子にも番組を観るよう勧めた。
「珍獣上等。噛みつかないとわかんないんだよ!」
「ボクにはできない? おまえがやるんだよ!ってはっきり言ってやりなよ」と画面に話しかけている。Z女子も職場で「珍獣」扱いされてきた1人だ。「親の顔が見てみたい」なんて思われているに違いないが、はっきり言わないと変わらないのだと思う。
女性参画と非正規雇用で働く女性の処遇改善
労働組合の世界でも同様の空気はある。本田一成先生の連載「クミジョ・ファイル」にも描かれていたが、クミジョによる男女の格差や差別の訴えは、無視されたり、なかったことにされたりしがちだ。男女間賃金格差の是正は、毎年の春季生活闘争の1つの柱にはなるが、メインの扱いとは言いがたい。
先日、「春闘」に関する連合のシンポジムで、芳野友子会長が会場からこう発言した。
「日本が一番遅れているのは、女性参画と非正規雇用で働く女性の処遇改善。その決定的な要因は議論の場に女性が少ないことだ。だから、連合はジェンダー平等・多様性推進を運動の柱に置き、意思決定の場に女性を増やそうと取り組んでいる。賃上げ水準の議論も世帯主をメインにしていては、女性や非正規雇用労働者が取り残されてしまう。男女間賃金格差の視点を持って、一人ひとりの賃金が公正で働きに見合ったものかを見て、女性の賃金を底上げしていくことが大事だ」と。長年、男女間賃金格差の是正に取り組んできた芳野会長は、当然ながらやるべきことがわかっているとうれしくなったが、この発言がちゃんと受けとめられているのかと不安にもなった。
地方女性の賃金を引き上げるには、その働きを公正に評価する仕組みや両立支援制度を整備し、女性の活躍を企業の生産性向上や地域の活性化につなげる政策が必要なのだと思う。
複雑怪奇な「年収の壁」の整理も必要
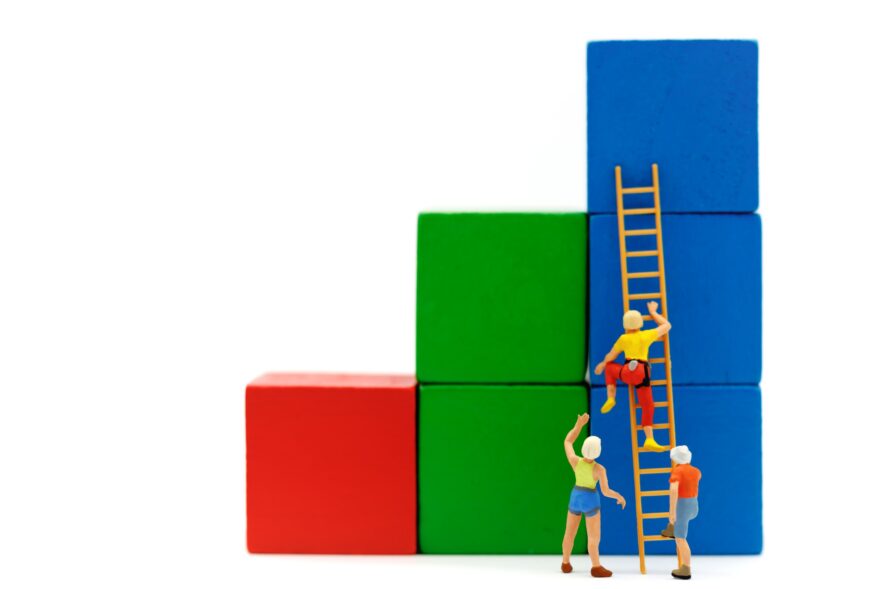
さて、家庭内Z世代男子は、週3回、近所の雑貨店でアルバイトをしている。基本の時給は、ほぼ東京都の最低賃金だ(土日や22時以降の割増あり)。10月に最低賃金が改定されると、それが反映されて時給はアップするが、バイト先のほうで年収103万円を超えないようシフトを調整してくれていた。
ところが、2025年度の税制改正で所得税の課税最低限が160万円に引き上げられた。学生バイト仲間でも、シフトをどこまで増やしていいのかが話題になったが、最近、別の壁が発覚して12月は休むことになった人もいるという。
「ねえ、壁、得意なんでしょ。みんなどうすればいいかわかんないって言っているから教えてよ」とZ男子。「年収の壁」をめぐる本質的な問題は理解しているが、手取りの増減に関わる具体的な数字は、私の最も苦手とする分野だ。調べてみたが、住民税や親の扶養控除、社会保険などの壁が幾重にも巡らされていて複雑きわまりない。
「結論から言えば、学生は親の社会保険の扶養に入れる130万円以下にしておくのが無難だと思う」と答えたが、2020年代中に最低賃金1,500円をめざすなら、この複雑怪奇な各種「年収の壁」問題を早急に整理してほしい。
★落合けい(おちあい けい)
元「月刊連合」編集者、現「季刊RENGO」編集者
大学卒業後、会社勤めを経て地域ユニオンの相談員に。担当した倒産争議を支援してくれたベテランオルガナイザーと、当時の月刊連合編集長が知り合いだったというご縁で編集スタッフとなる。


