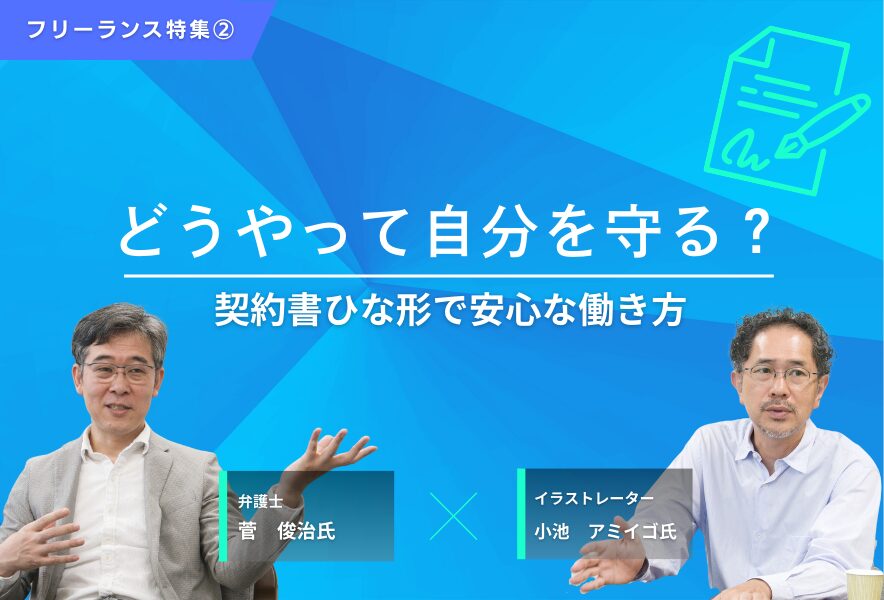口約束で仕事を引き受けたが報酬が支払われない、「イメージと違う」などと言われて何十回もの修正を迫られた―フリーランスのクリエイターで、クライアントとのトラブルを経験する人は少なくない。こうした事態を防ぐため、連合が立ち上げたWor-Qアドバイザリーボード(※)は、フリーランスで働くイラストレーター向けに契約書のひな形を作った(2025年10月公開予定)。Wor-Qアドバイザリーボードのメンバーで作成に関わった菅俊治弁護士とイラストレーターの小池アミイゴさんに、ひな形がもたらす効果などについて話してもらった。
※Wor-Qアドバイザリーボード:連合がフリーランスの課題解決に向けて、フリーランス当事者など多方面の様々な立場の方から意見を聴き、連合運動に対する助言・意見等をもらう場として2022年に立ち上げた。

小池 アミイゴ
群馬県生まれ。長澤節主催のセツモードセミナーで絵と生き方を学ぶ。1988年よりイラストレーターとして活動開始。 書籍や雑誌、広告、音楽家とコラボレートした仕事多数。1990年代はCLUB DJを兼ね、デビュー前夜のクラムボンやハナレグミなど多くの表現者の実験場を創造。2000年以降は日本各地を巡り、ライブやワークショップ、展覧会開催など地方発信のムーブメントをサポート。2011年3月11日以降、東北各地を巡り絵を制作、個展「東日本」を開催し続ける。絵本「ちいさいトラック」「とうだい」(作画)「かぜひいた」「うーこのてがみ」「はるのひ」。2019年台湾の台三線3週間の取材を行い「台湾客家スケッチブック」(KADOKAWA)を上梓。

菅 俊治(すが しゅんじ)
東京都生まれ。筑波大学附属駒場高校を経て、東京大学法学部卒業。1999年、司法試験合格後、2001年に弁護士登録。東京法律事務所に入所し、以降、労働問題を中心に活動を行う。日本労働弁護団の常任幹事を務め、2013年から2015年には事務局長としても活躍。日弁連労働法制委員会事務局長(2016年〜現在)としても労働法制の改革に取り組んでいる。
現在、B型肝炎訴訟東京弁護団の事務局長や、医療問題弁護団のメンバーとしても活動中。また、解雇や賃金問題、残業代、労災などの労働法全般を扱い、特に労働組合からの相談にも積極的に応じている。
「働き方改革」やギグエコノミー、雇用によらない働き方などのテーマで講演を行い、書籍『職場を変える秘密のレシピ47』の監訳も手がけた。
本来対価の発生すべき「業務」を書面化 発注者の責任も明記
-なぜ、イラストレーター向けの契約書のひな形を作ろうと考えたのでしょう。
菅弁護士:フリーランス当事者から寄せられる相談には、報酬未払いや遅延のほか無限定に義務を負わされた、すべての著作権を譲渡させられたといった、契約にまつわるトラブルが少なくありません。そこでフリーランスが自分の身を守れるよう、適切な契約をできるだけ容易に結べる「ひな形」を作ろうと考えたのです。
今回のひな形はイラストレーター向けで、契約期間が比較的長く報酬未払いなどのトラブルが多い「プロジェクト型」の契約を念頭に作成しました。単発短期型や、連載のような反復継続型の契約用に修正したり、他の業種の人が状況に合わせて内容を編集したりして使ってもらえるよう、誰でも無料で利用できるオープンライセンスでの公開を予定しています。
-アミイゴさんは活動する中で、契約トラブルに遭った経験はありますか?
アミイゴさん:若手時代には、発注者に「こんな作品じゃだめだ」とお説教された挙げ句、報酬ももらえない、といったことがありました。当時はそれを自分の力量不足と考えていましたし、業界全体にも「発注者に鍛えられて成長する」という空気がありました。
また僕の参加する「東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)」のメンバーは、著名なイラストレーターも多く、豪放磊落に振る舞う先輩たちへの憧れから「報酬額を聞くのは野暮だ」「黙ってお金を受け取るのがかっこいい」という気風も強くありました。
クリエイターの立場が強かった時代は、こうした商慣行もあまり問題にはなりませんでした。しかし時代とともに関係性は変わり、今やイラストレーターは「アーティスト」と持ち上げられてはいるものの、報酬の保障や適切な就業環境がない「底が抜けた」状態に陥っています。納品後、発注先に「求めていた作風と違う」と言われて報酬が支払われない、といったトラブルも多数起きています。
菅弁護士:トラブルの多くは「業務のどの部分に対価が発生するか」が曖昧なことによって起きています。このため発注者は、満足できる成果物が納品されたら報酬を払えばいい、と考えて際限なく修正を要求したり、仕事が中途で頓挫した時、それまでの報酬を支払わなかったりするのです。
ひな形では納期や修正回数の上限のほか、作成過程で発生するラフや草稿などの報酬も規定できるようにして、どの業務にどれだけの対価が発生するかを明確にしています。
また一般的な契約書は、成果物が第三者の権利を侵害した場合全般について、クリエイターが全責任を負う建てつけになっています。しかし内容を指定した発注者も責任を負担すべきだと考え、受発注者双方が、権利侵害を防ぐ責任を負うことを明記しました。さらにクリエイターが発注者に保証する責任(表明保証)も、翻案・複製をしないことなどに限定しました。
アミイゴさん:ひな形ができたことで、クリエイションも他の職業と同じように、「労働」として相応の契約条件と対価を要求できることが明示され、自分たちの仕事に確固たる足場ができたと感じています。
権利侵害に関しては最近、TISのメンバーが描いたある書籍の表紙イラストが、人権侵害だと批判される事例が起きました。発注者はイラストレーターを守ろうとせず、本人が情報開示や説明に追われました。権利を巡るトラブルについて「受発注者が協力して誠実に対応する」との文言がひな形に盛り込まれたことで、クリエイターの安心感も高まると思います。

発注者との対話が大事 コンテンツ産業を「世界標準」に変える
-ひな形の作成にあたり、発注者側にも意見を聴いたそうですが反応はいかがでしたか。
菅弁護士:内容について細かく点検し、有益な意見もたくさん出してもらえたので、おおむね前向きに受け止められたという感触です。発注者にもひな形の普及に力を貸してもらい、協力して公正な取引を浸透させることで、業界を盛り上げていければと考えています。
ただ中間報酬の定めや、著作権や著作者人格権を尊重する条項に、なじみが薄いところもあると思います。これまでのように無限の修正はできなくなり、追加の報酬が必要となるので、発注者サイドは予算の確保の仕方やプロジェクトの立て方に影響が出るでしょう。こうした項目について、引き続き説明し理解を求めていきます。
アミイゴさん:クリエイター側も、発注者と対立し要求を押し付けるのではなく、先方の状況も聞きながら、サステナブルな関係を構築していく柔軟性が求められるでしょう。発注者も、攻撃的にならず冷静に対話できるクリエイターと、一緒に仕事をしたいと考えるのではないでしょうか。
僕自身、ひな形作りに関わったことをきっかけに「リスクを避けるため、この部分は契約で明確にしませんか?」といった交渉ができるようになりました。このようにひな形は、発注者との対話を促すツールでもあります。まずは行政との取引でひな形を活用し、双方がWinーWinの関係を築けたという好事例を作ることで、ひな形の活用を拡大していきたいです。
菅弁護士:アミイゴさんやTISの会員のような「トップ・オブ・トップ」にひな形を活用してもらえれば、クリエイティブの業界全体が変わる第一歩になるのではないか、と期待しています。
また韓国では2009年、10の業界で88種類の契約書が作られました。日本もこうした動きに追いつけるよう、イラストレーター以外の職種についても、連合と協力して契約書のひな形作りを進めていこうとしています。
特に日本のアニメや漫画などのコンテンツは近年、海外での取引が増加しています。国際取引では、書面で契約を結ぶのが当たり前なので、コンテンツビジネスも「世界標準」に変える必要があるでしょう。
アミイゴさん:アニメの業界では、業務内容が契約できちんと規定されていないために、アニメーターが低報酬・長時間労働を強いられるといった問題も起きています。こうした状況では優れたクリエイターは育たないでしょうし、その結果、日本の作品に対する国際的な評価が低下し、クールジャパンを支えるコンテンツ産業全体が地盤沈下しかねません。各業界がそれぞれの特性などを踏まえた上でひな形を活用し、きちんとした契約を結ぶことで国際競争力を高めてもらいたいです。

フリーランスの集まる場を提供 組織化しエンパワーメント
-フリーランスの待遇改善や地位向上に向けて、連合や労働組合にどのようなことを期待しますか。
菅弁護士:フリーランスが1人でクライアントと契約について交渉するのは、仕事を失うリスクもあり勇気が必要です。しかし仲間が集まって情報交換することで賢く交渉することは可能です。さらに、海外では俳優やVTuber(バーチャルな姿で活躍するYou Tuber)などが労働組合を作り、団体交渉を通じて労働協約を締結する例も見られます。連合には海外事例も参考にしながら、業種別にフリーランスを組織化し、当事者のエンパワーメントや政策提言を行ってほしいと考えています。
他方、日本ではフードデリバリーの配達員や軽貨物ドライバーなど、本来なら労働者とされるべき人が多数、フリーランスとして扱われています。こうした人たちも労働運動に巻き込み、労働法や社会保障を適用していくための取り組みを進めてほしいと思います。
アミイゴさん:Wor-Qアドバイザリーボードやフリーランスサミットを通じて、異業種のフリーランスと交流して、交渉の好事例や報酬の相場観といった情報を得られたことは、個人的に非常に大きな財産になりました。連合には引き続き、当事者に業種を越えて情報交換できる場を提供してもらいたいと思います。
クリエイターは、「好き」を仕事にしているから苦労が少ない、と思われがちですが、実はものづくりの最底辺に位置し、搾取される側に立っています。連合には、クリエイターが適切な就業環境や報酬を確保することの重要性を、社会に発信する役割も果たしてほしいと願っています。
(執筆:有馬知子)