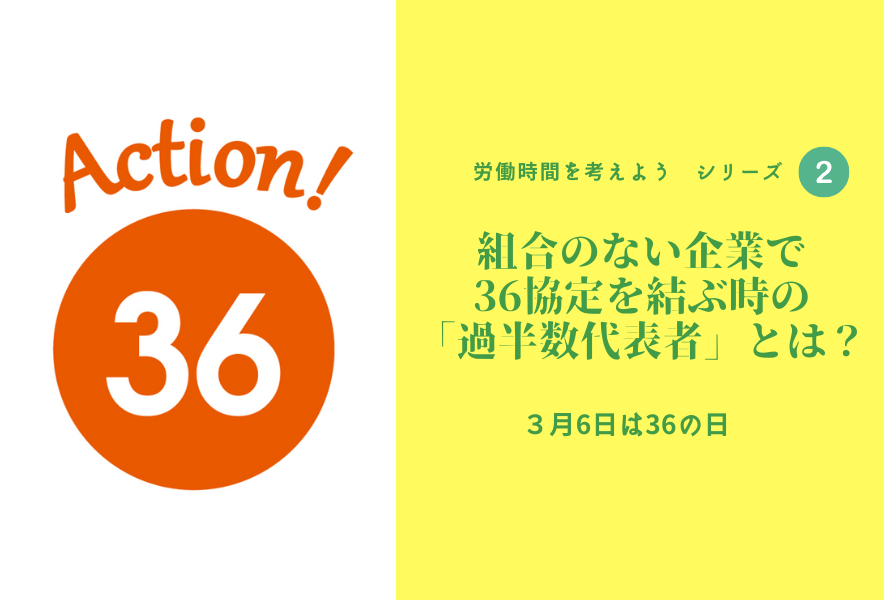3月6日の「サブロクの日」に向けて、職場の労働時間に関する取り決め「36協定」について考えるシリーズ。2回目は成蹊大の原 昌登教授(労働法)に、労働組合のない職場で36協定を結ぶ際に選ばれる「過半数代表者」について聞いた。過半数代表者はどのように決まり、どのような役割を担うのか、あなたは知っていますか?

原昌登(はら まさと) 成蹊大学法学部教授
東北大学法学部卒業。専門は労働法。
東北大学助手、成蹊大学法学部専任講師、助(准)教授を経て2013年に教授。
労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)委員、中央労働委員会地方調整委員、厚生労働省ハラスメント対策企画委員会委員、東京都カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会委員、労働基準監督官採用試験専門委員などを務める。
労働法に関する講演、研修等の講師も多数経験。著書に『ゼロから学ぶ労働法』(経営書院)、『コンパクト労働法(第2版)』(新世社)、『事例演習労働法(第4版)』(共著、有斐閣)など。
残業は最小限に留める 36協定は「例外」的な措置
―36協定はどのようなものですか。
まず大前提として心に留めていただきたいのが、労働時間は1日に8時間以内で週40時間以内、休日は少なくとも週1日か4週に4日と定められており、これを超える時間外・休日労働は原則的に違法だという事実です。36協定はこのルールを超えて労働者を働かせる必要がある時、例外的に時間外労働を認める仕組みです。決して労働者を上限ぎりぎりまで『働かせていい』制度ではなく、残業は最小限に留めるべきだというのが法律の趣旨です。
―2019年に労働基準法が改正され、時間外・休日労働について複数月にまたがる時は平均で月80時間、単月では100時間という上限が定められ、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則も設けられました。上限と罰則が設けられたことの意義は何でしょうか。
法律の上限を超えて労働者を働かせた場合、職場の管理者と事業主の企業が責任を問われる恐れがあります。罰則だけ見れば軽いと感じるかもしれませんが、刑罰があるほど重い違法行為だ、という事実を企業に認識させるという点で、大きな意義があります。「割増賃金さえ支払えばいくら残業させてもいい」と考える経営者もいるでしょうが、その理屈は通用しないという強いメッセージにもなります。
さらに、時間外労働をさせたうえ、残業代も支払わないといった非常に悪質な場合、付加金として未払いの割増賃金にそれと同額の支払いを上乗せされる「倍返し」が生じます。また時間外労働が36協定の範囲内であっても、労働者の心身の健康が損なわれた場合は安全配慮義務違反となり、経営者は責任を問われる可能性もあります。
経営者が職場の過半数代表者を「指名」するケースも選出プロセスを具体的に示す
―現在は、労働組合のない職場が多数を占めます。こうした場合、労使で協定を結ぶにはどうすればいいのでしょうか。
労働者の過半数が加入する労働組合のない職場で36協定を結ぶ場合、職場の労働者の過半数を代表する「過半数代表者」を選出して、協定を結びます。代表者はパートやアルバイトなどを含めた、すべての労働者の挙手や投票などで決まり、経営側が指名することはできません。最高裁の判例では、全労働者が参加する親睦会の会長が署名していた労使協定も、無効と判断されました。つまり、たとえ周囲から信頼を得ていて代表者として適任であったとしても、正しい選出プロセスを踏まなければ代表者にはなれないのです。
―実際に個々の職場では、どのような形で過半数代表が選ばれているのでしょう。
残念ながら実態としては、経営者などが過半数代表者の候補者を決めていることもしばしばです。候補者がメールなどで通知され、反対意見が出なければ賛成とみなすといった方法が取られることも多く、選出プロセスが適切に機能しているとは言い難い面もあります。こうした状況では過半数代表制に対する理解も進まず、自分の職場の過半数代表者が誰かが分からない労働者も少なくありません。
ただ適正な選出方法についての情報がないと、どのように候補者を告知し、どのくらいの投票期間を設けるべきかが分からない、となってしまう職場が多いことも事実です。ですから、例えばスーパーなら「控室にチラシを貼って候補者を示し、意見を送りたい場合の連絡先も添える」など、業種や企業規模に応じたガイドラインを作るなどして、具体的なやり方を職場に伝える必要があると思います。
個人が会社と協議するのは至難の業 締結プロセス全体の見直しも検討を
―もし自分が過半数代表者に選ばれても、会社と協議できるほどの知識も経験もなく、できるとは思えないのですが…。
ほとんどの労働者はそうだと思います。正直に言えば、労働者がたった1人で、仕事をしながら過半数代表者の役割を果たすことは、極めて難しいと感じています。
過半数代表者は、月ごとの労働時間を把握し経営側の提案を理解した上で、なるべく長時間労働を抑制する方向で交渉を進めるのが本来の姿です。しかし交渉ノウハウと経験のある労働組合が集団で取り組んでも難しいことを、従業員1人に担わせることにそもそも無理があります。現状では、過半数代表者をサポートする仕組みもほとんどありません。この結果、大半は経営側が提示する協定書にサインするだけになってしまっています。36協定は毎年更新する必要がありますが、過半数代表者が前年の協定を追認するだけでは、経営状況の変化などに応じて内容を見直すこともできません。
―どうすれば制度が有効に機能するようになるのでしょうか。
職場に過半数に満たない労働組合があるなら、その役員やメンバーが立候補して、過半数代表者を担う形が望ましいでしょう。組合役員なら、労働法や職場の実態を把握しているでしょうし、他のメンバーと協力して交渉を進めることも可能です。
制度的な課題もあります。過半数代表者は協定締結の時だけ選ばれる形になるので、行政や労働組合が選出された人に必要な情報やサポートを提供するのが難しく、協定締結後、経営者が内容をきちんと守っているかどうかをチェックすることもできません。任期制の導入の検討や、過半数代表者に対する継続的な教育が重要だと思います。ただそれでも個人に任せるだけでは根本的に限界があるため、協定締結プロセス全体の見直しも検討すべきでしょう。

適切な協定締結は経営側にもメリット 消費者も「変化」の受入れが必要
―36協定が適切に結ばれることによって、労使にはどのようなメリットがありますか。
時間外労働を適切な範囲に収め、休息時間を確保できれば、労働者がリフレッシュして前向きに働けるようになります。また協定締結の際に労使で働き方を考えることは、経営側に長時間労働で利益を生む労働集約型モデルから、付加価値創出型モデルへの転換を促すきっかけにもなり得ます。そうなれば労働者の環境改善ややりがいの向上につながるだけでなく、経営側も生産性の向上や企業の成長が期待できます。
昨今は、ESG投資や人的資本経営の考え方が浸透し、法令順守に対する社会の目は厳しくなっています。36協定に反するような長時間労働が明らかになれば、経営側には投資家だけでなく取引先やユーザーなど、あらゆるステークホルダーからの批判も免れません。若い世代は残業や休日労働を避ける傾向も強く、採用面にもマイナスの影響が出るでしょう。協定を「守らない」ことのリスクも、非常に高いと言えます。
―長時間労働の問題を解消するため、社会にできることは何でしょうか。
経営者はネガティブな情報を出したくないと考えるので、情報開示を進めることが職場環境の改善を促す圧力になり得ます。2024年には次世代育成支援対策推進法が改正され、フルタイム労働者の時間外・休日の労働時間を把握し、目標を設定・開示することが一定規模以上の企業に義務付けられました。こうした情報開示を進めることが一つの策だと思います。
また、これまで製造業や建設業などの現場は、人手不足の中、長時間労働によって何とか納期を守ってきました。発注企業が下請けに無理な納期を押し付け、犠牲を強いるのはもうやめるべきです。そして、私たち消費者も「我慢」を学び、例えば荷物の配達期間が多少延びるといった変化を受け入れなければいけません。
連合は「プッシュ型」で情報提供を 組織化への流れを作る
―長時間労働をなくすためには、適切な36協定を締結して、それを守らせること必要ですが、労働組合に求めることはありますか。
連合には、労働者からの相談を待つのではなく、「プッシュ型」で労働組合のない中小企業の職場を含めてアプローチし、36協定に関して必要なサポートを提供してほしいです。
また協定を締結する過程で、職場に「過半数代表者が1人で交渉を担うのは荷が重い」という認識が生まれ、何人かのキーパーソンが集まって労働組合を作るという動きが起きれば理想的です。そのためには連合や労働組合が普段から、職場に労働組合があることのメリットを発信し、「労働組合は労働者にとって活用できるツールだ」という理解を深めておくことが大事です。もちろん、組合結成に向けて動き出した職場にもサポートの手を差し伸べ、組織化への流れを作ってほしいと考えています。
(執筆:有馬 知子)
第1回目の記事はこちら↓