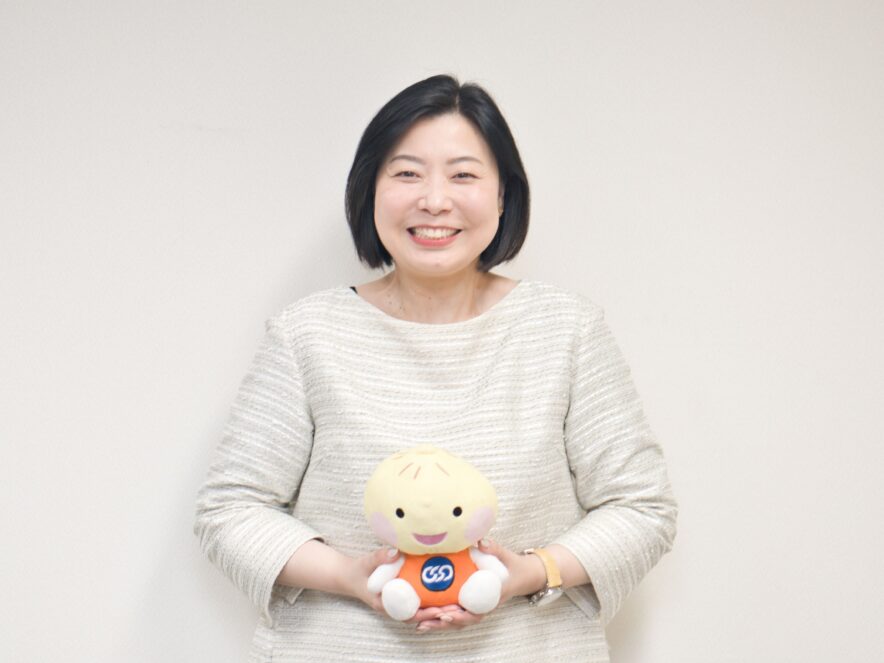シリーズ第17回は、大方幹子連合副会長にインタビュー。NTT労働組合の大阪総支部、西日本本部で経験を積み、中央本部を経て、2021年から情報労連で活躍中。「みんなでやろう!」という組織活動が大好きなのに、休日は「おうち大好き人間」のインドア派。表情豊かなリーダーの素顔に迫ります。

大方 幹子(おおかた みきこ) 連合副会長・情報労連副書記長
1998年日本電信電話(現・西日本電信電話)株式会社[NTT]入社。2002年NTT労働組合大阪総支部の執行委員に就任。以降、NTT労働組合にて、西日本本部執行委員(2010年)、中央本部執行委員(2015年)、コミュニケーションズ本部組織部長(2019年)を歴任。
2021年情報労連(情報産業労働組合連合会)組織連帯局長に就任し、2023年より情報労連副書記長、連合副会長を務める。
こんな世界もあったのか!
—労働運動を始めたきっかけは?
1998年、大学を卒業してNTT(日本電信電話株式会社)に入社しました。翌年、持株体制移行に伴い、NTTは、東日本、西日本、コミュニケーションズに分社化され、私はNTT西日本の所属となりました。仕事は法人営業部の営業職で、大阪の「キタ」と呼ばれる梅田界隈を毎日自転車で回っていました。
労働組合は、入社した年の暮れに「全電通」から「NTT労働組合」に名称変更。オープンショップ制ですが、自然な流れで組合員になり、分会役員も引き受けました。女性が少ない職場だったので、分会長から「ぜひ女性に役員になってほしい」と説得されたんです。でも、会議に出たり、レクリエーションの手伝いをしたりするくらいで、本格的な組合活動には関わっていませんでした。
入社3年が過ぎた頃、「このままでいいのか」と考えるように…。法人営業は、顧客がほぼ決まっていてルーティンの仕事が多かったんです。先輩に相談すると「せっかく入った会社だから、続けるために何か道はないか考えてみたら」とアドバイスされ、「大阪総支部で女性役員を探しているからやってみないか」と声をかけていただいたんです。
2002年大阪総支部に行ってみたら、「こんな世界もあったんだ!」と驚きました。営業以外の部門や職種の組合員と話をすることができて、企業を超えた産別(情報労連)のつきあいや、UNIグローバルユニオンなどの国際労働運動の関わりもある。人との関係も、世界観も、格段に広がりました。そこが、私のスタートです。

自立・自活を支援する国際ボランティア
—思い出に残る活動は?
総支部では、広報、組織、総務などの仕事を一通り経験しました。
忘れられないのは、NPOと連携した国際ボランティア活動として取り組んだフィリピンの「子豚銀行」プロジェクトです。NTT労組は、全電通の時代から社会貢献活動に力を入れていましたが、目的は「国際的な視野を広げ、問題意識の持てる組合員づくりやリーダー育成」という組織強化。総支部委員長は、資金提供だけでなく、組合員や組合役員が、直接現地の活動に関わることを重視していました。
私自身も、ホームステイをしながら運営に参加しました。飼育するための水を確保するために、村人と一緒に石鎚でコンコン竪穴を掘って90メートル下の水脈に行き着いた時は本当に嬉しかった。貸付で購入した子豚が生活を継続的に支える存在になり、村が変わっていく姿に感動しました。職場にいた頃は想像もできなかった経験ができて、労働組合ってすごいなと思いました。
平和行動も担当しました。先輩から「『平和なくして労働運動なし』。働くという視点も大事だけど、働くことの根底にあるのは平和。絶対におろそかにしてはいけない。なぜ労働組合が平和行動や社会貢献に取り組むのか、組合員一人ひとりに理解してもらえるように活動するのが組合役員の役割だ」と叩き込まれました。
労使交渉は避けては通れない道
—その後、2010年に西日本本部へ。
もっと組合活動を続けたいと西日本本部へ。そこで初めて労使交渉を担当することになりました。総支部時代は主に組合員と関わる組織畑を歩み、「みんなでやろう!」という運動を得意としていました。でも、労使交渉は避けては通れない道。「苦手なんて言ってたらキャリア積まれへんぞ」と言われて、ぐうの音も出ず、先輩方のアドバイスを支えに交渉に臨みました。
この頃は、情報通信産業の競争環境が激化しており、会社も大きな処遇制度の見直しを行うなど、交渉はとても大変なイメージがありました。実際、大阪総支部時代に組合員説明会へ行くとベテランの組合員からは「お前みたいなひよっこじゃ話にならん」とよく詰められました。そんな経験もしていたので、労使交渉の担当は本当に不安でしたが、厳しい経営状況だからこそ労使が共に反転姿勢に向けて「良好な労使関係を築き、正確な情報を得て、そこに労働組合の意見をできる限り反映させていく」ことの大切さを学びました。

後ろに続く女性役員の育成にも
—そして、2015年に東京のNTT労組中央本部へ。
中央本部役員は、専従職であり相応のスキルや経験が求められます。「自信がない」と一度はお断りしたんですが、委員長が「中央本部に行くことは、自身のキャリアアップにつながるだけでなく、後ろに続く女性役員の育成にもつながる」と背中を押され、大阪を離れ、上京しました。
最初に担当したのは、やはり労使交渉。中央本部の交渉事項は、NTT労組のすべての組合員に関わることなので、すごく緊張感がありました。先輩からも厳しく鍛えていただきました。
4年後にNTTコミュニケーションズ本部(現在はドコモ本部と統合)に組織局長として派遣されました。すべての分会を回ろうと意気込んでいたら、新型コロナのパンデミックが起きた。職場は在宅勤務となって分会事務所から人影が消え、会議はオンライン。思うように動けず心残りもありますが、大事なことも学びました。
西本部は、組合員との対面コミュニケーションを重視し、対話に対話を重ねて理解を得る文化。それに対してコミュニケーションズ本部はドライでシステマチック。組合の提案に対し「その根拠は?」「背景となるデータは?」と論理的に説明を求めてくる。労働組合の仕事って論理的に解決できないことも多いし、労使交渉も互いに譲歩しつつ歩み寄ることが求められますが、その結果について組合員の理解を得るには、根拠を示すことも大事だと理解しました。

2018年UNI-LCJモンゴルセミナーにて
—そして、情報労連へ。
情報労連には、他社の労働組合の組合員もいて、情報通信産業含めた様々な業種全体を見なくてはいけない。連合を通じて他の構成組織との関わりも増え、さらに世界が広がりました。
最初の2年は、組織連帯局長として、社会貢献活動、平和行動、政治活動を担当し、昨年、副書記長に就任しました。
情報労連には「女性役員3割」という参画目標はありますが、私自身は、「女性だから役員になってほしい」と言われるより、「あなたに役員になってほしい」と言われたい。でも、ジェンダー平等をすすめる上では、「女性枠」と言われるクオータ制が必要な局面もあると思っています。
NTT労組の前身である全電通は、女性が働き続けるための条件整備に取り組み、法制化される前に育児休業などの制度を協約化してきた歴史を持っています。ただ、私が入社した頃には、改正均等法が施行され、制度上男女の格差を感じることは少なくなっていました。
でも、情報労連に来て、改めて「いまなお男女間の賃金格差がある」という事実に目を向けなければと思っています。背景には、女性管理職が少ないこと、女性は派遣や契約社員などの非正規雇用が多いといった要因があります。
この問題を解決するには、やはり労働組合が動かなくてはいけない。
そして、そのためには、労働組合におけるジェンダー平等を進めることが重要です。
かつての労働組合はタバコルームや夜の飲み会で大事な話が決まっていく「男社会」でした。そこは変わりつつありますが、働き方は変わっていない。私も「365日24時間、何かあればすぐに駆けつけるのが組合役員だ」と言われてきましたが、その働き方に対応できる人は限られる。女性だろうと男性だろうと、子育てや介護しながら、労働組合の役員を務めるのは厳しく、役員の担い手の幅を組合自身が狭めてしまうことになる。そこはもっと踏み込んでいきたいと思っています。
快適な睡眠でリフレッシュ
—趣味、休日の過ごし方は?
趣味がないのが悩みで、友人に誘われてあれこれチャレンジするけど続きません。
平日は仕事で遅くなることが多いので、休日は良質な睡眠で心身をメンテナンスすることを優先しています。快適に眠り、快適に目覚めるための「睡眠グッズ」にもこだわっているのですが、いまだ理想の枕にめぐりあえない「枕難民」(笑)。
ずっとがむしゃらに走り続けてきましたが、今の立場になって、ONとOFFの切り替えが大事だと気づきました。だからOFFは一歩も外に出たくない「おうち大好き人間」を満喫しています。

—好きな映画・ドラマは?
複雑なストーリーは疲れてしまうので、アクション系や一話完結ドラマを流しながら寝落ちのパターンです。
—尊敬している人は?
労働組合で出会った先輩たちは、みんなバイタリティがあって素敵な人たちが多いですが、尊敬する人を1人あげるとすれば、姉でしょうか。人と関わるのが大好きな「大阪のおばちゃん」で、どこへ行ってもガンガン喋って友だちをつくっちゃう。私は、逆に決まった友だちに安心感を覚えるタイプ。真逆のキャラの姉が、刺激にも、支えにもなってくれています。父の仕事の関係で海外生活が長かったのですが、姉の存在が大きいのは、海外での暮らしを家族で支え合ってきたおかげかもしれません。
—座右の銘は?
関西弁では「やってみなわからん」と言われますが、振り返った時、自分には力不足だと思っても、断らないでやってみたら新しい世界が拓けた。「何事もまずはやってみることが大事」だと肝に銘じています。
—これなら誰にも負けないと思うことは?
「右から左に流すスキル」です。100%受け止め、自力で解決しようとするとパンクします。だから、「これは流してはいけなかったんだ!」という痛恨のミスを繰り返しながら、どう受けとめるかを見極める力を身につけました。
—ご自分を動物に例えると。
猪突猛進なところもありつつ、のんびりしすぎてるところもあるので、愛らしい「カバ」でしょうか。
—連合の副会長として感じることは?
その役割を果たせているのかという思いはありますが、三役会では、トップリーダーの視点や考え方に直接触れることができて、刺激を受けています。
複数の女性副会長の存在も心強く、女性リーダーとして社会や労働界で自分が取り組むべき課題はこんなにたくさんあるんだと実感する日々です。