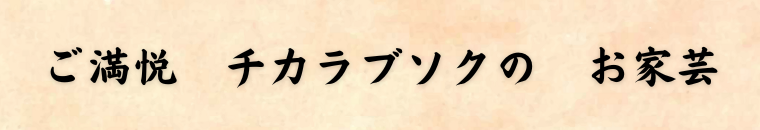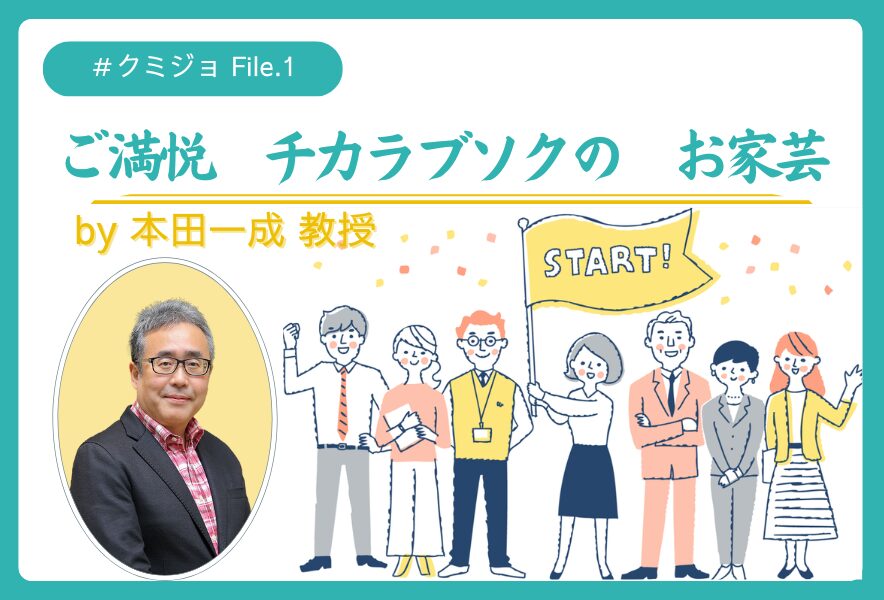連合は2024年10月、「203050(2030年に女性参画50%)」を最終目標とする「ジェンダー平等推進計画」フェーズ2をスタートさせた。フェーズ1では、5つの目標のうち「女性役員を選出」した構成組織は3分の2にとどまり、さらなる取り組み強化が求められているという現状にある。
なぜ、労働組合のジェンダー平等参画は思うように進まないのか。
30年以上労組と付き合い、150人超のクミジョ※1にインタビューしてきた本田一成 武庫川女子大学経営学部教授は、「クミジョとクミダンが見事にすれ違っている」と指摘する。そこで、これまでの研究や交流をもとに、「本音を語りたくても語れない」と思い悩むクミジョと「クミジョが増えない」と困惑するクミダンの間をつなぐメッセンジャーとして、本田先生に一肌脱いでいただくことにした。真のパートナーシップを築くのは、今しかない!(連載6回)
- クミジョ:労働界でがんばる女性(労働組合や関係団体の役員、職員、組織内議員など)の総称 ↩︎
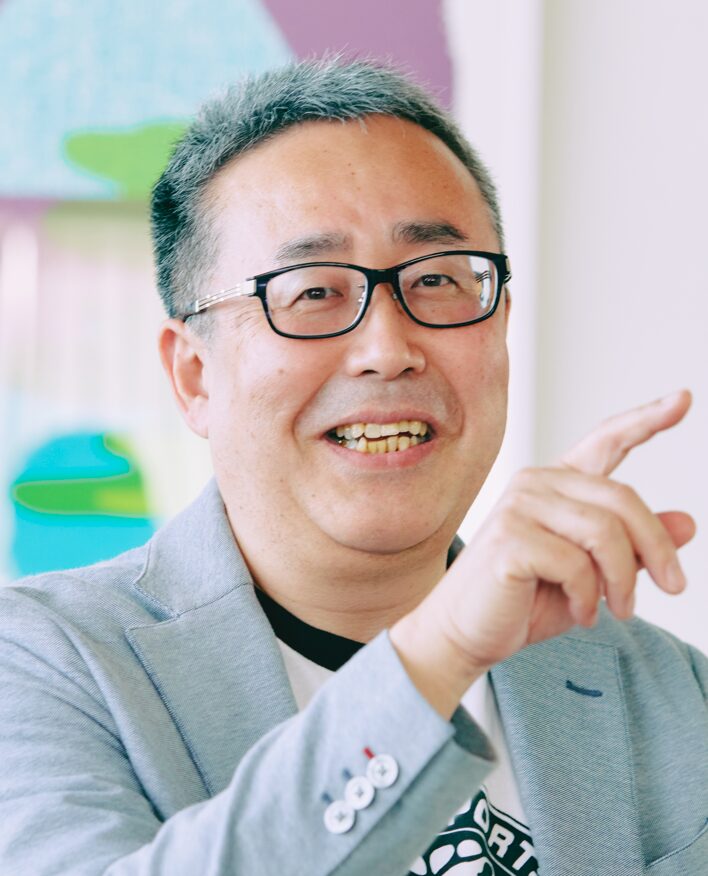
本田 一成(ほんだ かずなり)
武庫川女子大学経営学部教授 K2P2共同代表
専攻は労使関係論、人的資源管理論、専門領域はサービス産業の労働問題。博士(経営学)。大学教員のかたわら、JP 労組クミジョ応援係長(2023年委嘱)、K2P2 共同代表(クミジョ・クミダン パートナーシッププロジェクト、j.union 社との産学協同事業)に就任。現在 150 人超のクミジョに対するインタビューを継続中。
労組の衰退とクミジョの苦悩は関係ない?
私は武庫川女子大学に勤務するかたわらで、K2P2(クミジョ・クミダン パートナーシップ プロジェクト®)の共同代表を務めている(JP労組からはJPクミジョ応援係長に任命されている)。
「クミジョって何なの?」と聞かれることがあるが、労働界でがんばる女性(労働組合や関係団体の役員、職員、組織内議員など)の総称で、私の造語である。男性はクミダン。「どうしてあえてK2P2をつくったの?」とも聞かれる。そう、「あえて」のためにつくったのである。
クミジョとクミダンはとっても仲良しだ(仲の悪い人たちもいる)。ニコニコして、ともにがんばりましょう、な関係である。人類が発明した労組は素晴らしい。労働者を救う確かな力をもっている。
20代の頃から30年以上労組とお付き合いしてきた。だから、その衰えをつぶさに見てきた。一方、現在ほどではないが、クミジョとも交流してきた。クミジョと差し向かうと、ニコニコしていなかった。いつも労組やクミダンに関する悩みや不満だらけであった。仕事だから仲良くしているだけで、本当はそうでもない?労組の衰退とクミジョの苦悩や不満は関係ない?
ずっと気になっていたので、「ヤミ研」を止め、嫌われ役になってもよいから、お世話になったご恩返しのつもりで労働界に貢献したい、と思い立った。手始めに連合栃木の協力を得て『とちぎクミジョ白書』を発行したのが2020年。
同時に、リアルな話を聞こうと「クミジョインタビュー100」を開始し、コロナ禍に邪魔されたが継続中である。それが150人超となった現在でも新しい発見が多いから、研究途上なのであろう。未完成なのに予想外に講演、対談、座談会、取材などの依頼が多いので驚く。
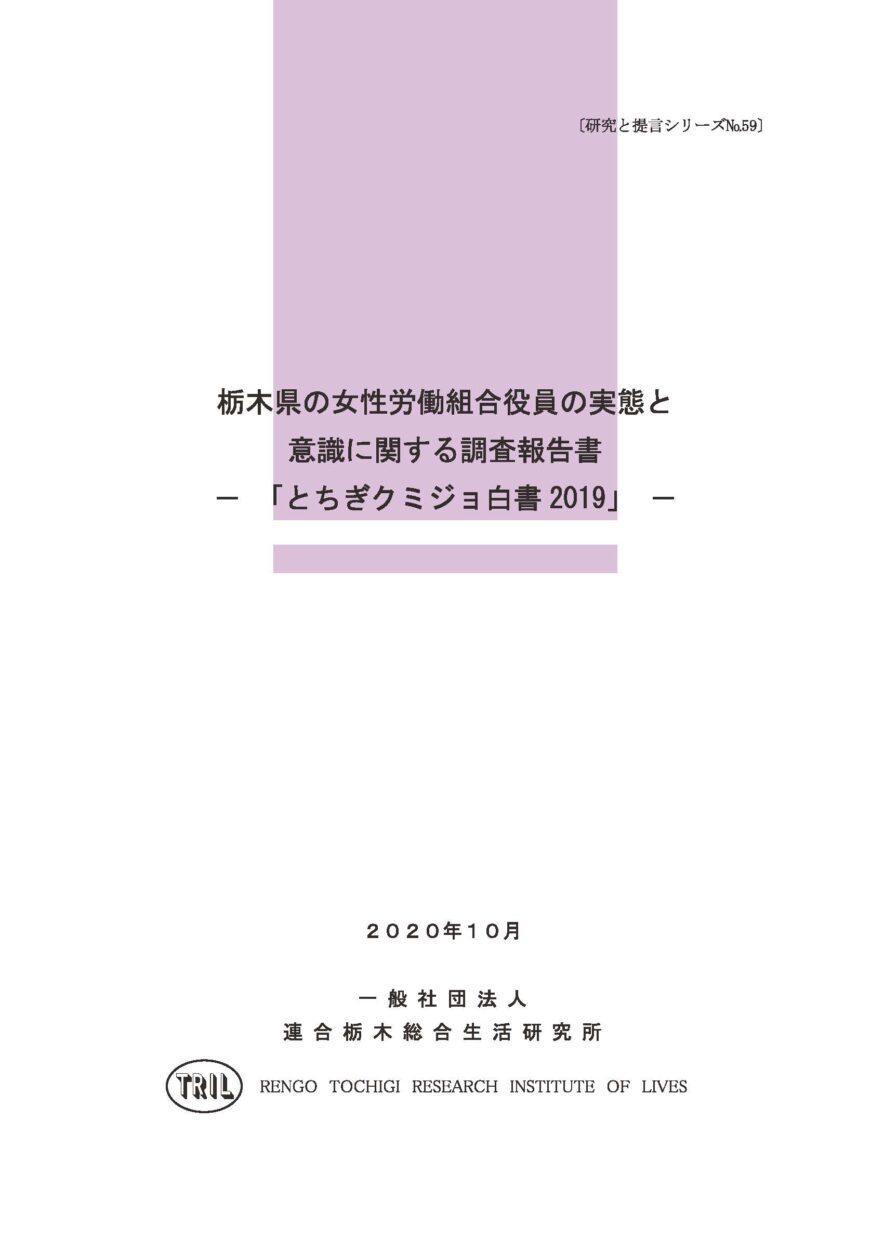
両者は見事にすれ違っている!
労働界はこの問題をタブー視しているわけではないようである(軽視、無視する人はいる)。しかし、やっかいなのは、日本というジェンダーギャップ最劣悪国の労組なのに、もう男性も女性もない、わざわざ区別するな、女性優遇をやめろ、という声が案外に強く、フタをされがちで研究がやりにくいことだ。クミジョという愛称すらも「見えぬ化」ねらいの「言葉狩り」の犠牲になりかねない。
労組は労使交渉、組織拡大、政策、政治、平和行動などいわば対外活動ばかりが語られがちだが、足元の組織内部のことも大切である。クミジョ・クミダン問題を研究しているうちに、両者は見事にすれ違っていることに気づいた。それを不問にして、当人たちが同じ目標に向かっているというのなら、労組は「演劇部」になってしまう。絶対に避けて欲しい。
人間は、同じ組織に所属していたり、すぐ近くや目の前にいたりする人、上下関係の中では、本当に言いたいことは言わない。言えない。だが、聞く耳をもつ第三者になら、語ることができる。あえてメッセンジャーになりたくて、K2P2を立ち上げたのである。
私が力不足なのかな?
クミジョと話していると、「私も力不足なんですが…」と言う言葉を何度も聞く。謙遜しているようでもない場合がある。一方で、飲み屋でクミジョを「力不足」と評するクミダンはとても多い(本人には言えないらしい)。
実は、この言葉はマネジメントの世界ではご法度である。個人のせいにして、組織の問題としないのなら、組織マネジメントは不要になる。マネジメントしなくてよいから楽だし、のうのうと逃げられる。
クミジョが増えないのは誰の責任だろうか。クミジョに問題があるのか、それとも増やせないほどウチはダメな組織なのか? そう考えられるかどうかが最初の関門である。クミジョ側に原因があるという神話では、「やりたがらない」「全力でやってくれない」「すぐ帰る」「知識や経験がない」「文句が多い」といくらでも力不足につなげられる。その先には、クミジョを増やすのは悪平等だ、クオータ制は男性差別だ、と広言するクミダンがいる(25%目標だと誤解しているクミダンもいる)。
クミジョが増えないのはクミジョの力不足が原因というのが本当なら、では増やすために組織はどうすべきか?へと進む。あるいは、それがウソなら、本当の原因は他にあるはずだが?と探す。これらはマネジメントの常識である。
一方で、クミジョのせいばかりにできないぞ、と感じるクミダンもいる。家族責任などで時間制約が全然違う点にはすぐに気づく(妻が専業主婦のクミダンは気づくのが遅い)。クミジョが変わらないからダメだ、早く俺たちに追いつけ、と繰り返すのには無理がある。普段から、労組も変えていかねば、と言っているから、辻褄が合わないな、と気づく。
それなのに、やっぱり女性じゃ無理だ、と決めつけていなかったか(女性のくせに、女性にしては、女性にしとくのはもったない、なども気をつけて)。力不足だ、と言いたくなる気持ちがわからないでもない。だが、もう少しだけ固定観念から離れて、クミダンはそう考えるがクミジョはそうは考えない、という「すれ違い」はどうするのか。


「女性がすーっといなくなる」組織
労組がマネジメントを必要とするのか、それとも、労組にそんなものは不要なのか、というところまで行きつく重大な話だと思う。労組の動かし方を知っているのと、マネジメントを理解しているのは別である。労組は見た目以上にタテ型組織だから、とりあえず動いてくれる。だが、リーダーは他人まかせではなく、意識的に部下たちが、働きがいをもって、安全に働けるようにしているのか。中央やトップはよいけれど現場に近づくとどうなるか。その逆も問える。
兵庫県豊岡市の「女性がすーっといなくなる」話をご存じだろうか(本も出版されテレビ報道も多い)。男性が当たり前のように行動していたら、とっくに女性に見切られていた。しかし、当時の中貝宗治市長は、いち早くその原因が深刻なジェンダーバイアスにあることを喝破し、対策を講じて巻き返した。
地方の市町の問題と片づけてよいのだろうか。クミジョが力不足なのではなく、あなたの労組は「女性がすーっといなくなる」組織になっているのに気づいていないだけではないのか。誰が悪いのかを決めつけ、責任を問うということよりも、組織というものは、自分たちに問題がある、とはなかなか言えない、と自覚するのが先決である。
だから、私はクミジョの立場の気持ち、苦労、希望などを伝えたい(個人情報に留意し、一部構成を変えるが、リアルな内容である)。ただし、メッセンジャーは、決して甘くない。クミジョが教えてくれることの裏にある、教えてくれないことも掘り出す。私の体験も交える。
クミジョのことはよくわかっているよ、とうそぶくクミダンは多い。だが「オレは芳野会長を知っている」のとは全く違う。100人以上のクミジョの話を聞いたのだろうか(私は芳野会長にインタビューしたことはない)。ピカピカの役職者でなくても黙々とがんばっているクミジョはどうか。サラ・クーパー『男性の繊細で気高くやさしい「お気持ち」を傷つけずに女性がひっそりと成功する方法』を読むクミジョはどうか。他組織も含め本当にクミジョを知っているのだろうか。
この連載では、耳に入れたくないこと、受け入れ難いことなどに出くわすと思う。だが、研究を続けていて、良いクミダン、マシなクミダン、スジがよいクミダンたちがいることを知った。クミジョと正真正銘のパートナーシップを築こうとする素晴らしいクミダンも。クミジョだけでなく、決してクミジョが話さない話を聞きたいクミダンの参考情報になれば幸いである。それでは、クミジョを主役にして、リアルなクミジョとクミダンの姿をコマ送りでお届けしていこう(川柳はおまけ)。