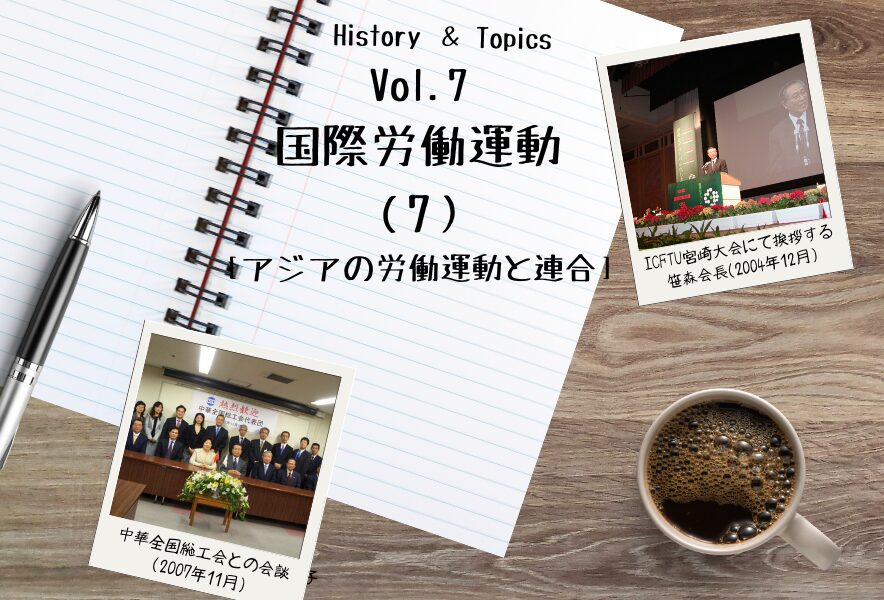日本の労働組合は、半世紀以上も前から、アジア地域の労働運動の発展に力を注いできた。例えば1960年に結成された「TWARO」(通称:アジア繊維/国際繊維被服皮革労組同盟(ITGLWF)の地域組織)は、全繊同盟(現・UAゼンセン)がその中心的組織として資源を投入してアジア地域の労働者の労働条件改善や組織化に取り組み、グローバルに活躍するユニオンリーダーを輩出してきた。そうした伝統を受け継いだ連合も、アジア地域の労働運動を重視し、ICFTU(国際自由労連)やITUC(国際労働組合総連合)のアジア・太平洋地域組織の会長や書記長という責任あるポストを引き受けてきた。そして、時にはアジアの現状をよく理解する立場から、国際労働運動の方針に対して物言う「アジアの代弁者」の役割も果たしてきた。 アジアの労働運動における連合のリーダーシップと貢献は、アジアの労働組合からも高く評価されているが、それを印象付けた出来事について、生澤千裕日本ILO協議会理事の話を聞こう。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)
日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー
1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。
「アジアの労働運動を救った」笹森清連合会長

ICFTUが宮崎で世界大会を開催「連帯のグローバル化」をめざす(「月刊連合」2005年1月号)
2004年12月5日から6日間、宮崎市でICFTU第18回世界大会が開催された。世界大会は、4年に1度、各地域の持ち回りで開催されることになっていたが、宮崎大会はアジア地域で初の開催。連合は、ホストユニオンの重責を果たすため、大会準備室を設置し、各局からスタッフを集めて万全の体制で準備にあたった。
大会には、世界150カ国から約1000名、国内から約400名のユニオン・リーダーが参加。「連帯のグローバル化—未来に向けたグローバル・ユニオン運動の構築」をスローガンに多国籍企業への対応や組織強化、WCL(国際労連)との統一などに関する議案が討議され、成功裏に幕を閉じた。しかし、その前段で、ICFTU本部が宮崎大会に向けて提起したある議案をめぐって、連合の笹森清会長が「宮崎大会の開催を返上する」とまで発言する事態が起きていたという。
「連帯のグローバル化を実現するためには
地域の自主性、独自性が尊重されなければならない」
これは、宮崎大会直前に執筆された笹森会長のコラム(「笹森会長の“行動系”で突っ走ろう」月刊連合2004年12月号)の見出しである。本文には、ICFTU本部の地域組織活動の見直し提案について「おおいなる異議がある」とし、「地域組織の地域事情や独自性を認めず、中央集権を志向する、その『組織改革』の方向性は、とても賛同できるものではない。APROの執行委員会は、この問題をめぐって本部書記長との間で大激論となった」と報告し、宮崎大会では、「APRO執行委員会の総意として、地域組織の自主性尊重を求める『連帯のグローバル化に関する決議』を提出し、各論については検討項目扱いすることなど、大会テーマ文書の修正を求める提案を『笹森提案』として提出することを決めている」と記されている。
いったい何があったのか。生澤さんの説明を聞こう。
2004年9月、第18回世界大会に向けて、ICFTU本部のガイ・ライダー書記長(後のILO事務局長)は、大会提出議案資料を各加盟組織に配布しましたが、そこに「地域大会を廃止し、地域大会で選出する地域組織書記長は地域執行委員会が推薦し本部執行委員会が承認する」という提案が入っていたんです。
事実上の地域組織取り潰しです。ICFTU-APROの鈴木則之書記長(当時)にとっても寝耳に水の提案。APROは、10月にニューデリー(インド)で開催した執行委員会で、「提案は容認できない」と否決するのですが、その席上で、ガイ・ライダー書記長に対し、強く撤回を迫ったのは、連合の笹森会長でした。
「現場の実態や自主性を尊重しない運動は成功しない」と訴え、「このような提案がなされるのであれば、連合は世界大会の宮崎への招致を返上する」と言い切った。
開催まで2カ月を切ったタイミングでの「返上」発言のインパクトは絶大でした。
連合はICFTUの中で3番目に大きい組織であり、人的にも財政的にも活動領域の豊富さにおいても、アジア地域のリーダー的組織。ICFTU本部も、その連合のトップの言葉はないがしろにはできません。
詳しいことはわかりませんが、おそらく笹森会長自身が「これは、宮崎大会を返上してでも、アジア地域組織を守らなければいけない」と判断して、APRO執行委員会に乗り込んだのだと思います。APROも強い危機感を持っていたものの、鈴木則之書記長も主要組織のリーダーも、本部提案を覆すのは難しいと半ば諦めていた。ところが、笹森会長は、ニューデリーの空港に到着すると、開口一番「鈴木さん、この本部直轄方針は撤回させよう」と…。卓越したリーダーって、理想と現実と現場を見て、どう行動すべきかを的確に判断できるのだと感服しました。
最終的には、宮崎の世界大会開催後にICFTU執行委員会が「大会ほか、現行規約の構造は維持する」との修正を提案することで決着し、APRO執行委員会の決議を本部執行委員会が受け入れた形となりました。
連合の事務局長4年、会長4年を務めた笹森清氏は、会長就任時、連合のスローガンを「力と政策」から「力と行動」に変え、連合評価委員会を設置した。頭の回転が速くて判断力も行動力もあり、演説ではその思いが言葉になって溢れ出た。現場を大事にして運動を進めることの重要性を深く理解していた素晴らしい指導者のなせる技であったと思います。
『アジア太平洋の労働運動—連帯と前進の記録』(明石書店)にこの経緯を詳細に記した鈴木則之元APRO書記長からは、この時のことを称して、「笹森氏はアジアの労働運動を救った、と多くのアジアの同志から言われた」という話を聞いています。

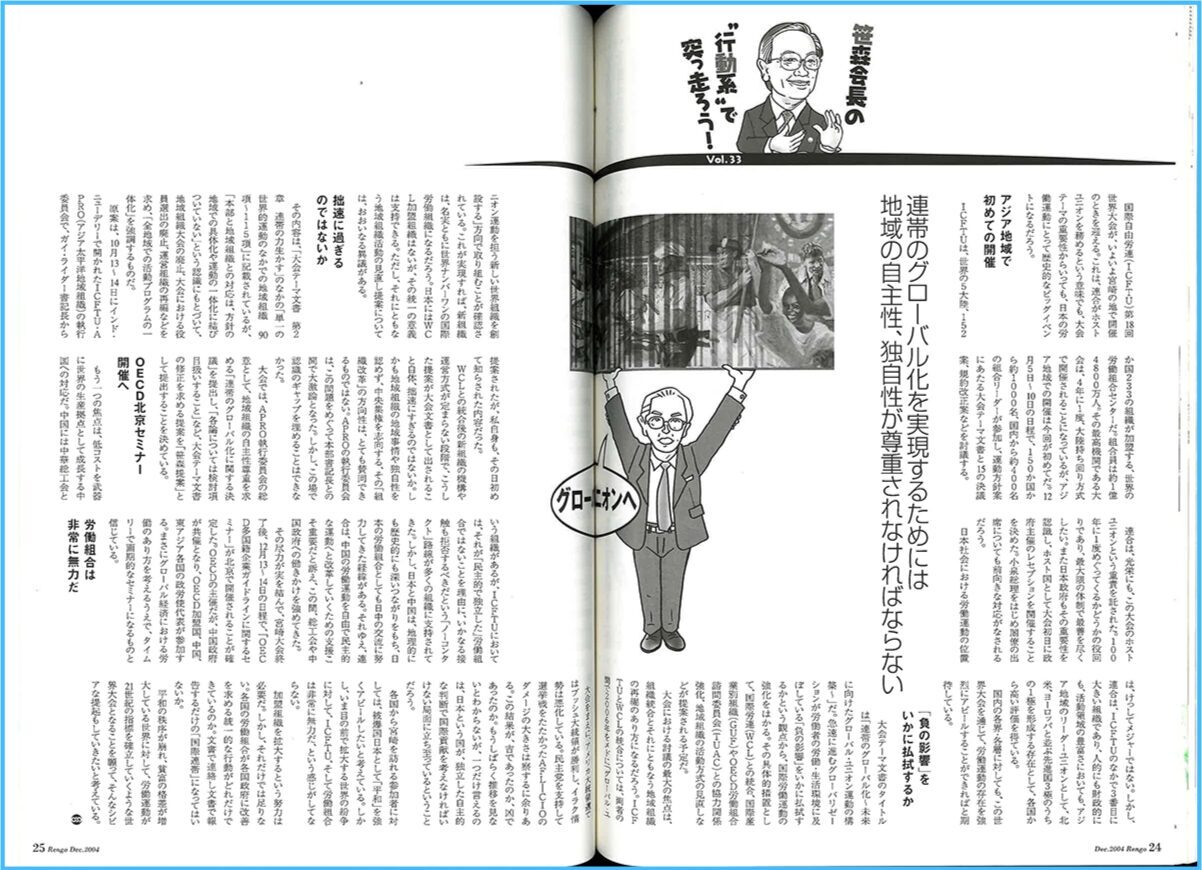
ICFTU宮崎世界大会と地域組織をめぐる本部提案(「月刊連合」2004年12月号)
もう1つのトピックである、中国の労働団体(ナショナルセンター)・中華全国総工会(以下、総工会)との関係構築をめぐる連合の取り組みについては次のページで見てみよう。
1
2