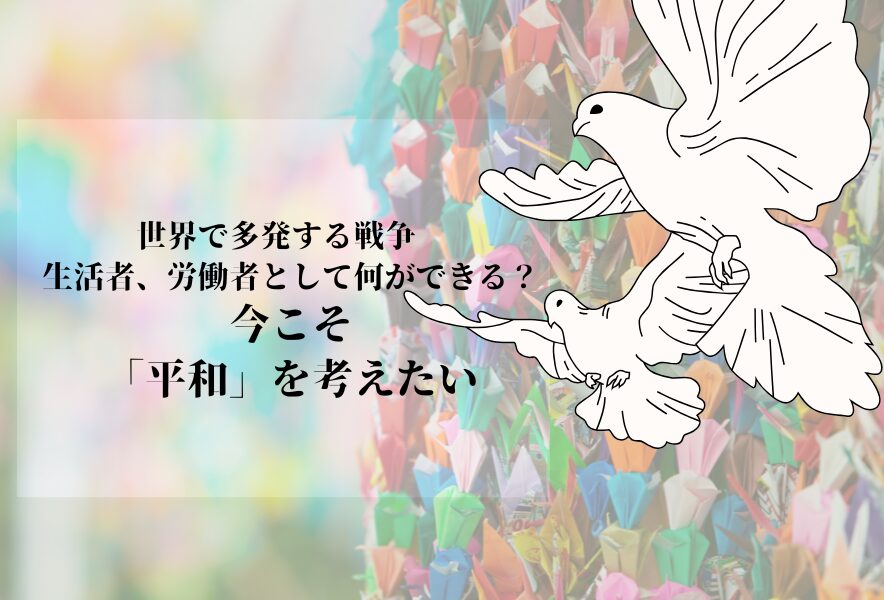長期化するウクライナ戦争のほか、イスラエルとパレスチナやイランとの武力衝突など、世界各地で戦争が多発している。日本も海外情勢と無縁ではいられない中、平和のため一生活者、一労働者である私たちにできることはあるのだろうか。平和運動に取り組む連合連帯活動局の杉山寿英局長に聞いた。

連合連帯活動局 杉山寿英局長
平和はすべてのベース 活動では「体感」を重視
連合は1989年の結成当初から30年以上、平和運動を活動の柱の一つと位置付けてきた。賃上げや職場改善など働く人の身近な課題に取り組む労働組合が、世界平和という大きな目標を掲げる理由は何だろうか。
「私たちは労働者であると同時に、地域に戻れば生活者、消費者であり、労働運動も日々の生活も平和でなければ成り立ちません。平和が全てのベースなのに戦争はなくならず、むしろ世界情勢の不安定さは高まっています。だからこそ活動を続ける必要があるのです」
活動の中心は、米軍基地を抱える沖縄と被爆地の広島・長崎、北方領土と向かい合う根室の4カ所で、毎年行っている「平和行動」だ。戦争体験者が年々少なくなる中、若い世代の組合員にもこれらの地域へ足を運んでもらい、戦争の爪痕を「五感」で体験してもらおうとしている。
このため沖縄や広島、長崎では、県外から訪れる組合員を対象に、戦跡などを巡る「ピースフィールドワーク」を行っている。例えば広島なら平和記念公園や原爆ドームなどを歩いて回るコースと、被爆した路面電車に乗って市内を巡るコースがあり「知識だけでなく心情的にも、戦争を体感してもらおうとしています」。
今年6月に行われた沖縄のピースフィールドワーク参加者の中には、小さな子どもを持つ父親もいた。「沖縄戦の集団自決では、親や祖父母が幼い子どもに手を掛けざるを得ないこともあった」という話を聞いて涙していたという。
「彼は『学生時代や独身だったころならそれほど響かなかったかもしれませんが、子どもが生まれた今は、とても他人事とは思えなかった』と語りました。戦争を自分ごととしてとらえ被害者に共感するというのは、まさにこういうことだと思いました」と、杉山さんは話した。
国内外のネットワークで、戦争の記憶を語り継ぐ
フィールドワークの案内人である「ピースガイド」は、主に地元の地方連合会の若手メンバーが務めている。メンバーの大半は引き受ける際に『戦争を体験したこともない自分に、ガイドができるのか』と悩むという。それでも多くの人が休日を使って研修に参加したり、何度も現地に足を運んだりして勉強し、本番に臨んでいる。
「プロではないので、説明がたどたどしくなることもありますが、どのガイドからも一生懸命伝えようとする姿勢が伝わってきます。重い話ばかりでは参加者が疲れてしまうからと、方言や地元あるあるなどの『ご当地ネタ』を取り入れ、親しみやすい案内も印象的でした」
平和行動が行われる地域は、総じて積極的に平和教育が行われている。ただガイド経験者からは「ただ教えられた内容を受け取るだけでなく、学んだことを参加者に語ることで、改めて自分の中に浸透した」といった感想も聞かれるという。
また、連合大分は毎年、沖縄にピースガイドを派遣するなど、他県のメンバーがガイドを務めることもある。沖縄の戦争の歴史や在日米軍基地の実相を、沖縄の仲間とともにみんなで分かち合い、平和について自ら考え伝えていく、という考えからだ。
「県外の組合員が、平和行動で得た学びを地元に持ち帰って広めることで、戦争の悲惨さをより広い地域で語り継いでいける。全国的なネットワークと700万人の組合員を擁する連合だからこそ、できることだと思います」

今年の広島・長崎での平和行動には、連合も加盟する国際的な労働組合組織であるITUC(国際労働組合総連合)から、リュック・トリアングル書記長をはじめ、米国や英国、ドイツ・アジア太平洋地域の代表者も参加する予定だ。「海外とのつながりを持っていることも、日本のナショナルセンターである連合の強みです。各国の代表者には、日本の取り組みを母国に伝えてほしいですし、逆に海外での事例も共有してほしいと考えています」
「もし都内で核兵器が使われたら?」 若い世代とコラボ
海外では米国がイランの核施設を攻撃したと発表し、ロシアのプーチン大統領も核兵器の使用を辞さない姿勢を示すなど、核兵器使用の懸念が高まっている。こうした中、新しい技術や発想を生かして、核兵器廃絶を訴える若者たちが現れ始めた。大学生や研究者らがAR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用し、「もし都内で核兵器が使用されたらどうなるか」など、戦争を疑似体験できる技術を開発するようになった。国際会議などの場で、被爆国・日本の若者として核兵器廃絶を訴える学生らの団体もある。「若者の技術や発想を支援すると同時に、彼ら彼女らと連携して平和行動を進めていければと考えています」
北海道では今年3月末から4月初旬にかけて、「平和大使」を務める高校生9人の実行委員会が主催し、原爆に遭った「被爆ピアノ」を演奏するコンサートが開かれた。実行委員会は開催費用をクラウドファンディングで集めたり、道内の労働組合を回って寄付を呼び掛けたりして、連合北海道は共催という形でサポートした。
連合が10月に開催する平和に関するシンポジウムでも、被爆ピアノとウクライナの伝統楽器「バンドゥーラ」のセッションや、平和運動に取り組む若者らとの意見交換が予定されている。
さらに連合と原水禁(原水爆禁止日本国民会議)、KAKKIN(核兵器廃絶・平和建設国民会議)は、2026年に開かれるNPT(核兵器不拡散条約)再検討会議に合わせて「核兵器廃絶1000万署名」を実施し、デジタル上で署名できる特設サイトも設けている。ただ杉山さんは、活動に関する情報を広く社会に伝えることが課題だと考えている。
「核兵器は多くの犠牲者を生む、決して使ってはいけないという意見には多くの人が賛同するでしょう。しかし平和行動や署名活動の存在を知らなければ、人々は動きようがない。情報発信にはまだまだ工夫の余地が大きいと思います」

URL: https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/kakuheiki/syomei/
「戦争の足音」が聞こえる 麻痺する危機意識
最近はSNSなどでさかんに「手ぶらで国は守れない」といったメッセージが拡散され、それらを見て核兵器容認論に傾く人も少なくない。沖縄でも基地の存在が当たり前になる中で「基地がなければ雇用や経済が成り立たない」と考える若い世代も増えているという。
「SNSでシェアされる極端な意見を『多くの人の考え』だと勘違いする人もいます。だからこそ私たち労働組合は、人が人を殺す戦争は最大の人権侵害だという、目新しくはなくとも動かしようのない事実を、伝え続けなければいけないのです」
先進国が軍事費の比率を高める中で「戦争行為や核兵器の使用は決してあってはならない」という危機意識が、世界的に麻痺しつつあるとも、杉山さんは感じている。
「沖縄島しょ部の組合関係者も『政府が台湾有事を想定して軍備を拡充している様子がうかがえ、戦争の足音が聞こえるようで本当に怖い』と話していました」
パレスチナのガザ地区で起きていることが「対岸の火事」ではなくなる、あるいは日本が「唯一の」被爆国でなくなる、といった事態を防ぐために、私たちにできることはあるのだろうか。
「世界を見れば、平和は今まさに取り組まなければいけない課題です。物価高などの身近な問題だけでなく、海外での戦争もぜひ自分ごととしてとらえてほしい。連合としても平和行動や情報発信を通じて、戦争の悲惨さを伝える活動を続けていきます」
(執筆:有馬 知子)