
RENGO ONLINE開設から2年。毎月5日と20日、休まず配信してこられたことを、読者のみなさんに感謝し、編集担当のみなさんとささやかに祝いたい。
わしよりこの家に縛られたいがか?
さて、このところ、主にプライベートで予期せぬ出来事に翻弄されているのだが、そんな日々の救いとなっているのが、朝ドラ『あんぱん』(NHK)の「ヒロシ伯父さん」(柳井寛)である。演じるのは、年を重ねてますます魅力的な竹野内豊さん。毎朝、お顔を見られるだけで幸せと思っていたのに、その役柄がめちゃくちゃ素敵なのだ。
『アンパンマン』の作者・やなせたかしさんがモデルの柳井嵩の伯父で、高知の御免与町で柳井医院を開いている。高知一高から京都帝国大学医学部に進学したエリートなのに、物腰柔らかでまったく偉ぶったところがない。早くに亡くなった弟の息子2人を引き取り、愛情深く見守る。戸田菜穂さん演じる妻の千代子は、柳井医院の「跡取り」を期待するのだが、ヒロシ伯父さんは「何のために生まれて何をしながら生きるがか 、見つけるまでもがけ。必死でもがけ」と嵩を諭し、受験に失敗した時は「絶望の隣は希望や」と励ます。そして4月30日放送の第23回は神回だった。
絵を描いて生きていくと美術学校の受験を決めた嵩の部屋に顔を出し、数学の勉強法をアドバイスしたヒロシ伯父さん。居間に戻ると、千代子が飲めないウイスキーをあおりながら、「柳井医院は、ほんまにあなたの代で終わってしもうてええがでしょうか」「あなたはいっぺんも責めんけんど、跡取りを産めんかった私のせいです」と自分を責める。ヒロシ伯父さんは「何言いゆうがな。そんなん誰のせいでもない。君はこの家と結婚したがか? わしと結婚したがやないがか? わしよりこの家に縛られたいがか? わしは、千代子にほれて、一緒になれて、これ以上の人生はないと思うちゅう」と。
この時代にこんな言葉が聞けるなんて! 「そんなに見つめんといてください」と恥じらう千代子さんも胸キュンだった。
舞台は戦時へ向かう昭和10年代である。同時代設定のドラマには、女に教育は必要ないとか、跡継ぎがどうとか、家族を縛りつけようとする「家長」がたくさん出てくるが、その対極にあるヒロシ伯父さん。ステキすぎる!
戦後、日本国憲法では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」(第24条1項)と規定され、「家制度」は廃止された。
にもかかわらず、いまだ「家制度」の呪縛が残存しているようだ。選択的夫婦別姓に関するニュースが出ると、待ち構えていたかのように、家族の一体感だの、戸籍制度が崩壊するだのといった意見がウヨウヨわいてくる。事実誤認も多いのに、そんな意見に惑わされて政治は動かない。
選択的夫婦別姓は、ヒロシ伯父さんが説く「一人ひとりが自分らしく生きる」ための1つの選択肢だと思う。コラムの22回に書いたZ女子の結婚は「別姓待ち」となっているが、宇多田ヒカルさんの新曲『Mine of Yours』にある「令和何年になったら この国で夫婦別姓OKされるんだろう」というフレーズは、まさにZ女子の心の叫びだ。
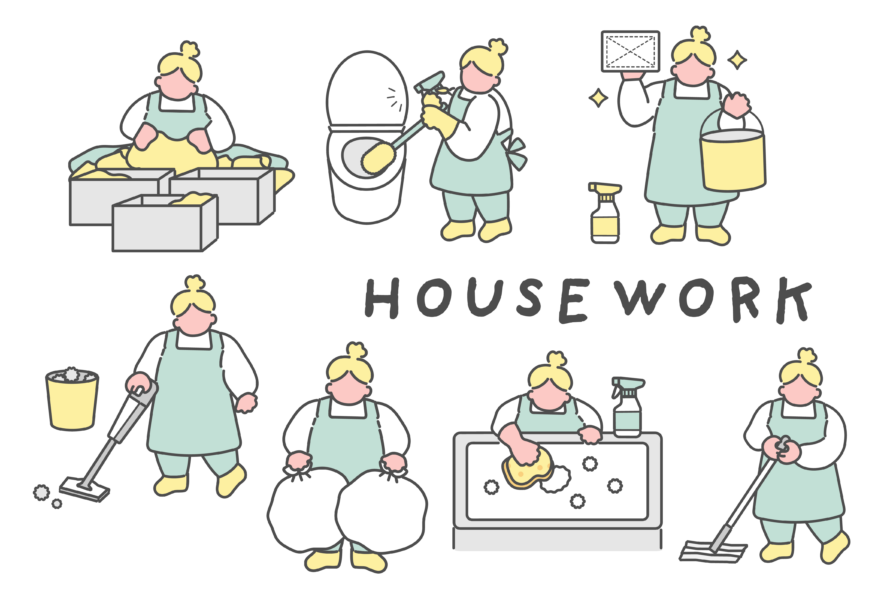
主婦なんて絶滅危惧種?
朝ドラ『あんぱん』で、もう一人ステキだなと思うのが、江口のりこさん演じるヒロインのぶの母、羽多子さんだ。夫を亡くし、シングルマザーとして3人の娘を育てるためにあんぱん作りを学び、パン屋を開いて娘たちの夢を応援する。子どもの人生を型にはめようとせず、一人ひとりに向き合う姿に見習わなきゃと思わされる。
さて、羽多子さんは、令和に転生してワーキングママとして奮闘中だ。
今クール話題のドラマ『対岸の家事~これが、私の生きる道!』(TBS系列)である。江口のりこさん演じる長野礼子は、営業職として成果を挙げていたが、3歳と1歳の子育てのため総務部に異動。定時になると速攻で保育園に迎えに行き、子どもたちにご飯を食べさせ、お風呂に入れ、寝かしつける。合間に洗濯や掃除もこなすからクタクタだ。そこに追い打ちをかけるのが、子どもの感染症。おたふく風邪で1週間登園できなくなった時は、若い同僚に、これ以上迷惑をかけられないと絶望する。実家は遠く、夫は出張が多い。意を決して、同じマンションに住む専業主婦の村上詩穂に子どもを預かってほしいと頼み込む。
あまりにリアルで胸が痛くなった。
私もZ女子やZ男子が小さい頃は、家事が回せなくて絶望した。年下の専業主婦・3人の子持ちママ友に「働いたほうがいいよ」と勧めていたのだが、ある日、彼女が子どもを連れて突然遊びにきた。アポ無し訪問だ。ちょうど仕事が立て込んで、わが家は家事崩壊の極限状態。もはや取り繕うこともできない光景を見た彼女から「お仕事大変なんですね。やっぱりまだ仕事するのはやめておきます」と言われ、返す言葉がなかったという苦い経験がある。
ドラマの主人公は、多部未華子さん演じる、専業主婦の村上詩穂。高校生の時に母を亡くし、家事をしなければならなくなって大好きな部活をやめる。そんな日々と決別しようと、家を出て美容師に。その常連さんだった虎朗と結婚し、2歳の娘・苺ちゃんと3人で暮らしている。
一昔前の「専業主婦」ドラマは、「専業主婦VS働く女性」という構図をベースに「専業主婦っていいよね」という価値観を押し付けてくる感じがあったが、『対岸の家事』のテイストとはまったく違う。
詩穂は、長野さんには「主婦なんて絶滅危惧種」と言われ、公園で知り合った育休中のパパ友・中谷さんには、低成長、超少子高齢化の時代に「女性が家事だけに専念できる余裕はこの国にはもうないんです。専業主婦は贅沢です」と説教されるが、それでも2人が困っていることを知ると、全力で助けようとする。
ドラマは終盤に向けて進行中だが、毎回「家事やケア労働なくして社会は成り立たない」ということを再認識させてくれる。
自分ごとの、家しごと—「いまを生きる」ための知恵と技術
『対岸の家事』を観ながら思い出したのが、『〈主婦〉の学校(The School of Housewives)』(監督:ステファニア・トルス、配給:kinologue、2020年)というドキュメンタリー映画だ。2年前、ジェンダー・ギャップ指数が十数年連続1位のアイスランドってどんな国だろうと調べていたらヒットして、配信サイトで視聴した。
映画のキャッチコピーは〈自分ごとの、家しごと 北欧アイスランドにある男女共学の「主婦の学校」が教えるのは「いまを生きる」ための知恵と技術〉。
わが家で、しょっちゅう家事が崩壊してしまうのは、時間が足りないだけではなく、私や夫の家事能力が低いからだとずっと思っていた。私は高校の家庭科が男女別だった世代。女子大の家政学部系で学んだ友人たちは、高い家事能力を身につけているが、私は不器用で針仕事も料理も掃除も苦手。家事負担が倍増する子育て期は苦労した。もっとスキルがあれば、こんなにストレスにならないのにと何度思ったことか…。
アイスランドの「主婦の学校」は、本当に魅力的だった。1942年に創立され、定員24名の学生が寮で共同生活を送りながら生活全般の家事を実践的に学ぶ。1990年代に男女共学となり、「主婦(主夫)になるため」ではなく、「いまを生きる」ための知恵と技術を求めて学生が集まってくるという。
映画は、荒れ地にベリーを摘みに行くシーンから始まる。ジャムにして保存するのだ。初歩的な料理からおもてなし料理・伝統料理、洗濯法やアイロンがけ、縫製技術、テーブルセッティング&マナー、防災や環境への配慮まで、できることなら、今からでも一から学びたい内容ばかりだ。
ジェンダー先進国アイスランドも、かつては「家事や育児は女性が担うもの」とされていて、女性が多い職種の賃金は低かったという。これに抗議して、女性たちは、国際女性年である1975年10月24日、「女性の休日」を掲げて一斉ストライキを決行した。主婦は子どもを夫に任せ、働く女性は職場を離れ、広場に結集してデモ行進。国内の9割の女性が参加した。この行動によって、女性の力がなければ家庭も職場も社会も立ち行かないことが実証され、アイスランドはジェンダー平等先進国へと大きく動き始めたという。
ジェンダー・ギャップ指数120位前後をさまよっている日本とは、何が違うのか。
アイスランドの女性たちが団結する基盤となったのは、第一に家事やケア労働の正当な価値を社会に認めさせたいという思いだったのではないかと思う。
日本は、それを横に置いたまま、仕事優先で「男並み」に働ける女性だけを平等に扱う方向で進んできた。『対岸の家事』が描くように、ケア労働が疎かになれば生活が回らないのに、会社も政府も、その責任を個々人に押し付けている。社会の根本が変わらないから、ジェンダー平等が進まない。そんな気がする。
どうすればいいのかと考えていたら、『主婦論争を読む』(上野千鶴子編、勁草書房)という本が本棚に眠っていることを思い出した。次回はそこに踏み込んでみたい。
★落合けい(おちあい けい)
元「月刊連合」編集者、現「季刊RENGO」編集者
大学卒業後、会社勤めを経て地域ユニオンの相談員に。担当した倒産争議を支援してくれたベテランオルガナイザーと、当時の月刊連合編集長が知り合いだったというご縁で編集スタッフとなる。


