[7]アジアの労働運動と連合
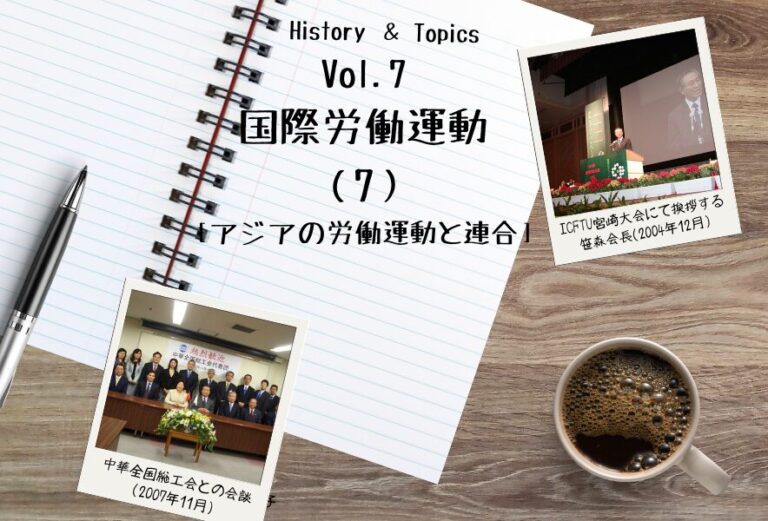
日本の労働組合は、半世紀以上も前から、アジア地域の労働運動の発展に力を注いできた。例えば1960年に結成された「TWARO」(通称:アジア繊維/国際繊維被服皮革労組同盟(ITGLWF)の地域組織)は、全繊同盟(現・UAゼンセン)がその中心的組織として資源を投入してアジア地域の労働者の労働条件改善や組織化に取り組み、グローバルに活躍するユニオンリーダーを輩出してきた。そうした伝統を受け継いだ連合も、アジア地域の労働運動を重視し、ICFTU(国際自由労連)やITUC(国際労働組合総連合)のアジア・太平洋地域組織の会長や書記長という責任あるポストを引き受けてきた。そして、時にはアジアの現状をよく理解する立場から、国際労働運動の方針に対して物言う「アジアの代弁者」の役割も果たしてきた。 アジアの労働運動における連合のリーダーシップと貢献は、アジアの労働組合からも高く評価されているが、それを印象付けた出来事について、生澤千裕日本ILO協議会理事の話を聞こう。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)
日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー
1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。
「アジアの労働運動を救った」笹森清連合会長

ICFTUが宮崎で世界大会を開催「連帯のグローバル化」をめざす(「月刊連合」2005年1月号)
2004年12月5日から6日間、宮崎市でICFTU第18回世界大会が開催された。世界大会は、4年に1度、各地域の持ち回りで開催されることになっていたが、宮崎大会はアジア地域で初の開催。連合は、ホストユニオンの重責を果たすため、大会準備室を設置し、各局からスタッフを集めて万全の体制で準備にあたった。
大会には、世界150カ国から約1000名、国内から約400名のユニオン・リーダーが参加。「連帯のグローバル化—未来に向けたグローバル・ユニオン運動の構築」をスローガンに多国籍企業への対応や組織強化、WCL(国際労連)との統一などに関する議案が討議され、成功裏に幕を閉じた。しかし、その前段で、ICFTU本部が宮崎大会に向けて提起したある議案をめぐって、連合の笹森清会長が「宮崎大会の開催を返上する」とまで発言する事態が起きていたという。
「連帯のグローバル化を実現するためには
地域の自主性、独自性が尊重されなければならない」
これは、宮崎大会直前に執筆された笹森会長のコラム(「笹森会長の“行動系”で突っ走ろう」月刊連合2004年12月号)の見出しである。本文には、ICFTU本部の地域組織活動の見直し提案について「おおいなる異議がある」とし、「地域組織の地域事情や独自性を認めず、中央集権を志向する、その『組織改革』の方向性は、とても賛同できるものではない。APROの執行委員会は、この問題をめぐって本部書記長との間で大激論となった」と報告し、宮崎大会では、「APRO執行委員会の総意として、地域組織の自主性尊重を求める『連帯のグローバル化に関する決議』を提出し、各論については検討項目扱いすることなど、大会テーマ文書の修正を求める提案を『笹森提案』として提出することを決めている」と記されている。
いったい何があったのか。生澤さんの説明を聞こう。
2004年9月、第18回世界大会に向けて、ICFTU本部のガイ・ライダー書記長(後のILO事務局長)は、大会提出議案資料を各加盟組織に配布しましたが、そこに「地域大会を廃止し、地域大会で選出する地域組織書記長は地域執行委員会が推薦し本部執行委員会が承認する」という提案が入っていたんです。
事実上の地域組織取り潰しです。ICFTU-APROの鈴木則之書記長(当時)にとっても寝耳に水の提案。APROは、10月にニューデリー(インド)で開催した執行委員会で、「提案は容認できない」と否決するのですが、その席上で、ガイ・ライダー書記長に対し、強く撤回を迫ったのは、連合の笹森会長でした。
「現場の実態や自主性を尊重しない運動は成功しない」と訴え、「このような提案がなされるのであれば、連合は世界大会の宮崎への招致を返上する」と言い切った。
開催まで2カ月を切ったタイミングでの「返上」発言のインパクトは絶大でした。
連合はICFTUの中で3番目に大きい組織であり、人的にも財政的にも活動領域の豊富さにおいても、アジア地域のリーダー的組織。ICFTU本部も、その連合のトップの言葉はないがしろにはできません。
詳しいことはわかりませんが、おそらく笹森会長自身が「これは、宮崎大会を返上してでも、アジア地域組織を守らなければいけない」と判断して、APRO執行委員会に乗り込んだのだと思います。APROも強い危機感を持っていたものの、鈴木則之書記長も主要組織のリーダーも、本部提案を覆すのは難しいと半ば諦めていた。ところが、笹森会長は、ニューデリーの空港に到着すると、開口一番「鈴木さん、この本部直轄方針は撤回させよう」と…。卓越したリーダーって、理想と現実と現場を見て、どう行動すべきかを的確に判断できるのだと感服しました。
最終的には、宮崎の世界大会開催後にICFTU執行委員会が「大会ほか、現行規約の構造は維持する」との修正を提案することで決着し、APRO執行委員会の決議を本部執行委員会が受け入れた形となりました。
連合の事務局長4年、会長4年を務めた笹森清氏は、会長就任時、連合のスローガンを「力と政策」から「力と行動」に変え、連合評価委員会を設置した。頭の回転が速くて判断力も行動力もあり、演説ではその思いが言葉になって溢れ出た。現場を大事にして運動を進めることの重要性を深く理解していた素晴らしい指導者のなせる技であったと思います。
『アジア太平洋の労働運動—連帯と前進の記録』(明石書店)にこの経緯を詳細に記した鈴木則之元APRO書記長からは、この時のことを称して、「笹森氏はアジアの労働運動を救った、と多くのアジアの同志から言われた」という話を聞いています。

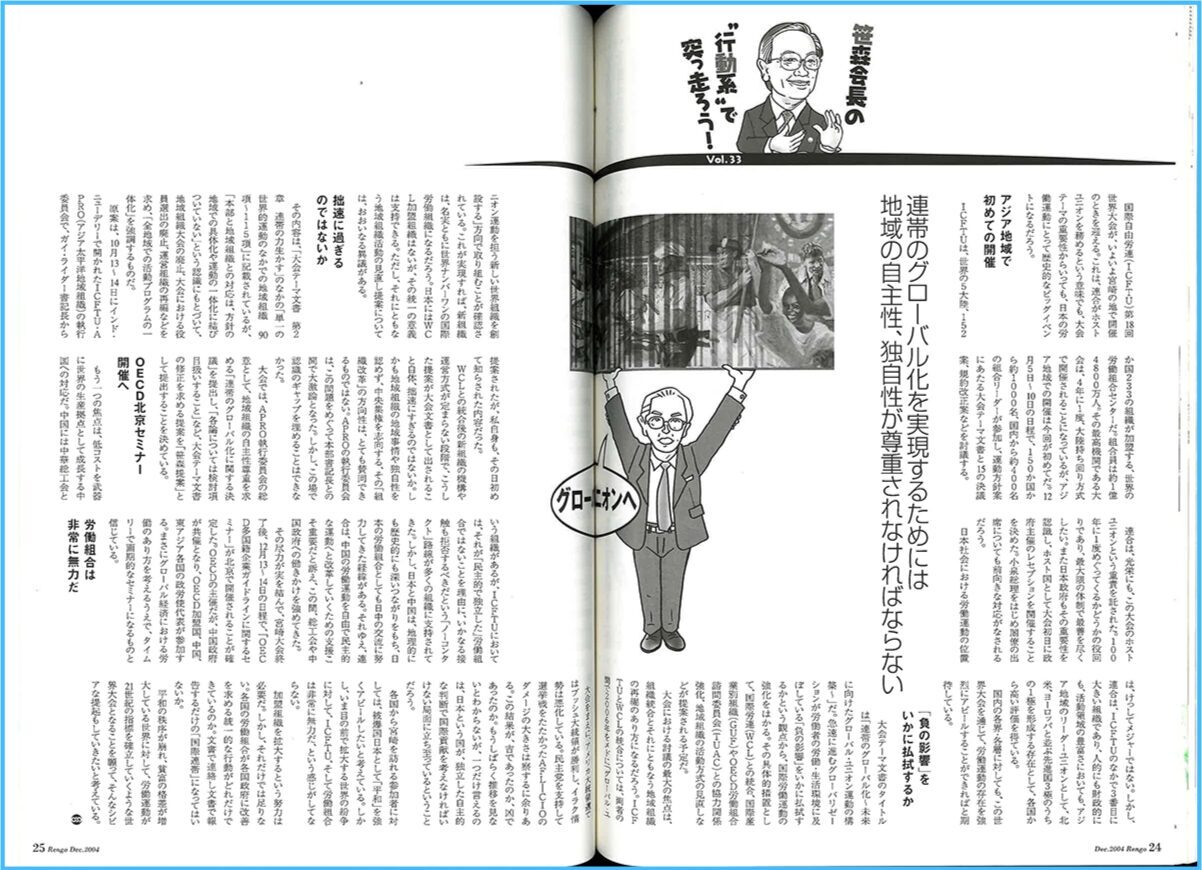
ICFTU宮崎世界大会と地域組織をめぐる本部提案(「月刊連合」2004年12月号)
もう1つのトピックである、中国の労働団体(ナショナルセンター)・中華全国総工会(以下、総工会)との関係構築をめぐる連合の取り組みについては次のページで見てみよう。
中華全国総工会との関係改善に動いた髙木剛連合会長

2009年9月10~13日 髙木会長を団長とする連合代表団が訪中した定期会談(右から3番目が髙木会長)
隣国である中国の労働運動が、孤立したものであって良いはずはない
さて、もう1つのトピックは、中国の労働団体(ナショナルセンター)・中華全国総工会(以下、総工会)との関係構築をめぐる連合の取り組みだ。
実はその1つの発端となったのは、2004年12月のICFTU宮崎大会の直後に予定されていた「OECD多国籍企業ガイドラインに関するセミナー(北京)」だった。セミナー開催の経緯について、笹森会長のコラム(「笹森会長の“行動系”で突っ走ろう」2004年12月号)には、宮崎大会への本部提案批判に続いてこう書かれている。
もう1つの焦点は、低コストを武器に世界の生産拠点として成長する中国への対応だ。中国には中華全国総工会という組織があるが、ICFTUにおいては、それが『民主的で独立した』労働組合ではないことを理由に、いかなる接触も拒否するべきだという『ノーコンタクト』路線が多くの組織に支持されてきた。しかし、日本と中国は、地理的にも歴史的にも深いつながりをもち、日本の労働組合としても日中の交流に努力してきた経緯がある。それゆえ、連合は、中国の労働運動を自由で民主的な運動へと改革していくための支援こそ重要だと訴え、この間、総工会や中国政府への働きかけを強めてきた。その尽力が実を結んで、宮崎大会終了後、12月13〜14日の日程で、「OECD多国籍企業ガイドラインに関するセミナー」が北京で開催されることが確定した。OECDの主催だが、中国政府共催となり、OECD加盟国、中国、東アジア各国の政労使代表が参加する。まさにグローバル経済における労働のあり方を考えるうえで、タイムリーで画期的なセミナーになるものと信じている
ところが、この北京セミナーは、中国政府が直前に中止を決定。その後、連合と総工会との関係が一気に悪化してしまうことになる。いったい何があったのか。生澤さんの話を聞こう。
北京セミナーの中止は、連合としても大きなショックでした。長年の努力は何だったのかと、無力感にとらわれた関係者も多かったのではないでしょうか。
日本の労働組合が、本格的に総工会との関係(再)構築に動いたのは、1970年代の終わりから80年代の初め頃だと記憶しています。日本と中国は1972年に国交正常化を果たし、1978年には中国の「改革・開放政策」がスタート。経済特区の設置や市場経済の導入など経済近代化政策が進められます。他方、文化大革命の影響下で機能停止していた総工会が復活を果たしたのが1978年の大会でした。こうした動きを背景にして、総評は1979年から総工会との交流を再開し、同盟も1980年に代表団を派遣して総工会との関係を構築。当時、ICFTUは「ICFTUとして社会主義圏の労働組合とは交流しないが、加盟組織の個別の交流は容認する。ただし、公式に共同声明を発するなどの行動はしないこと」を原則としていて、ICFTUに加盟する同盟の交流もそれに則ったものでした。
ところが、連合結成の半年前の1989年6月、民主化を求めて北京の天安門に集まった人々が武力で排除され、戒厳令が発せられるという天安門事件が起きました。中国の独立労組も弾圧を受けることとなりました。
ICFTUは中国政府の武力弾圧を強く非難しました。当時の民間連合は、総工会との交流関係をストップ。ただちに以降の総工会との関係について組織内で議論をスタートさせ、議論は連合結成後へと引き継がれました。
そして、出した結論は、「ICFTUの対応も十分に尊重しつつ、中国の労働組合との友好関係を求めていく」というもの。1990年1月に中国で戒厳令が解除されたタイミングで「今後の日中関係の展開を政府や財界に委ねるのでなく、労働者、人民間の接触を深めることが重要になるとの立場」から関係構築をはかるという声明を発しました。
これにもとづいて、同年12月、岩山保雄連合副会長を団長とする非公式の訪問団を中国に派遣。そこで「ILO国際労働基準の確立への努力を両組織の共通の立場として、交流を再開していくこと」を確認。1992年5月には山岸章連合会長を団長とする訪問団が訪中し党総書記や総工会主席と会談。「相互尊重の上に共通点を探り、協力関係を発展させる」ことを確認して交流が正式に再開しました。
この時点でも、ICFTUは「総工会とは一切の接触を持たない」という方針を堅持していましたが、連合は1994年5月、ICFTUに対して非接触方針を見直すべきという意見書を提出します。その後、様々な経過がありましたが、1997年の香港の主権の中国への返還問題なども大きく影響する中で、ICFTUは方針を転換。2000年の第116回執行委員会で「総工会との対話を維持発展させるとの方針を承認する」ことを決定したんです。
ICFTU加盟組織と総工会との交流に進展が見られる中で、ICFTUが総工会とのトップレベルでのコンタクトの機会として開催を準備したのが、2004年12月の北京での「OECD多国籍企業行動指針に関する国際セミナー」だったんです。これが実現すれば、ICFTUの主要先進国労組代表者が、OECD労働組合諮問委員会(TUAC)の幹部として中国を訪問することになる歴史的に大きな意義を持つ企画でした。ところが、直前になって中国政府からキャンセルが伝えられ、その理由も説明されない中で、総工会への失望と批判が高まる状況が生まれてしまったんです。
それが影響したのかどうかわかりませんが、セミナー中止から半年後の2005年6月、ILO理事選挙で再選を目指して副理事に立候補していた総工会の副主席が落選してしまいます。総工会は、落選の背景に、連合やICFTU-APROのマイナスの動きがあったのではないかと疑念を持ち、関係はギクシャクすることに。ICFTUは、総工会との関係を築く必要があるとの認識を持ち続けていましたし、理事選挙への関与は事実無根の思い込みなのですが、総工会の態度は頑なで誤解を解くのは容易ではないと思われました。
ところが、2005年10月に連合会長に就任した髙木剛会長は、それを見事に突破していったんです。関係改善策を考えに考えた末、髙木会長は「連合会長に就任したから、総工会に挨拶に行こう。就任の挨拶なら、拒否されることはないだろう」と。
日本は、アジアの先進国としてアジアの労働運動に力を尽くしてきました。その連合の会長が自ら挨拶に行くというのは、実は異例のこと。でも、そこにこだわらず、そういう判断ができるのが髙木会長でした。
2006年2月、髙木会長は、会長就任の挨拶に訪中し、総工会の幹部(王兆国主席、張俊九前副主席、孫春蘭第一副主席)と会談。敬意と誠意をもって語りかけ、「連合と総工会とが率直な話し合いを行うこと、2006年末には中国で両組織による定期会談を再開すること」で合意に至りました。
さらに髙木会長はITUCガイ・ライダー書記長とも緊密に連絡を取り合い、総工会とITUCの双方の立場を重視した調整に奔走。2007年12月にワシントンDCで開催されたITUC執行委員会は、中国についての詳細かつ重要な議論を行い、「ガイ・ライダー書記長が総工会とのコンタクトを行い、両組織間において可能な関係構築をはかるための条件を探求する」ことを確認するに至りました。2008年11月には、ガイ・ライダー書記長と総工会の王兆国主席との会談が実現。総工会は2008年のILO理事選挙で副理事の席を、2011年には正理事の席を得るに至りました。
世界に大きな影響力を持つ隣国である中国、その労働運動が孤立したものであって良いはずはありません。その意味で、総工会との関係改善の取り組みの意義は非常に大きかったし、その原動力は、髙木会長の行動力と熱意にあったと思います。関係資料にはすべて丁寧に目を通し、自分自身がまず理解し吸収する。これはと思ったら即行動に移す。懐深く、人間味溢れるリーダーでした。
私は2005年に連合国際局に移り、髙木会長の訪中や定期会談、ITUCとの折衝などにほぼすべて同行しましたが、当時のパスポートを見てみたら、中国のみならず、ヨーロッパを含めてものすごく高い頻度で海外に出張していました。改めて、得がたい経験をさせてもらったものだと感謝しています。

2006年11月27日~12月2日 髙木会長を団長とする連合代表団が訪中し定期会談 集合写真

2009年9月10日~13日連合代表団が訪中した時の総工会との定期会談時の様子

2009年12月7~8日浙江省杭州市で「日中多国籍企業の労使関係に関するセミナー」を開催

セミナーの様子
〈参考文献〉
鈴木則之(2019)『アジア太平洋の労働運動—連帯と前進の記録』(明石書店)
(執筆:落合けい)
【関連記事】
[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉
[1]連合結成とICFTU加盟問題〈後編〉
[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編]
[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[後編]
[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援
[3]世界を変えた国際連帯行動②南アフリカのアパルトヘイトを撲滅する取り組み
[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(前編)
[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(後編)
[4]「国際労働財団(JILAF)」設立秘話
[5]労働組合が求めた「ビジネスと人権」
[6]レイバーサミット —ディーセント・ワークを求めて