フリーランスのトラブル回避は「契約の書面化」がカギ
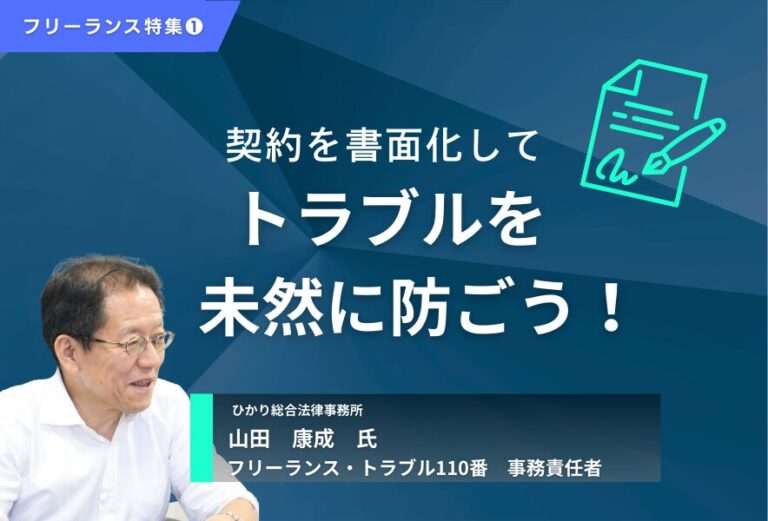
フリーランスの契約条件明示などを定めたいわゆる「フリーランス法」が施行されたが、契約内容や報酬などを巡るトラブルは今も後を絶たない。相談窓口「フリーランス・トラブル110番」事務責任者で弁護士の山田康成さんに、フリーランスの実状やトラブルを回避するための「備え」について聞いた。

ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士 山田康成
特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会委員。国際基督教大学非常勤講師(社会保障法)。厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」の事務責任者を務める。フリーランス・トラブル110番では自身も相談員として多数の相談を受けている。「フリーランス法における就業環境整備に関する規制の概要と問題点」(季刊労働法287号)等フリーランス法に関する執筆多数。フリーランスが安心して活躍できる場が広がる社会環境の整備に向け尽力中。
報酬関連の相談が最多 零細同士でトラブルに
「フリーランス・トラブル110番」は、厚生労働省から委託を受けて第二東京弁護士会が運営している。相談内容で最も多いのは、未払いなど報酬関連の相談で約3割を占め、契約書を交わしてもらえないなど、契約関連の相談が続く。
フリーランス法は報酬の一方的な減額などを禁じるほか、取引条件を書面などで明示するよう定めている。それでも「契約内容に関する相談より、そもそも書面が『ない』ことで生じるトラブルが今でも多いです」。
またトラブルの相手は、多くが資本金1000万円未満で下請法も適用されない中小・零細企業だという。ある程度規模が大きければ、新しい法律に対応できる体制が整っていることが多いが、零細企業は法知識も十分とは言えず、資金力も乏しいため未払いが生じてもお金の回収が難しい。
発注者とフリーランスが良好な関係を築いていても、発注者の収益悪化などで関係性が変わるリスクは常にある。だからこそ「書面で取引条件を示しておくことは、非常に重要です」と、山田さん。実際にトラブルが起きて訴訟などを起こしても、書面がなければ取引条件の内容を証明するのが難しくなってしまうからだ。
「業界団体などが用意する『標準契約書』を活用することもできますし、成果物の仕様や納期、報酬などを記したSNSやメールも証拠となり得ます。SNSなどの場合は、データを改ざん・消去されないようスクリーンショットなどを残しておきましょう」
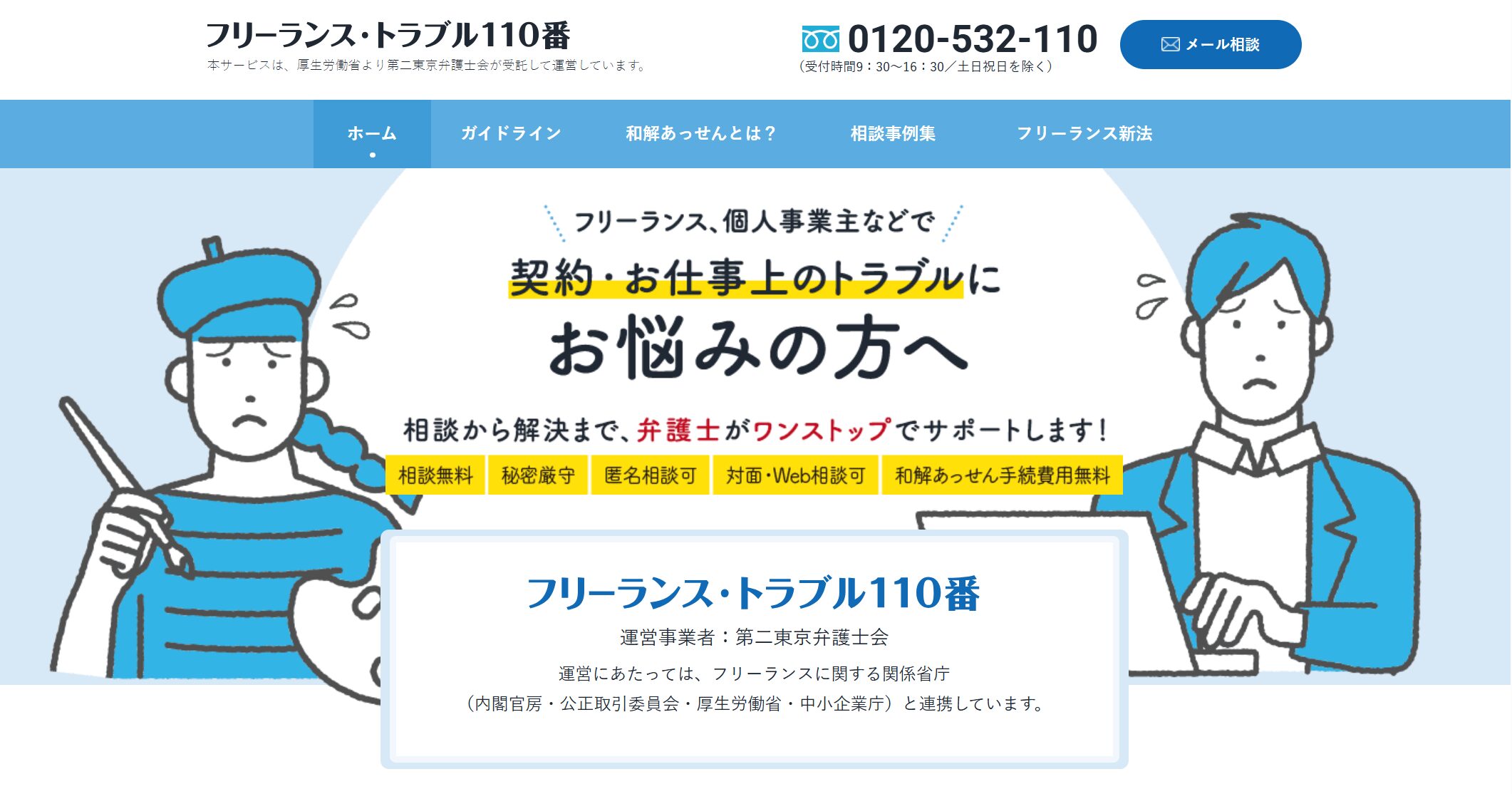
URL:https://freelance110.mhlw.go.jp/
和解あっせんや少額訴訟を活用 大事なのはコミュニケーション
トラブルの解決にあたって大きな選択肢となるのが、フリーランスと発注者の間に弁護士が入って話し合い、合意をめざす「和解あっせん」の仕組みだ。「110番」を通じた和解あっせんは無料で利用できる。ただ交渉が不調に終わったり相手が応じなかったりした場合は手続きが終了してしまう。その時は訴訟手続きを選択することになる。
訴訟は原告側が弁護士に依頼するなどして書面や証拠をそろえる必要があり、一定のお金と時間が掛かる。ただ請求額が60万円以下の場合、原則1回の審理で結論が出る「少額訴訟」を使うことで、負担を軽減できる。また実際には「和解あっせんや少額訴訟に踏み切る」と発注者に伝えるだけで、相手が話し合いに応じ、交渉が前進することもあるという。
「110番は実務に長けた弁護士が相談に応じるので、お金を回収するための具体策を提案できるのが強み。和解あっせんや少額訴訟は手軽で柔軟な解決法ですし、私たちもこれらの手続きの仕方などをサポートします」
相談の中には「成果物が必要な水準を満たしていない」「納期に若干遅れた」などフリーランスの「落ち度」を理由に報酬を減額された、という内容もある。特にデザイナーなどは、発注者にどんな成果物を求めているかを聞いたら「それを考えるのがあなたの仕事」と言われ、結果的に「これでは不十分」と報酬を減額されるケースが多いという。
フリーランス法では、発注者に事前に成果物の規格や仕様など「給付の内容」を明示することが義務づけられている。デザインなら発注者はどんな顧客を想定し、どんなテイストを求めているかといったことを説明しなければならず、説明がない場合は成果物が想定と違っても、報酬減額は許されない。
「発注者が、業務に関してフリーランスとやり取りしていれば、『給付の内容』を示した証拠はメールなどで残っているはずです。大事なのは双方のコミュニケーションです」
苦境に陥る軽貨物ドライバー 過剰なサービスに規制を
相談を業種別に見ると、最も多いのは運送関連(約15%)だ。運送業というとフードデリバリーなどのプラットフォームワーカーが注目され、海外でもこうした働き手を労働者として保護する動きが広がっている。しかし山田さんは、家庭に荷物を届ける軽貨物ドライバーの相談に、より深刻な内容が多く、契約の書面化などの対策では解決できないケースも多いと指摘する。
デリバリーの場合、どのプラットフォームを使って何時から何時まで働くかは、働き手自身が決められる。それに対し軽貨物ドライバーの多くは契約期間中、タイトなノルマを課され、1日中拘束されて配達に追われる。
「月額60万円の報酬を提示されたのに、ガソリン代などの経費を大幅に差し引かれた、わずかな遅配や車の傷を理由に多額の罰金を課されたという相談も多い。『話が違う』と辞めようとしたら、違約金や賠償金を請求された人もいます」
日本郵便も配達の委託事業者に対して、誤配やクレームの際に1件数千円~数万円の違約金を課していたことが明らかになり、下請法違反に当たるとして公正取引委員会から是正指導を受けた。これらの経費や罰金、違約金はたとえ契約書に示されていたとしても、ドライバー側が交渉を通じて変更する余地はほとんどないのが実状だ。
ドライバーの過酷な環境は、運輸業の多重下請け構造に加え、「翌日配送」「配送無料」などの過剰なサービスも密接に関係していると、山田さんは指摘する。
「『通販サイトで買った商品は翌日届いて当然』という市民の認識を改め、サービスに一定の規制をかけることも検討すべきです」

労働者として保護を 社会保険料が雇用の壁に
運輸業界以外では、エステティシャンや美容師らも事実上ひとつの職場に拘束され「専属性」の高い働き方を強いられている。受付や清掃など契約外の業務を課されるという、フリーランス法で禁じられた「不当な経済上の利益の提供要請」も横行している。
山田さんはドライバーやエステティシャンのような働き手は本来、「労働者」として保護するべきだと訴える。
「労働契約なら、賃金全額支払いの原則によって働いた分の賃金を確保できます。しかしドライバーなどは業務委託契約だというだけで、実質的には労働者同様に扱われているのに、未払い分の回収が難しくなるなどの不利益を被っているのです」
人手不足にもかかわらず、発注者側が人材を雇わず業務委託の形を取るのは、雇用すると社会保険料の支払い義務が生じることが一因だと、山田さんは考えている。中小・零細企業にとって保険料負担が経営に与える影響は小さくはないが、「貯金する余裕もないフリーランスがシニアに突入したら、国民年金だけでは生活を賄えず、生活保護の受給者が急増する恐れもあります」として、政府として何らかの対策を講じるべきだと訴えた。
「社会保険料を含めたフリーランスのセーフティネットを、国全体で重点的に議論すべきですし、連合も働き手の代表として、きちんと政策に関わってほしい」
フリーランスと労働組合、親和性は高い 情報提供し交渉をサポート
フリーランスの待遇改善に向け、労働組合にできることはあるだろうか。相談の中には、発注者によってフリーランス全員の報酬を一律で引き下げられた時など、集団で交渉した方が有利に進められるケースもあるという。1人で「報酬引き下げは不当だ」と訴えるよりも、10人で不当性を主張した方が発注者への影響力ははるかに大きいからだ。
「労働組合とフリーランスはなじまないと考えられがちですが、実は集団交渉のニーズは非常に高い。ナショナルセンターの連合が中心となって、多様な産業にまたがる当事者への情報提供や、交渉の際のサポートを担うべきでしょう」
一方でフリーランス側も、契約書の内容を理解し自分の身は自分で守る意識を持つ必要がある。連合も「Wor-Q(ワーク)」というサイトを設けてフリーランスにとって必要な情報を発信しているほか、連合大阪フェアワーク推進センターは、関連する法律や契約のあり方などを説明した「フリーランスで働くあなたのために」という冊子も作成した。

「契約や法律を知っておくことに加えて、先方の言い値でなく自分で『自分の値段』を決め、強みを売り込んで顧客を広げる意識も大事。それができればフリーランスは、自分の判断でやりがいのある仕事を選べる、とても魅力のある働き方です」
企業側にとっても、フリーランスを活用するメリットは大きい。特に人件費を投じて優秀な人材を雇用するのが難しい中小企業は、フリーランスから高度なスキルの提供を受けることで優れたアウトプットを生み出し、大手を逆転するチャンスも得られる。
「発注者はこうしたことを認識し、彼ら彼女らを尊重するべきです。私たちも発注者とフリーランスが良い関係を築けるよう、支援していきます」
(執筆:有馬知子)