「柴又・矢切の渡し」清水事務局長のFree Walk【28】
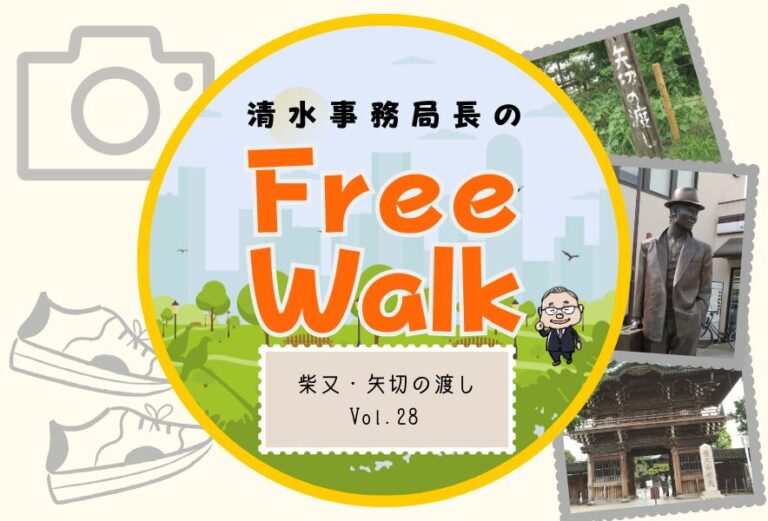
葛飾区柴又の帝釈天(たいしゃくてん)に行ってみた。帝釈天題経寺(だいきょうじ)とも呼ばれるが、正式には経栄山(きょうえいざん)題経寺と号する。江戸時代初期の1629(寛永6)年に創建された日蓮宗の寺院で、1912(明治45)年の夏目漱石の小説『彼岸過迄』にも登場し、1969(昭和44)年から始まった人気映画『男はつらいよ』の渥美清が演じる主人公・車寅次郎(フーテンの寅さん)ゆかりの寺として広く知られるようになった。寺には宗祖の日蓮が自ら刻んだという「帝釈天の板本尊」があったが、長年所在不明になっていた。十代将軍・徳川家治の治世で、天明の大飢饉や浅間山の大噴火の数年前、1779年に本堂(祖師堂)を修復した際に再発見された。その日が庚申の日であったことから、60日に一度の庚申の日に縁日が開催され、現在に至っている。

二天門から入ると正面に帝釈堂があり、手前の拝殿と奥の内殿がある。内殿には「帝釈天の板本尊」が安置され、内殿の外側には全面に浮き彫りの装飾彫刻が施されている。見学者用の通路が設けられ「彫刻ギャラリー」として一般公開されているが、法華経の代表的な説話を浮き彫りにした10面の精巧さは圧巻である。帝釈天の大きな見どころで、一度は拝観することをお勧めする。

真ん中:帝釈堂の内殿外側の装飾彫刻
下:本尊の「大曼荼羅(仏像ではなく、中央に『南無妙法蓮華経』を書き、その周りに仏、菩薩、天、神などの名を書いたもの)」が安置される祖師堂(本堂)
京成電鉄金町線の柴又駅前から参道が伸びている。参道の両側には、戦火を逃れた老舗や木造づくりの土産店などが並び、国の重要文化的景観にも指定されている。名物の草だんごの「髙木屋老舗」や「とらや(寅さんの実家として第1~4作目まで撮影に使われた)」、川魚の料理店やつくだ煮屋などが軒を連ねている。寅さんも食べた天丼が名物の「大和屋」で昼食とし、その天丼をいただいた。

寅さん記念館で目を引き付けられたのが、寅さんの実家のだんご屋の裏手の朝日印刷所(映画では寅さんとタコ社長との喧嘩のシーンが印象深い)で使われていた印刷業界の主流であった「活版印刷」をめぐる展示の部屋だ。「活字」を組み合わせ、インキをつけて、紙に押し当て印刷する方法で、その後のオフセット印刷、さらに今日のデジタル印刷への印刷技術の発展が想い返された。私の父は戦後、群馬県から上京し、神田川沿いで製本の仕事を営んだが、幼いころはよく製本機械のある喧しい工場で遊んでいたものだ。そして、私が教員になって初めての学級通信は、ガリガリと鉄筆で書いた「ガリ版(謄写版)」だった。その後コピー機が普及し、ワードプロセッサー(ワープロ)が登場して学校の印刷物も大きく変化していった。寅さんの「労働者諸君!」のセリフとともに、昭和の時代を思い出す。

寅さん記念館に併設された「山田洋次ミュージアム」も興味深い。展示室に山田洋次さんの言葉が掲示されている。①「ぼくの作品は、必ずといっていいほど社会からはみ出してしまった人間が主人公で、一流大学を出たエリートの技術者とか、権力者、実力者とかいう人が主人公になったことは一度もありません」、②「画面を見ているうちに、観客も出演者と一緒になってしまうような、映画館が教室になってしまうような、そんな映画ができたら、どんなに素晴らしいだろうか、と思った。それが映画『学校』のはじまりです」、何とも感銘深い言葉だ。『男はつらいよ』をはじめ、1977(昭和52)年の『幸福の黄色いハンカチ』、1988(昭和63)年からスタートし、脚本を担当した『釣りバカ日誌』、1993(平成5)年にスタートした『学校』シリーズの4部作、2002(平成14)年の時代劇『たそがれ清兵衛』など数々の作品を手掛けた山田洋次監督の、作品への思いに触れることができた。
「矢切の渡し」にも乗船した。徳川幕府は、江戸防衛のため川に橋を架けず、街道に続く渡船を厳しく管理していたが、江戸川の両岸に田んぼを持つ農民のための渡船は許していた。矢切の渡しは唯一現存する渡船で、千葉県・松戸市の矢切と東京都・葛飾区の柴又を結んでいる。今はモーターを使っているが、かつての川面を渡る手漕ぎの船の「ギーッギーッ」の音や、ヒバリ、ユリカモメの声などは、柴又帝釈天の大鐘楼の梵鐘の響きや界隈の昔ながらの呼び込みの声、参拝客のざわめきなどとともに“残したい日本の音風景100選”に選ばれている。政夫と民子(1981・昭和56年の映画では松田聖子が初主演を務めて話題となった)の悲しい恋を綴った伊藤左千夫の小説『野菊の墓』や、「♪♪連れて逃げてよ~♪♪」の歌い出しで有名な細川たかしの『矢切の渡し(1983・昭和58年)』が懐かしく思い出された。

右上:「矢切の渡し」の渡船
右下:鳴り響く音が“残したい日本の音風景100選”に選ばれている帝釈天の大鐘楼
近くには1926(大正15)年に開設された、東京ドーム5.5個分に相当する敷地を有する東京都水道局の金町浄水場がある。とんがり帽子で有名な、1941(昭和16)年に作られた第2取水塔は80年を過ぎても現役として稼働している。浄水場周辺は、『男はつらいよ』や1976(昭和51)年に連載が開始された両津勘吉(両さん)が主人公の漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』にも登場する。
立秋を過ぎて、本来なら藤原敏行が詠んだ「秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる(古今和歌集に収録)」のように、日中の暑さの中にも朝夕に少しずつ秋の訪れを感じるようになるものだが、ここ数年の暑さは尋常でない。残暑厳しきことが予想される。皆さま、ご自愛ください。
