退職金に厚生年金保険、定期昇給もない。「ないない尽くし」の外国公館スタッフ、その理由は。
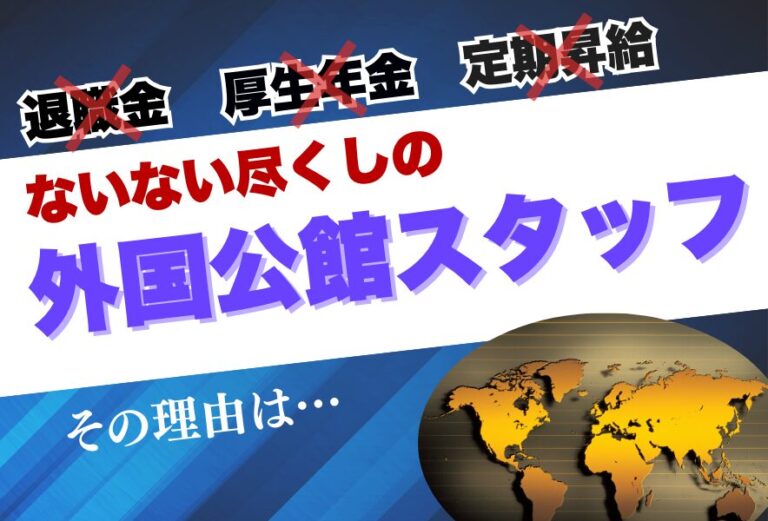
日本にある約180カ国・地域の外国公館(大使館・領事館など)では、母国から派遣された職員以外にも多くの日本で採用されたスタッフが働いている。大使館員というと語学を駆使した華やかな職場というイメージもある一方、日本で採用されたスタッフには賞与はおろか、退職金、交通費すら支給されず、厚生年金保険などの社会保険に未加入のケースも。なぜこうした「ないない尽くし」の職場になってしまっているのだろうか。
母国と日本の法律を都合良く使う
職員を苦しめる「リーガル・リンボ」
日本に大使館と3つの総領事館を置くブラジルの場合、現地職員には交通費も支給されず定期昇給も賞与も退職金もない。その上フルタイムであっても厚生年金保険に加入させてもらえない職員も多く、老後の生活不安につながっている。このため職員約120人が労働組合を組織し、待遇改善を求めている。
多くの国に共通するが、ブラジルでも外交官は「エリート中のエリート」で、大使館勤務にあこがれを抱く人も多いという。ブラジル大使館ユニオンの山﨑理仁委員長は「良い職場だと期待して応募し、責任感の伴うやり甲斐のある仕事をしているにもかかわらず、一般的な日本企業と比べても非常に待遇が低いと知り、衝撃を受ける人が多い」と説明する。

山﨑さんによるとブラジルは、賞与や退職金などを憲法や労働法で細かく定めると同時に、法的根拠のない財政支出を禁じる法律があるのだという。大使館側はこれらの法律をもとに、現地職員の処遇について「現地の法律で最低限決められた義務を果たす」という方針を打ち出している。このため日本で法的に義務付けられた雇用保険や労災保険には加入しているが、日本の法で明文化されていない退職金や諸手当はなく、厚生年金保険や健康保険も、1955年に当時の厚生省から「任意適用」の取り扱いが通知されていることを根拠に加入していない。
「定期昇給がないので物価高の中でも給与は変わらず、むしろ求人を出すたびに金額が引き下げられています。大使館が日本とブラジルの法律を都合よく使い分けることで、職員は『リーガル・リンボ(法的に宙に浮いた状態)』に苦しめられているのです」と、山﨑さんは訴えた。
パワハラに労働条件引き下げ
「闘うしかない」と職員が団結
ブラジル大使館では日本で採用された職員の3分の2、総領事館ではほぼ全員が日系ブラジル人で、残りが日本人という構成だ。これは職務上、日本の関係者や在日ブラジル人社会とのやりとりでポルトガル語と日本語両方の知識が要求されるからであり、ほぼ全員がバイリンガルだ。
「かつては『お金を稼いだら母国に帰る』という意識が強かった在日ブラジル人職員も、日本への定住が進むにつれて、労働環境の改善や社会保険の必要性を認識するようになりました」
2009年、ひどいハラスメントや不当解雇が横行したことをきっかけに、在東京総領事館で労働組合が結成された。その後大使館でも、本国の経済情勢を背景にシニア職員の雇い止めや長時間労働が頻発。さらに、労働条件を大幅に切り下げた就業規則を一方的に導入されそうになったことで「闘うしかない」と職員が団結し、組合を結成した。大使館と総領事館の組合が連携して交渉に当たった結果、就業規則の強行導入を食い止めたり、解雇事件を労働委員会で解決したりすることができた。
「組合があるとないとでは、絶大な差があります。就業規則の導入だけでなくハラスメントや不当解雇にも歯止めを掛けることができました」 世界に約200カ所あるブラジルの在外公館の中で組合がある国はほとんどなく、在日ブラジル公館の労働組合が最も組織率が高いという。山﨑さんは「ブラジル外務省は、年次報告書の現地職員に関する章で日本の成り行きを『注視する』としています。一定の規模があるからこそ、使用者に対して存在感を示せていると思います」とも話した。
「治外法権」の高いハードル
実効性の担保が課題に
在外公館職員が労働者として十分に保護されていないことは、2000年代に入ると国際的にも問題視されるようになった。このため国連は雇用契約について、「国とその財産を他国の裁判所で裁くことはできない」という裁判権免除の対象から外し、法改正により民事訴訟が提起できるようになった。
「それまでは違法な労働条件を押し付けられても、労働者には手の打ちようがなかった。裁判という手段ができたことで、労使交渉もしやすくなりました」(山﨑さん)
ただそれでも「治外法権」を持っているという使用者側の意識の壁は高く、日本側の公的機関が介入を避けたがる傾向があることを見越しているのか、労使交渉で不誠実な対応をとることもあるという。
ブラジル大使館・総領事館の労働組合の顧問を務める嶋﨑量弁護士は「日本の行政が日本で働く労働者への違法行為を正そうとしないなら問題です。軋轢が少ない行政指導など通じて、実効性のある救済を試みるべきではないでしょうか」と疑問を投げかけた。また行政としても、「外国公館に対して日本の労働法を遵守するよう啓発したり、日本の法律では労働組合を結成することが認められていると、職員に周知したりすることも考えられます」とも指摘した。

ブラジル大使館が2012年、雇用・労災保険に加入したのは、ハローワークが職員からの情報提供を受けて、大使館へ加入を求めたためだったという。山﨑さんはこの事例を踏まえ「大使館は日本の当局の働きかけには応じます。行政の指導には一定の効果があるので、しっかりやっていただきたい」と要望した。
声を上げ始めた外国公館職員
社会保険適用を
外国公館職員の待遇改善をサポートする情報労連によると、日本にある外国公館のうち社会保険に加入しているのは3割弱、領事館に至っては1割弱に留まり、未だに雇用・労災保険に加入していない外国公館も多数あるという。
2024年には、某国大使館の女性職員が雇用保険未加入のため育児休業給付金を受け取れなかったという事案も報道された。情報労連の水野和人書記長は「大半の大使館は、ブラジルのような労働組合がなく、職員も声を上げるすべを持っていません」と話す。

ただ情報労連が、山﨑さんらの活動を機関紙で紹介したところ、世界各国の外国公館職員から労働相談が寄せられるようになった。
「パワハラや過重労働による過労死、賃下げや解雇など相談の内容はさまざまです。中には雇用保険に未加入だったため、退職後に再就職のため職業訓練を受けたくとも、教育訓練給付を受給できなかったというケースもありました」(水野さん)
「組合をつくりたい」という相談もあるが、解雇に対する不安も強く、なかなか結成には至らないという。
「特に外国人職員の場合、解雇されると労働ビザを失い帰国せざるを得なくなることもある。日本人以上に弱い立場にあることが、組織化を難しくしています」(同)。
情報労連は、各国の外国公館職員を集めて勉強会などを開き、職場を超えたつながりづくりや情報共有に取り組んでいる。ブラジル大使館の山﨑さんもこうした場に参加し、連携を深めようとしている。
「先進諸国の多くは自国に駐在する外交官に対して、マニュアルで現地職員を採用する際に守るべき労働法や社会保障制度のガイドラインを明示しています。各国の外国公館職員と力を合わせて、日本政府にもガイドラインの策定などを働きかけていきたい」(山﨑さん)
連合は、各国の駐日外国公館職員の厚生年金保険や健康保険の加入を「任意適用」の取り扱いとしている、厚労省通知の見直しが必要だと考えている。日本の職場では一定の条件の個人事業所や、短時間労働者への適用が進められているにもかかわらず、外国公館職員にはフルタイムでも適用されないのは不合理だからだ。佐保昌一総合政策推進局長は「被用者であれば、原則として厚生年金保険や健康保険を適用すべきだと考えています。職場が違うだけで老後の生活格差が広がってしまうという事態を防ぐためにも、働きに見合った保障を受けられるよう通知の見直しを求めていきます」と述べた。

(執筆:有馬知子)